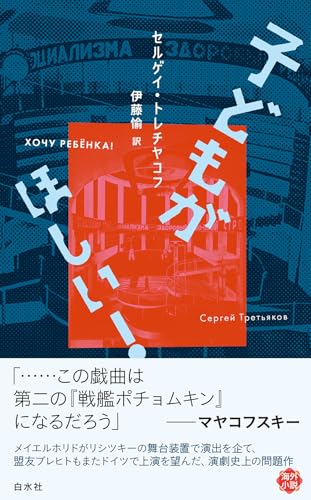書評
『モラルの話』(人文書院)
文学に何ができるか
南アフリカ出身のノーベル文学賞作家、クッツェーの最新短編集である。比較的短い七編から構成されるコンパクトな作りの本。しかし、それにしても「モラルの話」というタイトルを、ずばり直球で投げかけてくる剛直さは、いまどき稀(まれ)ではないか。もちろん、単純な道徳的教訓を引き出せるような作品集ではなく、文学的な企(たくら)みに満ちたものばかりである。最初のごく短い「犬」は、「猛犬」に吠(ほ)えられて恐怖心を抑えられなくなる女性の話で、あっという間に読み終えていったい何のことかと怪訝(けげん)にさえ思うのだが、本の全体を読んでから立ち返ってみると、人間と動物の関係、理性では制御できない情動、共感と暴力といった、本書全体を貫くモチーフが埋め込まれていることに気付く。次の「物語」は、束(つか)の間の不倫を楽しみながら、まったくやましさを感じず、幸せな結婚生活を続ける女性の話。
そして三つ目の「虚栄」以降の五編は、以前のクッツェー作品にも登場するエリザベス・コステロという架空の女性作家の晩年を点描していく連作になっている。六五歳の誕生日に年甲斐(としがい)もなく派手な変身を遂げて子供たちを驚かし、七二歳になって体が衰えてきても子供たちとの同居の誘いを頑とはねつけ、さらにいつの間にかスペインの片田舎に一人で移り住み、十数匹の野良猫を世話し、村の厄介者とされる露出癖の「愚者」まで引き取っている。そんな母の身を案じた息子がアメリカから訪ねてきて、「施設」への入居を勧めても、母は聞く耳を持たないばかりか、「本当の真実」を言っていないと逆に息子をなじる始末。
老いの問題に焦点を当てながら、常識破りの奇矯な老母と、多少偽善的なところがあるにせよ、常識的に親孝行な子供たちの間のやりとりが描かれている。辛辣(しんらつ)な味付けの喜劇として楽しめないこともない。しかし、クッツェーの「モラル」の真骨頂はその先にある。有名な作家である老母が、動物と人間の関係をめぐる現代最先端の倫理的な問題を突き付けてくるのだ。これはコステロの講演という形をとった『動物のいのち』(大月書店)という別の本でも既に展開されている議論だが、彼女はデカルトからヘーゲルに至る西欧哲学の底流にある、理性を基準として動物を人間と区別する考え方に批判的で、猫の魂にも共感できる想像力に基づいて行動しているのだ。
コステロという作家に託して論を展開するクッツェーのこうしたメタフィクション的な手法は、哲学を批判するだけでなく、文学に何ができるかを試す究極の試みにもなっている。動物論はいまやハイデガーやデリダ、アガンベン、シンガーといった哲学者たちの論考に支えられて目覚ましく発展し、動物と人間の関係をめぐる問題は文学研究でも盛んに取り上げられるようになっているが、クッツェーは実作者としてこういった思潮の転換の先頭に立ってきた。
『モラルの話』は、じつは原文の英語ではまだ本の形では出版されていない。英語版にさきがけて、まずスペイン語訳が、次に日本語訳が出ることになった。英語で流通する世界文学に対してささやかな抵抗をする世界的な英語作家、というのも逆説的な存在である。周縁にあって、中心に批判的なまなざしを向け続けること。政治家が息をするように嘘(うそ)を言い、ポスト真実が大手を振って通る世の中にあって、弱者を守るモラルの問題をあえて提起すること。こういう難題に取り組む作家のおかげで、文学は存在する価値を持ち続けられる。
ALL REVIEWSをフォローする