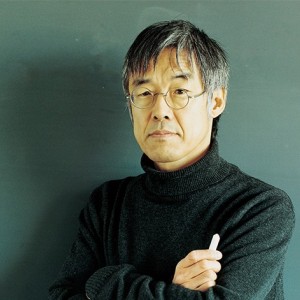書評
『カフカの父親』(白水社)
羽生名人ならびに小説における定跡について
羽生名人と対談をした。二回目だ。前回もそうだったが、羽生さんとは話が合うのである(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1996年頃)。どちらも天才だからだろうか(ウソウソ)。わたしとしては、将棋の天才の頭の中がどうなっているのか興味津々でいろいろ聞き出そうとするのだが、なかなかうまくいかない。やっぱり将棋をやらなくちゃわからないのかもしれない。
「ずいぶん昔、たとえば江戸時代の手なんかで参考になることはありますか」
「ありません。参考になるのは近代になってからですね」
やはり、将棋も言文一致以降でなくては「読む」理由がないのである。
「近代以降の作戦で、当時評価されずに後になってすごかったというようなことはあるんですか」
「升田さんの手はそうです。いまから考えるとすごい手だったけど、当時は理解されなかったんですね」
やはり、将棋界にもランボーやロートレアモンはいたのである。
「作戦に流行なんてあるんですか」
「あります。別に特許なんかないんで、誰かがいい手を指すと、パッと一気に流行ったりします」
やはり、……。
ところで、羽生さんに、棋士はふだんどうやって練習するのかとたずねた。過去にいろんな人が戦った戦跡をパソコンなんかで検討したり、時には同じ局面を指してみたりすると羽生さんは教えてくれた。
なるほど。小説を読んでいて、わたしもまたしょっちゅう同じようにその人の手を検討したりしている。自らの作品中で、同じ局面を指したりもするものなあ――というようなことを、トンマーゾ・ランドルフィの短編集『カフカの父親』(米川良夫・和田忠彦・柱本元彦訳、国書刊行会のち白水社)を読みながら、わたしは考えていた。
女中を自分でも止められぬ感情のままにイジメる「マリーア・ジュゼッパ」は、同じ手を太宰治が『黄金風景』の中で指していたし、音の重さや熱さや色や匂いや形を詳述する「『通俗歌唱法教本』より」はカルヴィーノが『柔かい月』で指した手の見本だったらしい。殺人犯が、論理的に考えすぎて捕まってしまう「ころころ」も、後にカルヴィーノが指した手だし、惚れ込んで『ランドルフィ名作選』を編纂しただけのことはあると妙な感心の仕方をしてしまったのだった。
ところで、いちばん面白い「ゴーゴリの妻」に出てくるゴーゴリの妻は人間ではなく(正体は読んでのお楽しみ)、それがゴーゴリの苦悩の源泉となっている。もちろん、この指し手はランドルフィの思いついた手ではなく、小説の定跡なのだが、こういう名作を読んでいると定跡も悪くないなあとか、この定跡を使ってみたいなあと小説家なら誰だって思うだろう。
実は、竣工間近のわたしの『ゴーストバスターズ』も、基本的には小説の定跡を踏みつつ、(これもまた小説家なら誰だってそう思うだろうが)新たな指し手を作り上げるつもりだった。
ところが! ある日、スティーヴン・キングの『ガンスリンガー』を読んでいてびっくり。わたしが新手の積もりで指していた手にたいへん似ていたのである。まずい。こんな作品がわたしのより先に出てるんじゃあ、キングを真似したと思われる!しかし、読み終えて、キングの新手は、わたしのとはよく似てはいるが発想がまるで違うことがわかってホッとしたのだった。
うーん、また出版されていない作品に触れてしまった。とにかく、キングの『ガンスリンガー』はすごいです。
※新版『カフカの父親』(白水社)は2018年11月5日発売
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする