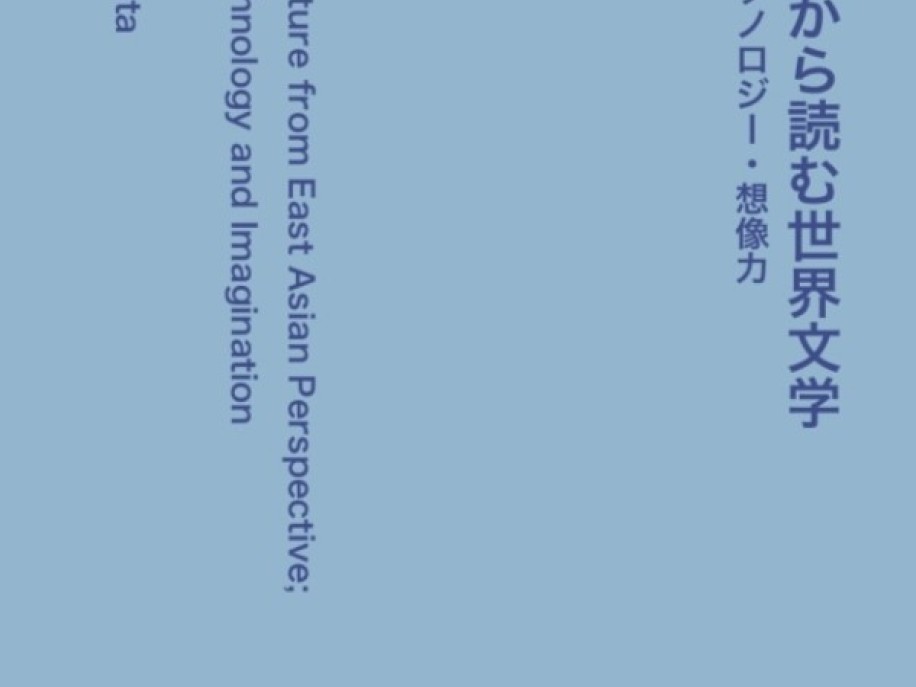書評
『82年生まれ、キム・ジヨン』(筑摩書房)
韓国に残る性差別浮き彫りに
フェミニズム小説としては、韓国では異例の大ヒットとなり、その後、世界を席巻する#MeTooムーヴメント(権力者から性被害や性差別を受けた女性が名乗り出る運動)に合流して、より大きな社会現象を生みだした話題の書である。二〇一五年、チョ・ナムジュがこの小説を書こうとしたきっかけは、あるヘイト発言を投げつけられたことだという。
マムチュン――。
作中ではヒロインのキム・ジヨン氏がぶつけられた言葉として、「ママ虫」と訳されている。「俺も旦那の稼ぎでコーヒー飲んでぶらぶらしたいよなあ……ママ虫もいいご身分だよな」と。「ママ虫」というと可愛い響きがあるが、元々はネットスラングで、「害虫」のようなかなり侮辱的な含意をもつ。
ジヨン氏はこの体験がもとで精神に異常をきたし、夫に連れられて精神科を受診する。本書は、彼女の診療カルテという体裁をとっているのだ。
「キム・ジヨン氏、三十三歳。三年前に結婚し、昨年、女の子を出産した。三歳年上の夫チョン・デヒョン氏と娘のチョン・ジウォンちゃんとともに、ソウルのはずれにある大規模団地の二十四坪のマンションに」賃貸契約で住んでいる。小さな広告代理店で働いていたが、出産とともに当然のように退職(させられた)。中堅のIT企業に勤める夫は毎日、帰宅は夜の十二時ごろで、土日も片方は出勤。
孤独とさまざまな鬱屈を抱えた彼女はある日、突如、異常行動を見せるようになった。ベランダに面した窓を開け、急に年寄りじみたしゃべりかたを始めたのだ。まるで、自身の実母が乗り移ったかのように。また、あるときは、はるか昔、夫に愛の告白をした女性が憑依(ひょうい)したように、夫に語りかける。妻のジヨンをもっと労(いた)わらないといけないと。
ヒロインが生まれた一九八〇年代の韓国では、「家族計画」という名称で、育児制限政策が展開されていた。ジヨン氏の下にできた子は出産前に女児と判明したため、母親がひとりで病院に行き、「消し」たと記述される。
ジヨンとは、一九八二年に韓国で生まれた女性のなかでいちばん多い、ありふれた名前だという。韓国の伝統社会のなかで、女性に生まれるとは、女児を産むとはどういうことか? ジヨン氏の心になにが起きているのか? ジヨン(ならびに多くの韓国女性は)幼いころから、男兄弟ばかり可愛がられる経験をしてきた。厳しい競争を勝ち抜いて大学に進んでも、就職しても、結局は男性がなにかにつけ優先されてしまう。雇用機会は不均等であり、キャリアの継続は至難の業だ。
さて、日本はどうだろう。表面上は平等を謳(うた)っていても、医大の女性合格率の操作などが発覚すれば、性差別が根深く残っていることを認めざるを得なくなる。女性の育休産休後の職場復帰の難しさ、家事育児の分担不平等など、歴然としてあることばかり。
本作は、ジヨン氏の精神分析医の日常で締め括(くく)られる。息子さんはADHDではないかと学校の担任に言われて断固否定する彼に、妻は、一日に十分も会わないのにどうしてわかるのか、あなたはシャーマンなのか、と痛烈に切り返す。それでも、彼に皮肉は通じない。病院では、出産のため病院を辞めることになった女性カウンセラーを高く評価しつつ、辞められると迷惑だから、次は未婚の人を探す、という。しかも、彼女を評価するのは、「顔は上品できれいだし」「気立てもいいし」「私が好きなコーヒーのブレンド」もちゃんと覚えていて買ってきてくれるから、だ。やれやれ!
ALL REVIEWSをフォローする