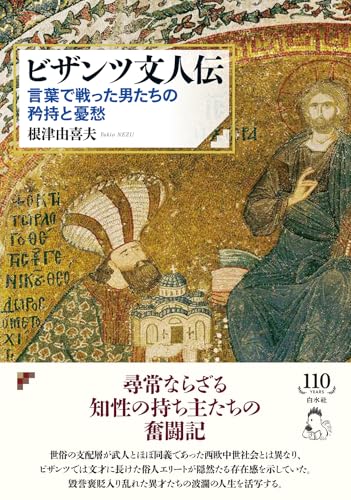後書き
『蛮行のヨーロッパ:第二次世界大戦直後の暴力』(白水社)
憎悪と暴力の連鎖に終止符を打つために知るべきこと
本書は、第二次世界大戦終結直後のヨーロッパの状況、とりわけ各地で行なわれた夥しい数の残虐行為を扱うものである。時期的にはドイツ降伏が近づく頃から一九四〇年代終わりに焦点が当てられ、その関連において一九三〇年代や戦時中に遡ったり、近くは二〇〇〇年代に至る出来事までも扱われる。すなわち国や地域ごとの通史的な歴史書ではなく、各々の現象を理解するために、場所や時間軸を行ったり来たりする構成となっている。その時期にヨーロッパの広範囲で荒れ狂った蛮行の詳細を一つ一つ取り上げることによって、著者は、戦争終結後すぐにヨーロッパは平和に向かって歩き始めたわけでは決してなく、そこでは戦いの一つの局面が終わったに過ぎなかった、それどころかむしろ戦争終結がさらなる別の残虐行為の起点にもなったことを強調する。「シュトゥンデ・ヌル(ゼロ時間)」、すなわち一九四五年五月にすべてがいったん白紙となったという見方に疑義を呈し、新たなヨーロッパの再建と復興へと着手されるまでに存在した混沌の状況に着目するのである。著者はまず、第二次世界大戦で引き起こされた物理的破壊の規模および実態を叙述することから始め、さらに「不在」、すなわちいかに膨大な数の人々やものが戦争で姿を消したのかを叙述することによって、戦争の残した遺産を把握するための枠組みを提示する。その際、死者数や破壊されたインフラの割合など具体的な統計の数字を多く挙げることと、体験・目撃した個々人の語りを引用することの両方によって、出来事の全体像に迫ろうとする。数々の事例に関して引用されている個人の語りには、印象的なものが少なくない。また、とりわけ第1部「遺産」第2章「不在」での統計および数字の扱いに関する文章に、著者は自身を従来の歴史学の流れのうちにというよりは、歴史家であると同時に作家と位置づけていることが読み取れる。
本書の第2部「復讐」では、ナチ・ドイツの暴虐が各地に呼び起こした反応として、ドイツ人並びに対独協力者に向けられた報復の数々の具体例が記述される。復讐と報復の波は、第二次世界大戦直後の残虐行為の主要なものの一つだった。著者は、報復がいくつかの目的のためには役に立ったことを認めつつも、荒れ狂った残虐行為が復讐と記述されることによってより理解しやすいものとなること、あるいは逆に復讐の非人道性があまりに強調されることによってもともとの犯罪の影が薄くなることのもつ危うさに言及し、また当然ながら「ホロコースト」と戦後のさまざまな報復行為の同一視には与しない。
後半の第3部「民族浄化」では、ウクライナ、ポーランドといった東欧諸国、戦後も存在し続けた反ユダヤ主義的言動が扱われ、人種と民族をめぐる戦いの側面が検討される。第4部「内戦」では、フランス、イタリア、ギリシア、ルーマニア、バルト諸国での内戦の事例が論じられ、混沌の中での権力の逆転や共産主義者の闘争の様子が描き出される。また、そこでは対独協力の有無とは無関係に、ずっと以前から自分たちを苦しめてきた者たちに対する反乱が生じていたことが指摘される。戦後の混沌と憎悪を活用した指導者たちの姿に関する記述は、第二次世界大戦が領土拡張をねらった闘争だっただけでなく、イデオロギーの戦争でもあった側面を思い起こさせる。
本書を貫く視点は、終戦直後は私たちの最近の歴史のうちで最も重要な時機の一つであり、今日のヨーロッパを真に理解するためには、まずこの決定的に形成的な時期のさなかに何が起きたかを理解しなければならないというものである。とりわけ、現在でも続いている憎悪や不和の根幹にあるものは何なのかを探るためには、この時代に関する理解が不可欠であり、憎悪と暴力のサイクルに終止符を打つためには、私たちはいかにして相競い合う歴史観が相並んで存在し得るかを示さなければならないと著者は主張する。全体の記述を通じて描かれるのは、第二次世界大戦がヨーロッパ社会にもたらした変容であり、これを読み解くには、権力や暴力ないしはイデオロギー的な力との関係を解きほぐすことが肝要であろう。
[書き手]猪狩弘美(桐朋学園大学ほか非常勤講師/ドイツ現代史)
ALL REVIEWSをフォローする