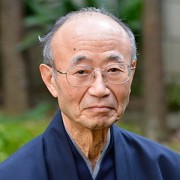書評
『マーガレット・ミードとサモア』(みすず書房)
人類学の名作を撃つ
文化人類学の分野で一世を風靡(ふうび)した「名作」が、実際にフタをあけてみると夢のような「神話」だったというお話である。マーガレット・ミードの「サモアの思春期」がそれだ。一九二〇年代のアメリカでは、人間の成長、行動の理論をめぐって二つの学派がしのぎをけずっていた。環境要因を重視する遺伝決定論と、教育要因を強調する文化決定論がそれだ。後者の文化決定論を代表するのが人類学の大御所フランツ・ボアズであったが、当時はまだ前者の環境決定論に押されぎみで意気があがらなかった。そこに飛燕(ひえん)のごとく登場してきたのがミードであった。
二十三歳の彼女は師のボアズの指示にもとづいて、南太平洋の米領サモア島におもむき、一年足らずのフィールド・ワークをへて驚くべき結論を持ち帰った。その島で思春期を過ごす少女たちは遺伝決定論者がいうような暗い抑圧とストレスのなかで成長するのではない、かれらはむしろ自由で開放的なセックスを楽しみ、平穏で気楽な明るい人生を送っていたのだという。「氏素生」という環境にたいして「育ち」という文化の力の勝利を、その調査報告書は高らかに宣言していたのである。こうしてミードの名声が時代の波にのって確立し、「サモアの思春期」が古典の地位によじのぼることになったのだ。
が、そこへ用意周到にして冷徹な反逆者があらわれた。オーストラリアを代表する人類学者で、本書の著者であるデレク・フリーマンである。彼はこの書で二〇年代のアメリカの学界事情を浮き彫りにするとともに、サモア島にかんする資・史料を精細に調べあげ、かつまたこの島の少女たちの間にみられる抑圧と葛藤(かつとう)の跡を克明に再現して、ミードのおこなったズサンな調査を痛烈に批判したのである。だが一読後、明るいサモアを構想したミードも、それにたいして暗いサモアを逆照射したフリーマンも、ともに類型的人間把握のワナにはまっているのではないかという思いがこみあげてきたのも事実である。
ALL REVIEWSをフォローする