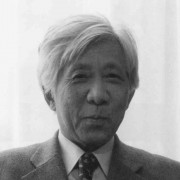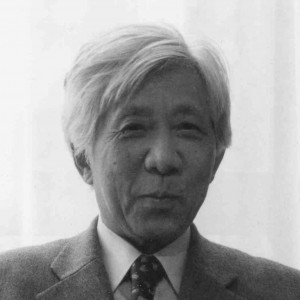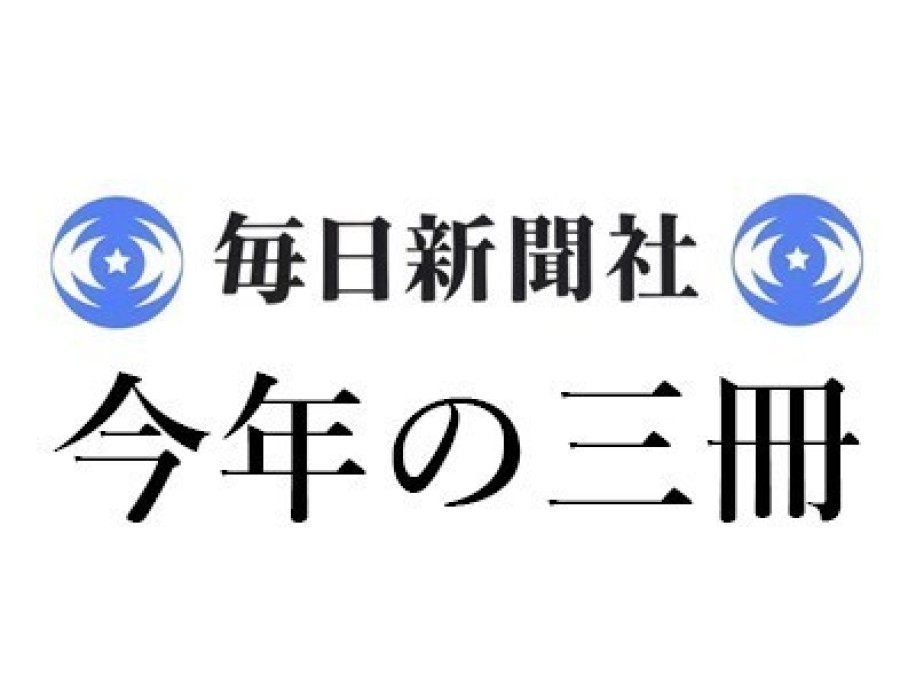書評
『バタイユ―消尽』(講談社)
”無効な消費”の美しさ読む
異端の思想家ジョルジュ・バタイユの、きわめて正統的な研究書が出た。著者の湯浅氏は、評者のように三十年も昔『有罪者』を翻訳出版した人間からすると、バタイユ研究の第二世代とでもいうべき人だ。ヘーゲルもソシュールもなまかじりのまま、難解なバタイユ本の邦訳を強行した第一世代に比べて、哲学、民俗学、言語学、宗教史、精神分析学など、バタイユ論を試みるのに欠かせないはずの勉強を、きちんとすませている。一世代分、目盛りは確実に先へ進んだと見ていい。
異端と書いたのは、ただの修辞ではない。バタイユの思想は、私たち人間の住む”有用性”の世界と正面から衝突する。彼が歓喜して肯定するのは、純粋に遊び自体が目的の、かぎりなく高揚してゆく子供たちの遊び、返礼を望まぬ際限のない贈与、”死”の淵を怖れない過激な性愛、全財産を、時には命そのものを賭ける賭博――つまりは、めぐりめぐって生産に奉仕することのない”非生産的消費”のすべてだ。
効用、効率優先の現代世界に異議申し立てをするのに、バタイユは、一晩に二万人もの捕虜の心臓をえぐりだしたアステカ人の宗教的供犠(くぎ)まで援用している。若いころ破滅的な放蕩にふけり、ロシアン・ルーレットを含む最大級の賭博を実行した人物の”提言”には、言ってみるだけのラディカリズムとは違った迫力がある。
この、無効だからこそ美しいといえそうな思想を、彼は戦後、ヘーゲル哲学に依拠する形で、全面的に理論化しようとした。湯浅氏の仕事は、そういう理論家バタイユを、その理論に即して読み解こうとする試みだ。かつてバタイユの「ハレルヤ」を翻訳しつつ、まぎれもない文学的陶酔を味わった評者には、この本の現代思想用語の大群は、いかにも重い。しかし、バタイユ論は一度、ここまで行くべきだったのだと思う。”文学”は、たぶんその先に出現するのだろう。
【新版】
ALL REVIEWSをフォローする