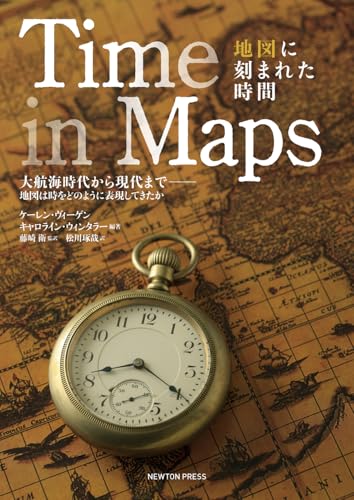書評
『静寂と沈黙の歴史』(藤原書店)
人間の感性の軌跡をたどる
誰でも自宅に個室をもちたがる。それは自然の願望だと思えるが、実のところ、個室への欲求は19世紀になってからにすぎないらしい。そこには、自分だけの空間、秘密の殻、静寂の場がある。「横暴な人間の顔は消え、私はもう自分に苦しむほか苦しまない。(…) 誰にも満足せず、自分に満足せず、静寂と夜の孤独のうちで、私は立ち直り、少しはうぬぼれてみたい」(ボードレール)という自分がいる。だが、自然の静寂がありふれている森林のような場所であれば、鳥や蛙(かえる)から葉っぱにいたるまでがかすかな音をつくりだす。静寂はいたるところにあるから、わざわざ探す意味がない。『森の生活』の思想家ソローは「音は静寂とほとんど同じである」と感じ、「静寂のみが聞くに値する」と結論づける。さらに、「砂漠には整然とした家のような深い静寂が君臨する」(サン=テグジュペリ)という。
原題にあるフランス語のシランス(silence)には、音やざわめきのない「静寂」と言葉や声のない「沈黙」という二つの意味がある。そこで、「感性の歴史」研究者として名高い著者は、一見すれば何の痕跡もない「静寂」と「沈黙」の歴史について探究する。作家や思想家からの引用をたっぷりと盛り込みながらの試みになる。
なによりも、静寂は音の不在だと思われているが、これは誤りだという。人が愛し合うとき、言葉や仕草よりも、ともに経験した静けさがものをいう。沈黙もまた声の消失ではなく、魂の言語なのだから。そこには人間の経験としての歴史の軌跡をたどる余地が残っている。
沈黙の探究は多種多様であり、聖なる領域にも浸透し、瞑想(めいそう)や祈りに伴っている。古代より瞑想が伝えられ、修道院で育まれ、16世紀には外に出て、俗人も手にできる内面の規範となる。それにルネサンス期の人文主義者(ユマニスト)が親しんでいた古典古代の倫理学が加わる。娯楽を排し一心に瞑想することが絶賛され、沈黙による内なる祈りが大衆化する。このプロセスは沈黙の歴史の核をなすのだ。
こうして沈黙は学ぶべきものになる。礼拝、学校、軍隊などで訓練され、慎み深い沈黙を身につける礼儀作法が求められた。それが規範となり、騒々しさは粗野と見なされた。しかしながら、思考は沈黙のなかでこそ働くのであり、言葉は思考を中断し窒息させる。だからこそ、平凡な日常生活のなかでは、沈黙はしばしば怖(おそ)れられ、沈黙のない場所が好まれることにもなる。
19世紀になると、大きな音をたてる機械があちらこちらに置かれ、荷車が通りで耳を聾(ろう)する音をたてる。やがて、それらの騒音が気にならない時期が過ぎると、朝の静寂を乱す雄鶏(おんどり)や犬の鳴き声にすら人々は不平をもらすようになった。静寂の個室が望ましくなったのは、まさしくこの頃のことだ。
見知らぬ間柄でも隣り合えば会話する。かつてそれは礼儀であり普通だった。ところが、20世紀後半になると、列車でも飛行機でも映画館でも、声を出すのは不作法になり、静寂が好まれるようになる。
現代はどうだろうか。昼間には電車で静寂を要求する人々であるのに、前の晩にはディスコやコンサートで強烈な音に熱狂し、これまで人類が経験したことがない音響に耐えている。まるで静寂は時に応じて断続的に求められるかのようだ。
それにしても最近の若者の歌には、これでもかといわんばかりに声をはりあげる饒舌(じょうぜつ)な曲が多い。バラードやブルースが好きな高齢世代には、あらためて音楽のなかにひそむ静寂と沈黙を思い知らされる。これってカラオケ愛好者の愚痴かもね。
ALL REVIEWSをフォローする