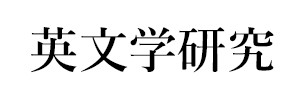書評
『「わたしのソーシャリズム」へ −−二〇世紀イギリス文化とレイモンド・ウィリアムズ』(研究社)
「文化」はいかにして生み出されるのか。本書は、この問いに突き動かされた著者が、レイモンド・ウィリアムズという人間の思想を読み解くことによって導き出した一つの回答ともいえる。「わたしのソーシャリズム」は、「個人」の〈意図〉によってのみ、もしくは「社会全体」の〈意図〉によってのみ文化の価値が生成されるわけではないというテーゼを示唆している。言い換えれば、それは「個人」のものの見方と、それとは必ずしも一致しない「共同体」のものの見方が複雑に絡まり合い、「関与」し合うヴィジョンである。ウィリアムズの著書だけでなく、同時代の小説、演劇、映画の分析を通して、この複雑なプロセスを丹念に、誠実に論じた研究書である。
限られた紙幅のうちでは各章の論点を網羅することができないため、ここでは大貫氏の広範な関心を束ねる「二重視(ダブル・ヴィジョン)」と、その概念を解きほぐしてくれる(と筆者が考える)ロマン主義思想に注目したいと思う。とりわけフリードリヒ・シュライアマハー(1768-1834)は、本書において文化生成の議論に援用されるだけでなく、後述するが、ウィリアムズの思想の源流にも通じている。このような観点から、著者が掲げる「二重視」をめぐる三つの位相について見ていきたい。
議論を進める前にシュライアマハーとロマン主義思想についてひとこと説明が必要であろう。彼の『宗教論』が実は『西洋思想大辞典』の「ロマン主義」の項でその定義に用いられており、彼の思想には「特殊性ないし個別性の強調、そして、無限なものと非合理なものとが人間の生の構成要素だという感覚」があることが提示されている。イギリス・ロマン主義研究者であれば、サミュエル・テイラー・コウルリッジの「個と全体」を想起するかもしれない。というのも、シュライアマハーが言及する「無限なもの」は「神」を示唆しつつも、決して人間の「生」の営為や「生長(グロウス)」から切り離せる超然としたものではなく、世界を包括する全体を理解しようとする感覚であるからだ(Streetman 110)。このロマン主義的な二重性は、シュライアマハーが既存の思想を「理解」するメカニズムを解明する際にも持ち込まれる。
これはどういうことか。他者の思想(が書かれた本)を読んだあとでその人物の立場に立てるほどその思想を熟知できれば、自分自身の考えと照らし合わせることもできる。この「対話」の論理は、個人の内面においても実践可能であり、そのプロセスによって二重性が生じるのだ。
ウィリアムズの文化生成に関する弁証法的なアプローチは、他者を「理解すること=対話に入ること」と考えたシュライアマハーの解釈学を彷彿とさせる。ここで意識したいのは、安酸敏眞氏が指摘しているように、シュライアマハーの「ロマン主義解釈学」が長らく非歴史主義という烙印を押され、一蹴されてきたことである。シュライアマハーにとっての解釈は、既存の思想の忠実な「再構成」であると理解されがちだが、最近になって実は歴史性を帯びるものだという見方が強まっている。現に、他者の思想を解釈する過程で再構成されるものは、「本来あったところの生ではない」とシュライアマハーはいう。彼にとって大事なことはむしろ「思惟によって現在の生との媒介を行うことにある」(安酸 47)。
これが二重視の一つ目の位相、「対話」である。過去と現在の思想との間に人間の「生」が媒介される二重視のプロセスは、本書の第一部の「翻訳と自由」(第1章と第2章)で取り上げられている。シュライアマハーのみならず、マシュー・アーノルドの翻訳論までもが論じられるのは、知性や精神の自由を獲得したリベラルな「個人」が新たな言語形態(フォーム)とともに「価値」を生み出すことに光を当てるためである。ここでは、単に言語を置換する「翻訳者」ではなく、「異なる言語から母語になにかを運び込む「移植者」」(26)、あるいは「一人ひとりの生きいきとした能力」に注目している(28)。
文化の「価値の創造者」は「共同体」であると主張したソシュールの論にさえ(52)、価値を生み出すある種の〈意図〉が含意されているという。大貫氏によれば、ソシュールの考える価値の創造プロセスには、人びとが価値体系に介入しようとする「漠たる意図」があり、それを事後的に記述する「観察者」の存在もある。
これが二つ目の二重視、つまり「観察」と「感情」との矛盾、またはこのどちらとも言えない「両義性」である。人びとの「漠たる意図」という見方を基軸にすれば、意図をもって文化を変容させようとするリベラルな諸個人(観察者)と、意図せずそれを変えてしまういわば感情的な(あるいは「盲目」の)大衆との境界線は必ずしも明確ではない。
知識人と呼ばれるようになる「特別な種類の人々」の系譜を辿ると(90)、一八世紀、ロマン主義時代の「天才」、すなわち類型化された「科学者」「芸術家」にまで遡ることができるだろう。おそらくわかりやすい例としては、サミュエル・ジョンソンの『幸福の探求―アビシニアの王子ラセラスの物語』(1759)があるが、学者イムラックや天文学者の俯瞰的なものの見方には、すでに感情の働きが含意されており、それはのちにメアリー・シェリーらロマン派作家たちが「天才」の役割を問い直すきっかけともなった。
「観察眼」を必要とする科学と、生命をもつ人間からは切り離せない「感情」との矛盾や両義性こそ、イギリス・ロマン派詩人たちの命題であった。ジョン・キーツによる『レイミア』で揶揄される科学的なものの見方は、本書の第8章の分析対象にもなっているウィリアムズの『ブラック・マウンテンズの人びと』(1981)に登場する知識人―「計測者(メジャラー)」ダール・メレド―のものの見方(172)とも響きあう。
これは、「オールド・ワンズ(いにしえの人)」と呼ばれる人びとの末裔が、ウェールズの南西部に広がるブラック・マウンテンズの自然環境において、厳しい制約にさらされながらも長い時間(数万年)をかけて文化や「場所の紐帯」を醸成していく物語である(160)。そこに描かれる「人びと」は複雑な感情をもち、盲目な大衆でもなければ、現実から距離をおく観察者(科学者)でもない。たとえば、羊飼いのカラーンはメンヴァンディルという土地からやってきたダール・メレドの思想に耳を傾ける。ダール・メレドは豊かな知識を得て「計測者」として高みに登りつめた人物であったが、結局それによって生じる権力関係を忌避し、カラーンが暮らす集落にやってきたのだった。「尾根(リッジ)」をめざすのが誰であれ、そこにたどり着いてもなおその先に別の「尾根」を発見するという象徴的な物語でもある。
第二部(第3章から第5章)の「二重視の諸相」では、ウィリアムズのこのような「二重」のものの見方を分析する前段階として、同時代作家たちの階級的な「二重の視点(ダブルアイ)」を紹介している。まず、名門一族の出身であったコリン・マッキネスは、『アブソリュート・ビギナーズ』(1959)という小説の中で、自分とは全く縁のない労働者階級の若者集団を観察対象とし、彼らの生活やものの見方を鮮やかに描いている。かつてはワーキングクラスの連帯を重んじた若者たちが、平均賃金の上昇と共に消費するためのお金を稼ぎ始めるのである(66)。
実際にこのような「二重視」、または「ダブル・アイ」という言葉を用いたのはカルチュラル・スタディーズの創設者のひとりリチャード・ホガートであった(73)。ホガートは『読み書き能力の効用』(1957)において、「金」よりも「愛情」と「友情」に価値を見いだした労働者階級のものの見方を「やつらとおれたち」という言葉に集約させつつ(「やつら」はミドルクラス)、「こういうものの見方だけでは駄目なんだ……誰もがダブル・アイをもたねばならない」(74-5)と主張し、この階級間の分断を問題視している。
「個」と「社会」の弁証法の最たる例としてベルトルト・ブレヒトの前衛演劇の手法が論じられている。ブレヒトの『肝っ玉おっ母』は、従来のカタルシスで感情移入を促す手法ではなく、観客が登場人物から適切な距離をとり観察できるような演出をしている。これは、現実の出来事からの「距離化」が必要と考えるブレヒトのマルクス主義が背景にある。社会的なプロセスは個人の意識では把握できないという前提に基づき(87)、あえて観客の客観視、弁証法的な思考を促すべく、主人公の悲劇と彼女の「盲目性」が強調されるのである。
デヴィッド・ヘアの『プレンティ』(1978)は、ブレヒト的な二重視を離れ、ウィリアムズ的な感情と生の二重視に近づいている。この劇は、ナチス占領下のフランスで出会った諜報員の男性との一夜が忘れられず、何事にも妥協できない主人公スーザンが破滅していく悲劇の物語である(96)。たとえば、占領が終わっても物質的問題を抱え憂鬱なフランスの農夫と、それには気づかないスーザンの「盲目」が対比されている。不自然なほど明るく「こんな日がずっとずっと続いていく」といい放つスーザンに感情移入する観客自身の「盲目」をも問う仕組みになっている。観客はスーザンの「盲目」を凝視しながらも、その「受け入れがたい生の現実」(109)に巻き込まれ、その結果、俯瞰する観察者と盲目の大衆(スーザン)の境界線が曖昧になるのだ。
こうして「書き手」―ウィリアムズ、マッキネス、ホガース、ブレヒト、ヘア―と「人びと」―カラーン、ワーキングクラスの若者、肝っ玉おっ母、スーザン―とを分かつ境界線について、大貫氏が思いを巡らせるのは、ウィリアムズが用いた「尾根(リッジ)」というメタファーの意味を深く掘り下げるためではないだろうか。
ブラック・マウンテンズの人びとが「尾根」を目指すとして、ではどうやって俯瞰するのか。「飛翔する鳥」の目で一気に(あるいは性急に)概観してしまうのか(171)、それとも、ゆっくり歩いて登るのか。「人びと」と「書き手」を分かつものはなんなのか。
一つの「尾根」を発見してもまた別の「尾根」が出てくるプロセスが「永遠に繰り返される」というのは、明らかに時間性を意識している。
この時間性が三つ目の二重性である。「性急」に答えを求めようとする個人がいるとしても、実際「文化」や「場所の紐帯」が醸成されるプロセスは遅々としている。キーツが性急さを否定し代わりに称揚した「不確かさや、不可解なことや、疑惑ある状態の中に人が留まることができる」ネガティヴ・ケイパビリティとも類した状態といえよう。語源的にも「自然の作物が生長していくのを世話する」という意味を持つ「文化」が形成されるプロセスは「地(質)学的想像力とでも呼称すべき経験の蓄積」(114)といった大局観にもつながる。
そして、このプロセスには人為的な関与がある。ウィリアムズが自然主義的な「進化」というものの見方を、人間が関与する「集団的な成長」(159)として捉えなおそうとするのも、人びとが、不測の事態が起きてはそれを解決し、またそれを繰り返してゆく人間的営為あるからだ。これこそ、まさに共同体の「回復力(リジリエンス)」であり(162)、ウェールズという「場所」とともに文字通り成長したウィリアムズの文化の思想ともいえる。
本書は、文学、歴史、思想を縦横無尽に論じながらも緻密に二〇世紀イギリス文化の変容を論じた優れた研究書である。ただ残念なのは、「二重視」という枠組みに拘泥しすぎるあまり、ロマン主義の捉え方がいささか偏狭になっていることである。たしかに、ロマン主義時代には天才の「(鼻持ちならない)「特別さ」」が強調されたかもしれない(91)。しかし、「ロマン主義」と「感情のリベラリズム」の間にそれほど大きな溝が存在するだろうか。前者を「個人を絶対的なものへと変容させる」思想(123)として捉えるより、むしろ個人と社会をつなごうとしたウィリアムズの思想の源流と見なしたほうよいようにも思われる。「自分のなかに内部化された社会に直面する」感情構造を認めたウィリアムズ以前に、「言語の生命」とその「移植」を推進したシュライアマハーの思想が存在したことは大貫氏自身が論じている通りである。
とはいえ、だれでも知識人たりうるというウィリアムズの「個人」についてのものの見方はわれわれが生きる現代社会に最も必要であるに違いない。ウィリアムズの「感情のリベラリズム」は、タイトルの「わたしの」と響きあいながら、ウェールズについて「だれもが語るべきであり、だれもが語る権利を持つ」(93)ことを力強く支持しているのだ。
参照文献
Streetman, Robert F. “Romanticism and the Sensus Numinis in Schleiermacher.” The Interpretation of Belief: Coleridge, Schleiermacher and Romanticism. Ed. David Jasper. Basingstoke: Macmillan, 1986.
Williams, Raymond. People of the Black Mountains I: The Beginning. . . . London: Chatto and Windus, 1989.
安酸敏眞 「シュライアーマッハーにおける一般解釈学の構想」、北海学園大学人文論集5(2011):231-59。
フィリップ・P・ウィーナー編 『西洋思想大辞典』全5巻、平凡社、1990年。
ヴォルフガング・H・プレーガー 『シュライアーマッハーの哲学』増渕幸男訳、玉川大学出版、1998年。
本多峰子 「シュライエルマッハー『宗教論:宗教を軽んずる教養人への講話』と、英国ロマン派詩人について」、二松學舍大學論集47 (2004):75-94。
限られた紙幅のうちでは各章の論点を網羅することができないため、ここでは大貫氏の広範な関心を束ねる「二重視(ダブル・ヴィジョン)」と、その概念を解きほぐしてくれる(と筆者が考える)ロマン主義思想に注目したいと思う。とりわけフリードリヒ・シュライアマハー(1768-1834)は、本書において文化生成の議論に援用されるだけでなく、後述するが、ウィリアムズの思想の源流にも通じている。このような観点から、著者が掲げる「二重視」をめぐる三つの位相について見ていきたい。
議論を進める前にシュライアマハーとロマン主義思想についてひとこと説明が必要であろう。彼の『宗教論』が実は『西洋思想大辞典』の「ロマン主義」の項でその定義に用いられており、彼の思想には「特殊性ないし個別性の強調、そして、無限なものと非合理なものとが人間の生の構成要素だという感覚」があることが提示されている。イギリス・ロマン主義研究者であれば、サミュエル・テイラー・コウルリッジの「個と全体」を想起するかもしれない。というのも、シュライアマハーが言及する「無限なもの」は「神」を示唆しつつも、決して人間の「生」の営為や「生長(グロウス)」から切り離せる超然としたものではなく、世界を包括する全体を理解しようとする感覚であるからだ(Streetman 110)。このロマン主義的な二重性は、シュライアマハーが既存の思想を「理解」するメカニズムを解明する際にも持ち込まれる。
〔思想を理解するプロセスは〕二重の仕方で生じうるであろう。つまり一つは、個々の人間が他者との対話をとおして、よりよい考えに至ることによってである。したがって、そこではまさに弁証法が、こうした変化の根拠であろう。もう一つは、自分自身で熟慮し熟考することによって、またより純粋な思想や表象に行き着くことによってである。(シュライアマハー;プレーガー 172)
これはどういうことか。他者の思想(が書かれた本)を読んだあとでその人物の立場に立てるほどその思想を熟知できれば、自分自身の考えと照らし合わせることもできる。この「対話」の論理は、個人の内面においても実践可能であり、そのプロセスによって二重性が生じるのだ。
ウィリアムズの文化生成に関する弁証法的なアプローチは、他者を「理解すること=対話に入ること」と考えたシュライアマハーの解釈学を彷彿とさせる。ここで意識したいのは、安酸敏眞氏が指摘しているように、シュライアマハーの「ロマン主義解釈学」が長らく非歴史主義という烙印を押され、一蹴されてきたことである。シュライアマハーにとっての解釈は、既存の思想の忠実な「再構成」であると理解されがちだが、最近になって実は歴史性を帯びるものだという見方が強まっている。現に、他者の思想を解釈する過程で再構成されるものは、「本来あったところの生ではない」とシュライアマハーはいう。彼にとって大事なことはむしろ「思惟によって現在の生との媒介を行うことにある」(安酸 47)。
これが二重視の一つ目の位相、「対話」である。過去と現在の思想との間に人間の「生」が媒介される二重視のプロセスは、本書の第一部の「翻訳と自由」(第1章と第2章)で取り上げられている。シュライアマハーのみならず、マシュー・アーノルドの翻訳論までもが論じられるのは、知性や精神の自由を獲得したリベラルな「個人」が新たな言語形態(フォーム)とともに「価値」を生み出すことに光を当てるためである。ここでは、単に言語を置換する「翻訳者」ではなく、「異なる言語から母語になにかを運び込む「移植者」」(26)、あるいは「一人ひとりの生きいきとした能力」に注目している(28)。
文化の「価値の創造者」は「共同体」であると主張したソシュールの論にさえ(52)、価値を生み出すある種の〈意図〉が含意されているという。大貫氏によれば、ソシュールの考える価値の創造プロセスには、人びとが価値体系に介入しようとする「漠たる意図」があり、それを事後的に記述する「観察者」の存在もある。
これが二つ目の二重視、つまり「観察」と「感情」との矛盾、またはこのどちらとも言えない「両義性」である。人びとの「漠たる意図」という見方を基軸にすれば、意図をもって文化を変容させようとするリベラルな諸個人(観察者)と、意図せずそれを変えてしまういわば感情的な(あるいは「盲目」の)大衆との境界線は必ずしも明確ではない。
知識人と呼ばれるようになる「特別な種類の人々」の系譜を辿ると(90)、一八世紀、ロマン主義時代の「天才」、すなわち類型化された「科学者」「芸術家」にまで遡ることができるだろう。おそらくわかりやすい例としては、サミュエル・ジョンソンの『幸福の探求―アビシニアの王子ラセラスの物語』(1759)があるが、学者イムラックや天文学者の俯瞰的なものの見方には、すでに感情の働きが含意されており、それはのちにメアリー・シェリーらロマン派作家たちが「天才」の役割を問い直すきっかけともなった。
「観察眼」を必要とする科学と、生命をもつ人間からは切り離せない「感情」との矛盾や両義性こそ、イギリス・ロマン派詩人たちの命題であった。ジョン・キーツによる『レイミア』で揶揄される科学的なものの見方は、本書の第8章の分析対象にもなっているウィリアムズの『ブラック・マウンテンズの人びと』(1981)に登場する知識人―「計測者(メジャラー)」ダール・メレド―のものの見方(172)とも響きあう。
これは、「オールド・ワンズ(いにしえの人)」と呼ばれる人びとの末裔が、ウェールズの南西部に広がるブラック・マウンテンズの自然環境において、厳しい制約にさらされながらも長い時間(数万年)をかけて文化や「場所の紐帯」を醸成していく物語である(160)。そこに描かれる「人びと」は複雑な感情をもち、盲目な大衆でもなければ、現実から距離をおく観察者(科学者)でもない。たとえば、羊飼いのカラーンはメンヴァンディルという土地からやってきたダール・メレドの思想に耳を傾ける。ダール・メレドは豊かな知識を得て「計測者」として高みに登りつめた人物であったが、結局それによって生じる権力関係を忌避し、カラーンが暮らす集落にやってきたのだった。「尾根(リッジ)」をめざすのが誰であれ、そこにたどり着いてもなおその先に別の「尾根」を発見するという象徴的な物語でもある。
第二部(第3章から第5章)の「二重視の諸相」では、ウィリアムズのこのような「二重」のものの見方を分析する前段階として、同時代作家たちの階級的な「二重の視点(ダブルアイ)」を紹介している。まず、名門一族の出身であったコリン・マッキネスは、『アブソリュート・ビギナーズ』(1959)という小説の中で、自分とは全く縁のない労働者階級の若者集団を観察対象とし、彼らの生活やものの見方を鮮やかに描いている。かつてはワーキングクラスの連帯を重んじた若者たちが、平均賃金の上昇と共に消費するためのお金を稼ぎ始めるのである(66)。
実際にこのような「二重視」、または「ダブル・アイ」という言葉を用いたのはカルチュラル・スタディーズの創設者のひとりリチャード・ホガートであった(73)。ホガートは『読み書き能力の効用』(1957)において、「金」よりも「愛情」と「友情」に価値を見いだした労働者階級のものの見方を「やつらとおれたち」という言葉に集約させつつ(「やつら」はミドルクラス)、「こういうものの見方だけでは駄目なんだ……誰もがダブル・アイをもたねばならない」(74-5)と主張し、この階級間の分断を問題視している。
「個」と「社会」の弁証法の最たる例としてベルトルト・ブレヒトの前衛演劇の手法が論じられている。ブレヒトの『肝っ玉おっ母』は、従来のカタルシスで感情移入を促す手法ではなく、観客が登場人物から適切な距離をとり観察できるような演出をしている。これは、現実の出来事からの「距離化」が必要と考えるブレヒトのマルクス主義が背景にある。社会的なプロセスは個人の意識では把握できないという前提に基づき(87)、あえて観客の客観視、弁証法的な思考を促すべく、主人公の悲劇と彼女の「盲目性」が強調されるのである。
デヴィッド・ヘアの『プレンティ』(1978)は、ブレヒト的な二重視を離れ、ウィリアムズ的な感情と生の二重視に近づいている。この劇は、ナチス占領下のフランスで出会った諜報員の男性との一夜が忘れられず、何事にも妥協できない主人公スーザンが破滅していく悲劇の物語である(96)。たとえば、占領が終わっても物質的問題を抱え憂鬱なフランスの農夫と、それには気づかないスーザンの「盲目」が対比されている。不自然なほど明るく「こんな日がずっとずっと続いていく」といい放つスーザンに感情移入する観客自身の「盲目」をも問う仕組みになっている。観客はスーザンの「盲目」を凝視しながらも、その「受け入れがたい生の現実」(109)に巻き込まれ、その結果、俯瞰する観察者と盲目の大衆(スーザン)の境界線が曖昧になるのだ。
こうして「書き手」―ウィリアムズ、マッキネス、ホガース、ブレヒト、ヘア―と「人びと」―カラーン、ワーキングクラスの若者、肝っ玉おっ母、スーザン―とを分かつ境界線について、大貫氏が思いを巡らせるのは、ウィリアムズが用いた「尾根(リッジ)」というメタファーの意味を深く掘り下げるためではないだろうか。
ブラック・マウンテンズの人びとが「尾根」を目指すとして、ではどうやって俯瞰するのか。「飛翔する鳥」の目で一気に(あるいは性急に)概観してしまうのか(171)、それとも、ゆっくり歩いて登るのか。「人びと」と「書き手」を分かつものはなんなのか。
ものごとのなかには単純なものもある。だが、君らが住んでいる山々のようなものもあるんだ。ひとつの尾根をみて、そこに登るとする。ところが、そこにやっとたどりついたら、その尾根のはるかむこうには別の尾根が見える。そして、また別の尾根が出てくる。これが永遠に繰り返されるような気さえしてくる。(Williams 173;大貫 171)
一つの「尾根」を発見してもまた別の「尾根」が出てくるプロセスが「永遠に繰り返される」というのは、明らかに時間性を意識している。
この時間性が三つ目の二重性である。「性急」に答えを求めようとする個人がいるとしても、実際「文化」や「場所の紐帯」が醸成されるプロセスは遅々としている。キーツが性急さを否定し代わりに称揚した「不確かさや、不可解なことや、疑惑ある状態の中に人が留まることができる」ネガティヴ・ケイパビリティとも類した状態といえよう。語源的にも「自然の作物が生長していくのを世話する」という意味を持つ「文化」が形成されるプロセスは「地(質)学的想像力とでも呼称すべき経験の蓄積」(114)といった大局観にもつながる。
そして、このプロセスには人為的な関与がある。ウィリアムズが自然主義的な「進化」というものの見方を、人間が関与する「集団的な成長」(159)として捉えなおそうとするのも、人びとが、不測の事態が起きてはそれを解決し、またそれを繰り返してゆく人間的営為あるからだ。これこそ、まさに共同体の「回復力(リジリエンス)」であり(162)、ウェールズという「場所」とともに文字通り成長したウィリアムズの文化の思想ともいえる。
本書は、文学、歴史、思想を縦横無尽に論じながらも緻密に二〇世紀イギリス文化の変容を論じた優れた研究書である。ただ残念なのは、「二重視」という枠組みに拘泥しすぎるあまり、ロマン主義の捉え方がいささか偏狭になっていることである。たしかに、ロマン主義時代には天才の「(鼻持ちならない)「特別さ」」が強調されたかもしれない(91)。しかし、「ロマン主義」と「感情のリベラリズム」の間にそれほど大きな溝が存在するだろうか。前者を「個人を絶対的なものへと変容させる」思想(123)として捉えるより、むしろ個人と社会をつなごうとしたウィリアムズの思想の源流と見なしたほうよいようにも思われる。「自分のなかに内部化された社会に直面する」感情構造を認めたウィリアムズ以前に、「言語の生命」とその「移植」を推進したシュライアマハーの思想が存在したことは大貫氏自身が論じている通りである。
とはいえ、だれでも知識人たりうるというウィリアムズの「個人」についてのものの見方はわれわれが生きる現代社会に最も必要であるに違いない。ウィリアムズの「感情のリベラリズム」は、タイトルの「わたしの」と響きあいながら、ウェールズについて「だれもが語るべきであり、だれもが語る権利を持つ」(93)ことを力強く支持しているのだ。
参照文献
Streetman, Robert F. “Romanticism and the Sensus Numinis in Schleiermacher.” The Interpretation of Belief: Coleridge, Schleiermacher and Romanticism. Ed. David Jasper. Basingstoke: Macmillan, 1986.
Williams, Raymond. People of the Black Mountains I: The Beginning. . . . London: Chatto and Windus, 1989.
安酸敏眞 「シュライアーマッハーにおける一般解釈学の構想」、北海学園大学人文論集5(2011):231-59。
フィリップ・P・ウィーナー編 『西洋思想大辞典』全5巻、平凡社、1990年。
ヴォルフガング・H・プレーガー 『シュライアーマッハーの哲学』増渕幸男訳、玉川大学出版、1998年。
本多峰子 「シュライエルマッハー『宗教論:宗教を軽んずる教養人への講話』と、英国ロマン派詩人について」、二松學舍大學論集47 (2004):75-94。
ALL REVIEWSをフォローする