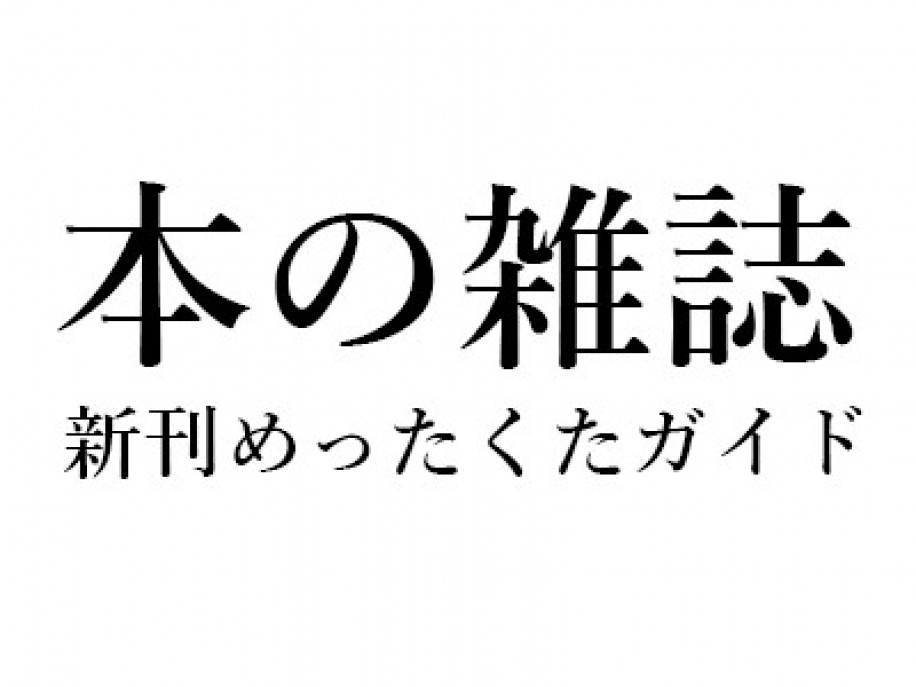書評
『SOSの猿』(中央公論新社)
「謎」の背後に本当の「謎」がある
手に取って帯を見るとこう書かれている。「ひきこもり青年の『悪魔祓(ばら)い』を頼まれた男と、一瞬にして三〇〇億円の損失を出した株誤発注の原因を調査する男。そして、斉天大聖・孫悟空――救いの物語をつくるのは、彼ら」
どんな小説かまったく見当がつかないのではないだろうか。荒唐無稽にさえ映るけれど、実際かなり荒唐無稽な小説である。
他人の発するSOS信号に敏感で、悪魔祓いの心得を持ち、ひきこもり青年救済に動く「私(遠藤二郎)」を語り手とした「私の話」。株誤発注事件の原因を、非人間的なまでの合理性で追究する「五十嵐真」を軸とした「猿の話」。このふたつの話が交互に平行するかたちで小説は進行する。
もちろんふたつの話は関係し合っており、やがてひとつに収束していく。そのなかで浮かび上がってくるのが「物語による救い」の物語で、孫悟空はふたつの話を縫い合わせ「『物語による救い』の物語」を紡ぎ上げる役割を果たしている。ほかにも、孔子と孟子、エクソシスト、ユングなど意表を突く設定満載である。
遠藤二郎が救おうとしているひきこもり青年と、五十嵐真が追う株誤発注事件、一見まったく無関係な両者のあいだに横たわる「因果関係」が読者を引っ張る謎なのだが、それは表面的な「謎」にすぎない。
「猿の話」のパートは毎度「さて、どうなるかはお次の回にて」といった言葉で締め括られている。中心人物・五十嵐真を「狂言回し」と呼び、「おまえたち」と誰かに話しかける正体不明の語り手が背後にいるのだ。この語り手の正体と、彼の語る「猿の話」が担っている意味、それらこそが小説全体のテーマ「物語による救い」に直に繋がる本当の「謎」なのである。
……どんな小説か、ますますわからなくなってしまっただろうか?
『SOSの猿』が以上のような、荒唐無稽でしかも錯綜した作品になっているのには理由がある。この小説は『読売新聞』夕刊に連載されたものだが、マンガ家・五十嵐大介とのコラボレーションであり、「猿」「孫悟空」「エクソシスト」などのキーワードは五十嵐の発案によるものだという。それらをもとに意見交換をし、物語をつくっていったそうで、早い話が三題噺であり、来年早々に『月刊IKKI』に発表されるという五十嵐のマンガ『SARU』と突き合わせて判断されるべき作品なのだ。
だがむろん、独立した作品として評価されることから逃れることはできない。課せられた制約を考えると、取り留めのないキーワード群をここまで破綻の少ない(皆無とはいえない)物語に組み上げた構想力・構成力は驚異的ではあるが、実験的だった前作『あるキング』同様、古くからの伊坂ファンのあいだでは賛否が分かれるだろう。しかし物語に心地よく乗ることだけが小説の読み方ではない。新しい方向の模索に動き出している作家・伊坂幸太郎の試みそれ自体を味わい見定めていくこともまた、同時代の読者に与えられた楽しみであり特権である。
ALL REVIEWSをフォローする