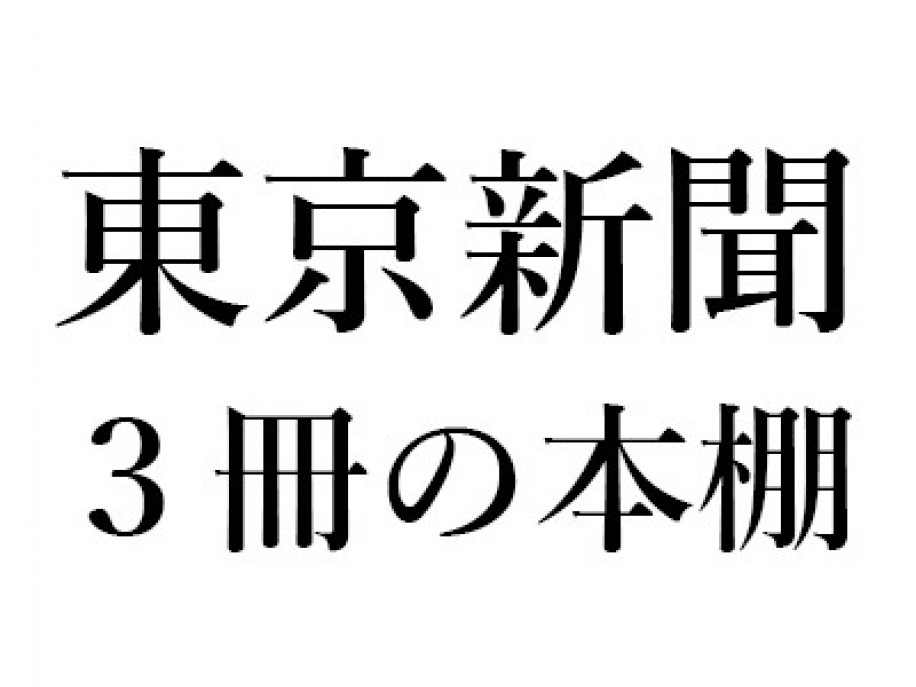書評
『散歩のとき何か食べたくなって』(新潮社)
名代名物富士そば、池波正太郎
七月末から、都内某ホテルに「缶詰」になっている。「缶詰」などという柄ではないが、諸般の事情によりこうなってしまった。他のどの作家の方がなっても、自分だけはそんな目にあうまい、だいたいそんな状況下では書けるものも書けない――と思っていたが、これはたいへん具合がよろしい。やはり、場所のせいか。ちょっと出かけて、タクシーで帰る。その際、ホテルの名前をいう。すると、運ちゃんが「ああ、池波正太郎さんがよく泊まられたところですね」。これがすでに三回。池波正太郎は死んでもすごい。折角だから、ホテルにいる間は、池波正太郎を読むことにしようと思った。歩いて数分の「書泉グランデ」で文庫本を買って、ベッドに横たわって読む。アルゴンクィンホテルに泊まれば「ニューヨーカー」御用達の作家を読む。横浜山手の大佛次郎記念館の喫茶店「霧笛」に入ったら、港が見える側の席に座って『パリ燃ゆ』を読む。それが礼儀というものである。まあ、他人に強制するものではないけれど。そういうわけで、ここでは当然池波正太郎である。『剣客商売』や『鬼平犯科帳』はだいたい読んでいたので再読、あるいは再々読、いや再々々読。『仕掛人藤枝梅安』や『真田太平記』はほとんど読んでいなかったので初読。 浩瀚(こうかん)なエッセイは読んでいたのもなかったのもいろいろ。当たり前だが、イヤになるぐらい面白い。池波正太郎の面白さは、いろんな人がいろんなところでいったり書いたりしているのでパス。
私が子供のころの、東京の下町に住む人々にとっては、その居住区域が一つの〔国〕といってもよかったほどで、たとえば浅草なら浅草、下谷や入谷に住んでいれば、そこで、ささやかながらも生活のすべてが過不足なくととのえられていったのである。仕事をもつ男たちは、他の土地へも町へも出て行ったろうが、女や子供たちは、ほとんど一年中を自分が住む町ですごした。そこには、かならず、小さいながらも映画館があり、寄席があり、洋食屋も支那飯屋も、蕎麦屋も鮨屋もあって、目と耳と口をたのしませる手段に、『事を欠かなかった……』ものなのだ。(『散歩のとき何か食べたくなって』新潮文庫、「横浜あちらこちら」)
池波正太郎の本領はこんなところにある。世界が小さかった頃をユートピアと感じることのできる人がいる限り、彼はずっと読まれ続けるだろう。
昨日は、単行本が出た時読んでなかった『原っぱ』(新潮文庫)を読んでいた。池波正太郎には珍しい「現代小説」(?)だが、いま現にその「現代小説」を書きつつある身で読むと、複雑な感慨に襲われる。主人公の恩師で、いまでいうホームレスになってしまった「佐土原先生」の登場の仕方を読んでいると、しみじみ、こういうのも書きたいなあと思う。だが、ぼくにはそのために必要ななにかがすでにないのである。
池波正太郎が愛した神田界隈を、ぼくも深夜うろついている。ぼくが出かけるのは「書泉グランデ」の正面にある「名代名物富士そば」だ。よくある「立ち食いそば」の店である。そこで、天ぷら玉子そば+いなり寿司を食べてホテルに帰る。さすがの池波正太郎もここには行かなかっただろう。時間は午前五時。もう、朝は近い。ホテルのロビーも暗い。ロビーの壁には、池波正太郎が描いた二枚の絵が飾ってある。そこだけは時間が止まっているようだ。ぼくは部屋へ帰り、寝た。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする