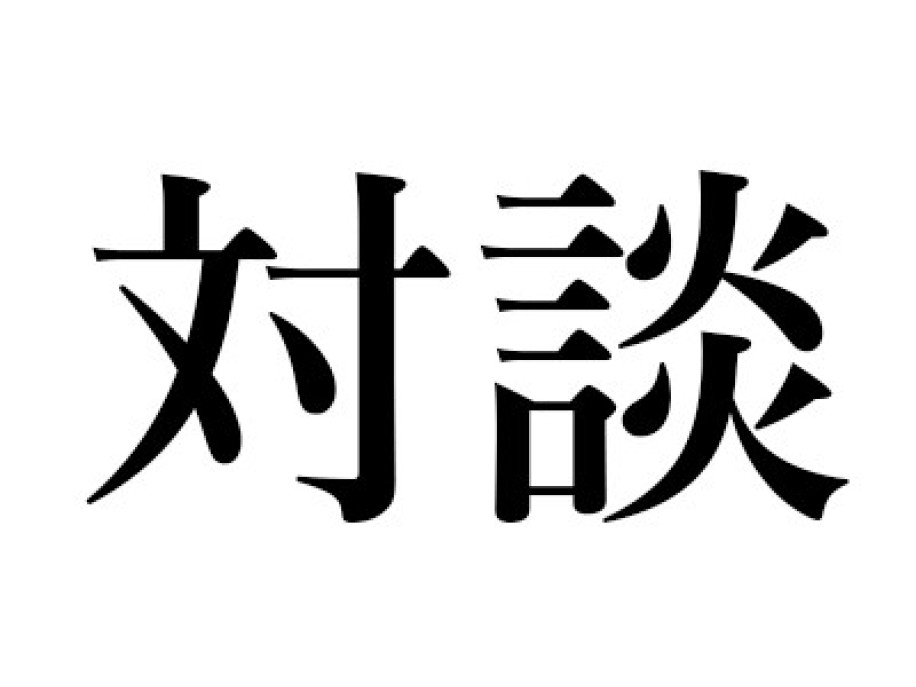書評
『ロンリー・ハーツ・キラー』(中央公論新社)
今、日本に江國香織的なモノローグ小説が蔓延している。江國的小説世界には、多くの場合、易しい言葉の連なりで、いかにも意味深な何か(本当はそんなものどこにもないかもしれないのに)を伝えんとする〈私〉がいる。そこに会話はあっても“対話”はない。わたしは鼻につくくらい巧(うま)い作家・江國香織を非難しているのではない。そのエピゴーネンたちに辟易しているだけなのだ。若いうちから、巧さを志向してどーする。対話を回避してどーする。もっと、のたうち回れよ、そんな苛立ちを覚えずにはいられないのだ。
星野智幸の最新小説は全然巧くない。嫌みでも逆説でもなく、でも、それがいい。だから刺激的なのである。物語の舞台となるのは、中国大陸から風にのって運ばれる黄砂吹きすさぶ、現実とは異なるパラレルワールドとしての日本だ。カリスマ的な人気を集めていた〈若オカミ〉の死によって〈カミ隠し〉と呼ばれる無気力な状態に陥る人々が急増。やがて、ネットに拡散したあるメッセージによって、心中という形で死を選ぶ者が続出する。天皇制、ひきこもり、ネット心中、無差別殺人といった現実世界でも通用するネタをちりばめながら、星野氏は、生きているのではなく社会の余力によって生かされているだけの我々のリアルに肉薄しようと七転八倒している。〈子どもが子どもを再生産するだけの、子どもの島〉である日本の、今ここにある危機を告発せんと、登場人物らに対話を繰り返させる、愚直なまでに。ここには、言葉が、思考が、溢れ返っている!
洗練や巧さとは真逆にあるスタイルで、星野氏はたくさんのメッセージを読者に手渡そうとしている。しかし、メッセージの送受の怖さと限界もまた、この作品のメインテーマのひとつなのである。つまり、これは作者自身の“表現すること”との格闘の軌跡を示した小説でもあるのだ。なんと面倒なことを自らに課していることか。しかし、そこからしか新しい小説は生まれ得ないことを星野氏は知っている。そして、それは実に正しい認識というべきなのだ。
星野智幸の最新小説は全然巧くない。嫌みでも逆説でもなく、でも、それがいい。だから刺激的なのである。物語の舞台となるのは、中国大陸から風にのって運ばれる黄砂吹きすさぶ、現実とは異なるパラレルワールドとしての日本だ。カリスマ的な人気を集めていた〈若オカミ〉の死によって〈カミ隠し〉と呼ばれる無気力な状態に陥る人々が急増。やがて、ネットに拡散したあるメッセージによって、心中という形で死を選ぶ者が続出する。天皇制、ひきこもり、ネット心中、無差別殺人といった現実世界でも通用するネタをちりばめながら、星野氏は、生きているのではなく社会の余力によって生かされているだけの我々のリアルに肉薄しようと七転八倒している。〈子どもが子どもを再生産するだけの、子どもの島〉である日本の、今ここにある危機を告発せんと、登場人物らに対話を繰り返させる、愚直なまでに。ここには、言葉が、思考が、溢れ返っている!
洗練や巧さとは真逆にあるスタイルで、星野氏はたくさんのメッセージを読者に手渡そうとしている。しかし、メッセージの送受の怖さと限界もまた、この作品のメインテーマのひとつなのである。つまり、これは作者自身の“表現すること”との格闘の軌跡を示した小説でもあるのだ。なんと面倒なことを自らに課していることか。しかし、そこからしか新しい小説は生まれ得ないことを星野氏は知っている。そして、それは実に正しい認識というべきなのだ。
ALL REVIEWSをフォローする