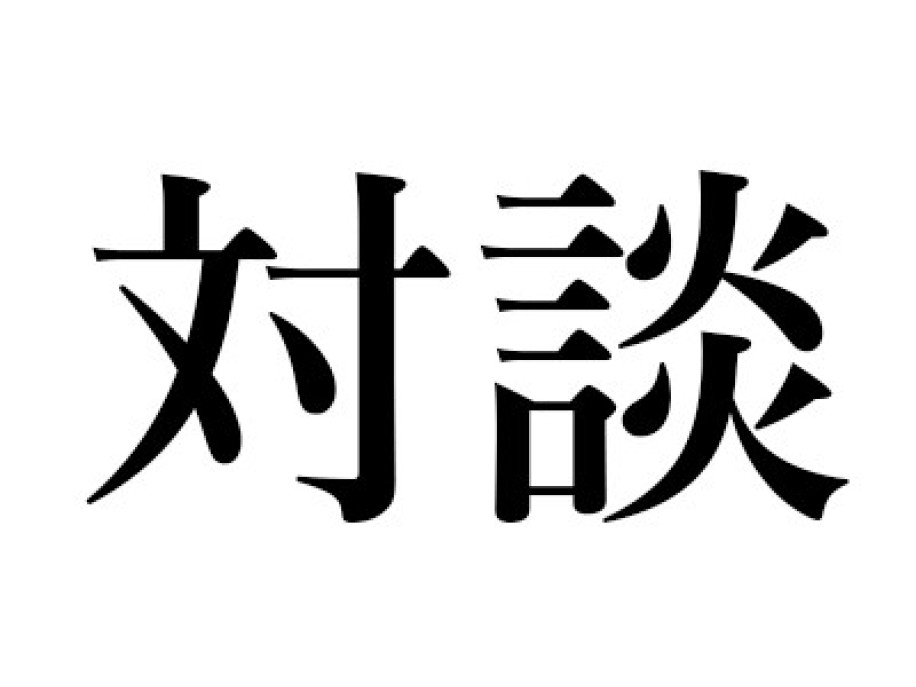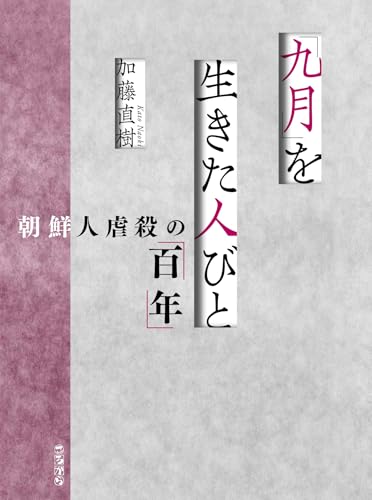書評
『だまされ屋さん』(中央公論新社)
家族の解体と再定義の物語
とある家族の物語である。夫と死別した七十歳の夏川秋代と、絶縁状態の三人の子どもたち。長男の優志(やさし)は在日コリアンの梨花と事実婚をしているが、二人して「正しさ」の呪縛にがんじがらめになり、夫婦の危機を迎えている。次男の春好はゲームにのめり込んで借金を抱え、性格の弱さゆえに妻の月美との仲は最悪。一人娘の巴(ともえ)は、アメリカでシングルマザーとなり、プエルトリコ人との間に生まれた娘を連れて帰国したが、日本での子育ての壁にぶち当たる。
その大元に、母・秋代の存在がある。優志には育児放棄、春好には溺愛、巴には優志に丸投げからの一転過干渉をやらかしている秋代は、「子育てを間違えた」と自分を絶えず責めているものの、何を間違えたかの認識が大幅に間違っている。
小説は、この家族の再生の物語――とは少し違う。そういうステレオタイプには回収されていかない、読んだことのない家族小説に向き合わされる。
物語は、巴の奇妙な友人である夕海(ゆうみ)の画策もあり、巴、梨花、月美という義理姉妹が集まって、それぞれが胸に抱えていたつらさを吐露することで動き出す。この女たちの行動は、やがて男たちを、そして母をも、語りの場に引き出すことになる。
長男の優志、という人物は、小説中もっとも複雑なキャラクターだが、「男らしさ」を強要する文化の中で徹底的に痛めつけられ、否定され、それこそ猿ぐつわを嚙まされて声を封じられてきた優志が語りだす場面は圧巻だし、優志のような人物が小説中に描かれたことも画期的なのではないだろうか。
小説が肯定するのは、「自分の声を発する」という行為だ。
最初のうちはみんな、声を出すのがうまくない。やむにやまれず発される声はしばしば悲鳴に近く、聞く者を萎えさせ傷つけもする。それでもだんだん、なんとか言葉を出せるようになり、自分の声を獲得したことに安らぎと自信を覚える。
それができるようになるのは、聞き手がいるからだ。聞き手は辛抱強くなければならない。遮って話し出したり、耳を塞いだりしては元も子もない。登場人物からはしばしば、「私の声を奪うな」というメッセージが発せられる。だけど、人間、身内だと思うと我慢がきかなくなる。近距離で聞く声はうとましい。そこで登場するのが「他人」だ。巴の家に現れる夕海、秋代の家に現れて「家族になっちゃいましょうよ」と妙なことを言いだす未彩人(みさと)は、身内ではなく距離があるゆえに、よい聞き手になれる。秋代が未彩人に依存していく姿は、どこか危なっかしいけれど、人は誰も聞き手を必要としているという真実を突く。
家族の再生の物語、ではない。むしろ解体の物語だ。家族の構成者は、ひとり一人他人なのだという現実を直視した上で、「血縁者は他人ではない」という幻想を解体し、家族という概念を再定義する物語なのだ。家族の崩壊をテーマにした小説はさんざん書かれてきたが、その先を描いたものはあっただろうか。
ラストまで読んで、「家族」の定義の変化を実感すると、前半に登場する未彩人のこんな言葉が、脳裏に蘇る。
「相手を遠ざけちゃう迷惑は、たんに人間関係の終わりですよ。家族の終わりとか。寂しいじゃないですか」。
ALL REVIEWSをフォローする