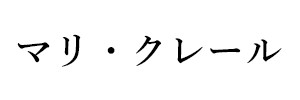書評
『見えるものと見えないもの――付・研究ノート 【新装版】』(みすず書房)
この本はメルロ=ポンティの最後の著作のひとつになるはずの草稿をまとめたものだ。『知覚の現象学』からはじまったかれの知覚論が、とうとうここまでやってきた。ずいぶん遠くまで歩んだものだ、というのが、この本を読んで、まっさきに浮んだ感慨だった。もっと初期のころからいえば、「知覚の本性」という論文までさかのぼってもいい。
その歩みの奥行をひとおもいにつかむには『知覚の現象学』の「奥行」のつかまえ方と、この本の「奥行」のつかまえ方とを比べてみるのがいいとおもう。ここにテーブルがある。あそこにピアノや壁がある。眼のまえを車が走りさってゆく。このテーブル、ピアノや壁、車が遠ざかり、それらの空間的な位置づけや位置の移動を、どうやって奥行としてつかまえればいいのか。『知覚の現象学』では、「私」がこれらのもの(テーブル、ピアノ、壁、車の移動)をみるために両眼を集中する度合いや、これらのものの見かけ上の大きさとか、その変化のなかに、すでに奥行をつくりあげる見方が含まれていることになる。そしてこれらのものの変化がつながって、奥行へと組織化されるとかんがえる。ここでは原因があるから結果がついてくるという解釈の二元的な印象をさけようとするモチーフが前面にあるから、わずかに現象学にとどまっている。この本では、そうでない。「奥行」は見えるものの背中であり、裏面であり、かくされたものであり、それ自体が意味なのだとはっきり指定されていて、あいまいさはどこにもない。眼のまえをいま走っている車は、別の瞬間にはやや斜めの位置に、すこし小さい見かけで移動している。また別のある瞬間には、もっと遠ざかった位置に、さらに小さな車体の見かけで移動している。「私」はこの車の走行する軌跡を組織化して「奥行」の概念を手にする。この「奥行」は見えないものであるが、車の走行という意味に核を与え、その核が「奥行」ということになる。
こういってみるとおなじメルロ=ポンティをうけとっているようにみえる。だがほんとうは、自在になった現象学をおなじメルロ=ポンティとしてうけとっているのだ。何が自在になった要素かを、すこし確かめてみよう。
いちばん最初に言わなくてはならないことは、すでにこの本では(とうとうこの本ではといってもおなじだ)メルロ=ポンティにとって、哲学は知覚のことであり、(既に)見えるものときりはなすことができないことが、徹底的にはっきりさせられている。これは著者の言い方では「コンコルド橋」のことを考えることは、意識の秩序化である考えのなかに「コンコルド橋」をたずさえていることではなくて、「コンコルド橋」のところにいることを意味している。これは徹底的な考え方で、考えることが見ることときりはなすことができないという宣明であるばかりではない。考えることは物ときりはなせず、物の方へゆき、物と混じりあうひとつの仕方のことだという宣明を意味している。もっといえば、考えることは世界ときりはなせないし、自然ときりはなすことができない。いいかえればメルロ=ポンティの哲学にとってこの世界は「私」と「見られるもの」との液状の混合物のことを意味している。
ここでメルロ=ポンティが、くどいほどくりかえし注意していることがある。「私」が「コンコルド橋」をかんがえることで体験したとおなじように、「このコップ、このテーブル」を見られるのは、「私」がそれらのもののうちにあるということで、「私」の表象や思考のうちに、それらのものがやってくるからではないということだ。「私」が物を見ているとき、その物は物の存在であって「私」の世界ではないし、「私」が感じているその物との距離の遠近でさえ、物の存在の一部で「私」自身の一部ではない。そこでもうひとつ注意すべきことが起こる。その「物」について他人の眼差しが加えられているとき、それは見る「私」にとってどんなことを意味しているかということだ。メルロ=ポンティによれば、この場合の他人の眼差しは「物」にたいして「私」とおなじつかみ方をもっていると解すべきではなく「私」にとっては他人は盲目のうちに手でその「物」に触れているのとおなじ意味しかもっていない。いいかえれば「私」が私の身体の外観を見ながらやれる理解とおなじ程度のことをしている人物と等価だとかんがえればいいことになる。このふたつの注意すべき事柄は、メルロ=ポンティがこの本で到達した哲学にとって、とても大切な柱になっているとおもえる。
そしてわたしの好みからもうひとつ柱をつけ加えるとすれば、この本でメルロ=ポンティが高いところからの視覚、上方からの視覚に特別の位置を与えていることだ。高いところ、遠い上方はメルロ=ポンティによれば、いつも独我論的であり、ここでは他人の眼差しを考慮にいれることはない。まして他人の眼差しが「私」にとって盲目の触診みたいな位置にあるとかんがえることもいらない。他人の眼差しは充分に近くでそれを見ているときに、はじめて眼差しとしての意味をもつものだからだ。高いところから、遠い上方から(たとえば星のように)見ることによって、見えるものはそれ自身と同一な「純粋事物」として存在しているとメルロ=ポンティはこの本でいっている。何かそこだけは世界や物はメルロ=ポンティにとって純粋物理的な空間のようにおもえて、かれの哲学にとって奇異な感じをいだかせる。でもこの高いところから、遠い上方からの視覚は、いってみれば哲学にとって上方、下方の概念をうしなう未知の領域に属している。そこからこの奇異さはやってくるようにみえる。
メルロ=ポンティがこの本で到達したところでは、世界は原理的にも、本質的にも視覚的なものであり、サルトルのように無から熟慮のなかにやってくる純粋本質でもなければ、物に溶けこむことによって得られる存在地平でもない。見るもの(「私」)があり、触知する他人の眼差しがあり、物がそれらの結節点としてあるような厚みが世界なのだといわれている。物は見られるものとしてあるが、物は可能性や潜在性としての肉体をもっている。わたしたちは物を見ることによって物の方へ出かけてゆく。だがそのときでもわたしたちのなかには、外から見ると内部の闇のなかにとどまっているものがあり、ここでは交叉が起っている。この交叉は、物を見るものと、見られる物とのあいだに「存在」の地平と「存在」からこぼれおちた「物」たちの境界としての渚をつくっている。メルロ=ポンティによれば、どうしてもこのときに見えないものとしての裏面や、背中や、胎内がなくてはならず、それはこの世界や物の〈意味〉をつくっていることになる。
わたしたちは見える物と見えない裏面とを統合しているとき、はじめて世界や〈存在〉を体験していることになる。
メルロ=ポンティがこの本で到達している理念は、強いてとりだせばふたつあるとおもう。それはかれの哲学のとても重要なところで、わたしたち読むものの琴線にふれてくる。メルロ=ポンティも苦労したように、わたしたちもおなじ年月、理念の労苦をつんできたことを想い出させてくれるからだ。
もうひとつメルロ=ポンティは重要な理念をメモのなかで書き記している。
このふたつは、この本でメルロ=ポンティがやっている考察と、草稿やメモのなかから拾いだすことができる理念だとおもえる。
(1)の指すところはとても明瞭で、また予言的ともいえるものだ。わたしたちが現在たたかっているものがあるとすれば、真理をふたつに分割して所有しようとするもの、それに身をすり寄せているものにたいしてだからだ。
(2)においてメルロ=ポンティが指しているものは何だろうか。〈自然〉が物質であり、物質が必然であるという記述が、記述された世界から物質を物神化してしまうことにつながってゆく過程を、わたしたちはあまりにたくさん見てきた。〈自然〉は物質でもなければ、物質についての観念でもない。そのまま即自的に「肉」としての人間の存在の裏面、背中、奥行のなかにという地平で、はっきりと確定的に〈自然〉がつかまえられることが大切なのだ。わたしたちは、ひどく幼稚な自然主義に当面している。人間はこの自然主義のなかでは、ただの人形のように、見ることをしないし、見えないものの存在の領域を奪われることで、造ることも息をつくこともできない場面にたたされている。わたしたちはこの本のメルロ=ポンティから、とても正確な磁針が『知覚の現象学』をここまで歩ませてきた有さまを感じとっている。
【この書評が収録されている書籍】
その歩みの奥行をひとおもいにつかむには『知覚の現象学』の「奥行」のつかまえ方と、この本の「奥行」のつかまえ方とを比べてみるのがいいとおもう。ここにテーブルがある。あそこにピアノや壁がある。眼のまえを車が走りさってゆく。このテーブル、ピアノや壁、車が遠ざかり、それらの空間的な位置づけや位置の移動を、どうやって奥行としてつかまえればいいのか。『知覚の現象学』では、「私」がこれらのもの(テーブル、ピアノ、壁、車の移動)をみるために両眼を集中する度合いや、これらのものの見かけ上の大きさとか、その変化のなかに、すでに奥行をつくりあげる見方が含まれていることになる。そしてこれらのものの変化がつながって、奥行へと組織化されるとかんがえる。ここでは原因があるから結果がついてくるという解釈の二元的な印象をさけようとするモチーフが前面にあるから、わずかに現象学にとどまっている。この本では、そうでない。「奥行」は見えるものの背中であり、裏面であり、かくされたものであり、それ自体が意味なのだとはっきり指定されていて、あいまいさはどこにもない。眼のまえをいま走っている車は、別の瞬間にはやや斜めの位置に、すこし小さい見かけで移動している。また別のある瞬間には、もっと遠ざかった位置に、さらに小さな車体の見かけで移動している。「私」はこの車の走行する軌跡を組織化して「奥行」の概念を手にする。この「奥行」は見えないものであるが、車の走行という意味に核を与え、その核が「奥行」ということになる。
こういってみるとおなじメルロ=ポンティをうけとっているようにみえる。だがほんとうは、自在になった現象学をおなじメルロ=ポンティとしてうけとっているのだ。何が自在になった要素かを、すこし確かめてみよう。
いちばん最初に言わなくてはならないことは、すでにこの本では(とうとうこの本ではといってもおなじだ)メルロ=ポンティにとって、哲学は知覚のことであり、(既に)見えるものときりはなすことができないことが、徹底的にはっきりさせられている。これは著者の言い方では「コンコルド橋」のことを考えることは、意識の秩序化である考えのなかに「コンコルド橋」をたずさえていることではなくて、「コンコルド橋」のところにいることを意味している。これは徹底的な考え方で、考えることが見ることときりはなすことができないという宣明であるばかりではない。考えることは物ときりはなせず、物の方へゆき、物と混じりあうひとつの仕方のことだという宣明を意味している。もっといえば、考えることは世界ときりはなせないし、自然ときりはなすことができない。いいかえればメルロ=ポンティの哲学にとってこの世界は「私」と「見られるもの」との液状の混合物のことを意味している。
ここでメルロ=ポンティが、くどいほどくりかえし注意していることがある。「私」が「コンコルド橋」をかんがえることで体験したとおなじように、「このコップ、このテーブル」を見られるのは、「私」がそれらのもののうちにあるということで、「私」の表象や思考のうちに、それらのものがやってくるからではないということだ。「私」が物を見ているとき、その物は物の存在であって「私」の世界ではないし、「私」が感じているその物との距離の遠近でさえ、物の存在の一部で「私」自身の一部ではない。そこでもうひとつ注意すべきことが起こる。その「物」について他人の眼差しが加えられているとき、それは見る「私」にとってどんなことを意味しているかということだ。メルロ=ポンティによれば、この場合の他人の眼差しは「物」にたいして「私」とおなじつかみ方をもっていると解すべきではなく「私」にとっては他人は盲目のうちに手でその「物」に触れているのとおなじ意味しかもっていない。いいかえれば「私」が私の身体の外観を見ながらやれる理解とおなじ程度のことをしている人物と等価だとかんがえればいいことになる。このふたつの注意すべき事柄は、メルロ=ポンティがこの本で到達した哲学にとって、とても大切な柱になっているとおもえる。
そしてわたしの好みからもうひとつ柱をつけ加えるとすれば、この本でメルロ=ポンティが高いところからの視覚、上方からの視覚に特別の位置を与えていることだ。高いところ、遠い上方はメルロ=ポンティによれば、いつも独我論的であり、ここでは他人の眼差しを考慮にいれることはない。まして他人の眼差しが「私」にとって盲目の触診みたいな位置にあるとかんがえることもいらない。他人の眼差しは充分に近くでそれを見ているときに、はじめて眼差しとしての意味をもつものだからだ。高いところから、遠い上方から(たとえば星のように)見ることによって、見えるものはそれ自身と同一な「純粋事物」として存在しているとメルロ=ポンティはこの本でいっている。何かそこだけは世界や物はメルロ=ポンティにとって純粋物理的な空間のようにおもえて、かれの哲学にとって奇異な感じをいだかせる。でもこの高いところから、遠い上方からの視覚は、いってみれば哲学にとって上方、下方の概念をうしなう未知の領域に属している。そこからこの奇異さはやってくるようにみえる。
メルロ=ポンティがこの本で到達したところでは、世界は原理的にも、本質的にも視覚的なものであり、サルトルのように無から熟慮のなかにやってくる純粋本質でもなければ、物に溶けこむことによって得られる存在地平でもない。見るもの(「私」)があり、触知する他人の眼差しがあり、物がそれらの結節点としてあるような厚みが世界なのだといわれている。物は見られるものとしてあるが、物は可能性や潜在性としての肉体をもっている。わたしたちは物を見ることによって物の方へ出かけてゆく。だがそのときでもわたしたちのなかには、外から見ると内部の闇のなかにとどまっているものがあり、ここでは交叉が起っている。この交叉は、物を見るものと、見られる物とのあいだに「存在」の地平と「存在」からこぼれおちた「物」たちの境界としての渚をつくっている。メルロ=ポンティによれば、どうしてもこのときに見えないものとしての裏面や、背中や、胎内がなくてはならず、それはこの世界や物の〈意味〉をつくっていることになる。
わたしたちは見える物と見えない裏面とを統合しているとき、はじめて世界や〈存在〉を体験していることになる。
メルロ=ポンティがこの本で到達している理念は、強いてとりだせばふたつあるとおもう。それはかれの哲学のとても重要なところで、わたしたち読むものの琴線にふれてくる。メルロ=ポンティも苦労したように、わたしたちもおなじ年月、理念の労苦をつんできたことを想い出させてくれるからだ。
(1) 「私」が「それ」と手を切っても「それ」の外で「そ・れ」であることもできるし、「それ」に再融合しても「それ」でないこともできる。裏面、奥行、背中、そして見えないものとしての世界や物の〈意味〉は、この両義性の方へ行くことによって、真理の彼岸にある〈真理〉に到達することができる。
もうひとつメルロ=ポンティは重要な理念をメモのなかで書き記している。
(2) 〈自然〉は人間の裏面である(肉である)が、けっして〈物質〉ではないという位相から〈自然〉を記述しなくてはならないこと。また、〈ロゴス〉(言葉の普遍性のこと)は、人間のうちで実質化されるものにちがいないが、けっして人間の所有物ではないことをはっきりさせること。
このふたつは、この本でメルロ=ポンティがやっている考察と、草稿やメモのなかから拾いだすことができる理念だとおもえる。
(1)の指すところはとても明瞭で、また予言的ともいえるものだ。わたしたちが現在たたかっているものがあるとすれば、真理をふたつに分割して所有しようとするもの、それに身をすり寄せているものにたいしてだからだ。
(2)においてメルロ=ポンティが指しているものは何だろうか。〈自然〉が物質であり、物質が必然であるという記述が、記述された世界から物質を物神化してしまうことにつながってゆく過程を、わたしたちはあまりにたくさん見てきた。〈自然〉は物質でもなければ、物質についての観念でもない。そのまま即自的に「肉」としての人間の存在の裏面、背中、奥行のなかにという地平で、はっきりと確定的に〈自然〉がつかまえられることが大切なのだ。わたしたちは、ひどく幼稚な自然主義に当面している。人間はこの自然主義のなかでは、ただの人形のように、見ることをしないし、見えないものの存在の領域を奪われることで、造ることも息をつくこともできない場面にたたされている。わたしたちはこの本のメルロ=ポンティから、とても正確な磁針が『知覚の現象学』をここまで歩ませてきた有さまを感じとっている。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする