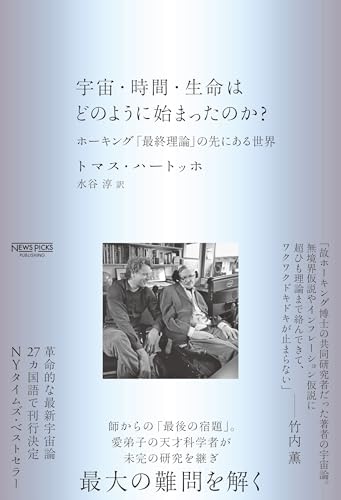書評
『進化の意外な順序ー感情、意識、創造性と文化の起源』(白揚社)
身体なくして心始まらず
著者は、感情や意識など、人間とは何かを知るうえで重要なテーマを考え続けている神経科学者、神経科医である。人間に注目すると、言葉、社会性、知識、理性などに眼が向くが、著者は、それらを動機づけ、結果をチェックし、必要な調整を行っているのは感情であることに気づいた。そこで、「これまでその働きに見合うだけの注目を浴びて来なかった」感情を基本に人間について考えていくのである。それが示された部分を少し長いが引用する。<人間が持つ感情の本性と影響に関するストーリーを語ろうとしたとき、私は、心や文化に対する私たちの考えが、生物学的な現実に即していないことに気づいた。私たちは、生物が見せる、社会環境における知的な振る舞いが、神経系に支援された先見の明、熟慮、複雑性に由来すると想定している。しかしその種の振る舞いが、生物圏(バイオスフィア)の夜明けの時代に存在していたバクテリアのような単細胞生物が備えていた簡素な装置にその起源を持つ可能性があることは、今や明らかである>。原初の生命体からの連続性の中で、心や文化を語るという新しい視点を出すという思いから、表題に「意外」がつけられている。しかし、評者の立場(生命誌)はこれを意外でないと見てきたので、神経科学からのこのアプローチに大いに関心を抱いた次第である。著者は「ホメオスタシス」に注目する。これは通常「恒常性」と訳され、「平衡」「バランス」に注目するが、著者は「単に生存のみならず繁栄を享受し、生命組織としての、また生物種としての未来へ向けて自己を発展させられるよう生命作用が調節される」ところが重要であるとする。ここでの繁栄とは、「生存に資するより効率的な手段の確保と繁殖の可能性の両方を意味する」。つまり、生命体の調節は非常に動的であり、近年出された「ホメオダイナミクス」という言葉の方が実態を示しているとするのである。ここは大事なところだ。
そこで著者は、進化の過程で私たち人間だけに備わった特別な脳のはたらきとして心を見るという従来のやり方を捨てる。ホメオスタシスに支えられた単細胞生物に始まる生命現象全体を通して心を見ていくのである。細菌は環境の状態を感知し、生存に有利な方法で反応する。そこには相互のコミュニケーション(分子による)もある。ここにはすでに知覚、記憶、コミュニケーション、社会的ガバナンスの原点が見られると言ってよい。その後真核生物、それの集まった多細胞生物へと進み、循環系、内分泌系、免疫系ができる中で、神経系が生れる。イメージが生成され、心が構築されるのは神経系あってのことだが、重要なのは神経系が単細胞に始まる流れの中で誕生し、はたらきとしても古いところからつながっていることである。消化管に複雑な神経系が存在することから、腸は第二の脳であると言われるが、最初に生れた神経系に似ているこちらこそ第一の脳と呼ぶにふさわしいと考えることもできる。このように関心は常に身体に向いていく。
そこで身体の進化につれて生れる感情から心を考えていくのである。もちろん、イメージの形成は中枢神経系あってこそであり、そこには外界と生体内の世界とのイメージがある。通常は外界を知る感覚器官からの刺激に注目しがちだが、著者は内界のイメージを重視する。古い内界(内臓・平滑筋・皮膚)で起きている生命現象がホメオスタシスから評価され、健全なら「快」、不健全な時に「疲労」「不快」などが生れ、それが感情の核となる。もう一つのより新しい内界は、骨格や随意筋が関わって生体内の状態を評価し、言葉にする役割をもつ。内界と外界とをつなぐと言ってもよい。こうして古い内界から生れた感情を中核として心が生れるというわけである。「身体がなければ心は決して始まらない」のである。
心の基本単位はイメージであり、脳がこれを抽象化し、たゆまず言葉に翻訳していくことが心を豊かにするプロセスである。ここから語りが生れ、理性的推論と想像、更には創造性が生れる。こうして神経系が古くから存在する身体と連携することで、感情から主観性、意識、文化などが生れるという一つの科学的物語りが語られる。この流れを示した部分をまとめると「感情はホメオスタシスの心的表現であり、そこにある身体と神経系の協調関係が意識の出現をもたらし、ここで生れた感じる心が人間性の現われである文化や文明をもたらした」となる。
芸術・哲学・宗教・医療などのあらゆる文化・文明をいかに動的であるとはいえホメオスタシスという生物的現象に帰して考えていく中では、当然疑問も生じる。ただその度に問題点をあげての解説があり、それに説得されながら読み進めることになった。
人工知能が実用化に向けて動き、脳をコンピューターと並べて人間を語ることが多くなった今だからこそ、進化によって生れた生きものとしての人間に注目して人類のこれからを考えていく視点は重要であり、魅力的である。
ALL REVIEWSをフォローする









![中村桂子「2023年 この3冊」毎日新聞|<1>西田洋平『人間非機械論 サイバネティクスが開く未来』(講談社選書メチエ)、<2>中沢新一『カイエ・ソバージュ[完全版]』(講談社選書メチエ)、<3>ロビン・ダンバー『宗教の起源 私たちにはなぜ<神>が必要だったのか(白揚社)](/api/image/crop/916x687/images/upload/2025/03/e172f187e73582fd5102cba2655da740.jpg)