書評
『文学なんかこわくない』(朝日新聞社)
柔らかくて過激な自己検証
文学を通して「それをとり囲む世界」を見ようとする試み。そう銘打たれてはいるものの、『文学なんかこわくない』は、じつのところ「タカハシさん」と片仮名で表記される虚構の語り手に託した、柔らかく過激な自己検証となっている。一九九五年夏から九八年夏にかけて書き継がれただけあって、ここではバブル以降の日本を揺るがした新興宗教団体によるテロ行為や、あの神戸の殺人事件がしっかり見据えられているのだが、そうした社会的な事件に対するタカハシさんの関心は、あくまで書かれたものに、書くための道具に向けられている。つまり思考のすべてを統御する日本語とはなにか、という問いに貫かれているのだ。
だからこそ彼は、惨劇を招いた教団の限界を、教祖たちが発する「どれも意味が一つずつしか」存在していない言葉の貧しさに見出し、アダルトビデオに出現した素人を演じる女優というおきて破りの衝撃の深さを、書き手と言葉の「一対一対応」が崩壊する分裂症の事例に関連づけ、自由主義史観が抱えている矛盾の出所を、日本語を扱う人間こそが日本人だとする視点の欠如に探り、度し難い紋切り型に満ちあふれた大ベストセラー小説のからくりを、「文学」を殺すことで読者を獲得する平板さに求めずにいられない。そして、戦後日本の言語が、ひたすら国の内側に収束する言語であったことに触れた書物の意義を説きつつ、そうした閉塞をやはり内側から乗り越えられるのは、「文学」しかないと言い切るのだ。
これらの発言を支えているのは、地の文をしのぐほどの長大な引用である。究極の小説論は、本篇全体を含む「もうひとつの小説」を書いてしまうことだとするタカハシさんの生みの親が、「この連載は、ぼくにとって小説を書くことと同じであった」と後書きで語っているのは当然だろう。本書は、そんな小説的実践のための、記念すべき第一歩なのだ。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
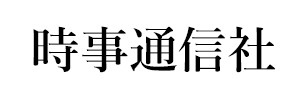
時事通信社 1998年11月
ALL REVIEWSをフォローする








































