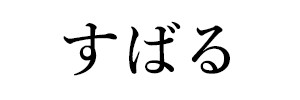書評
『めす豚ものがたり』(河出書房新社)
潑剌とした邪気
高級香水店で売春婦まがいの仕事を仰せつかっている若い女性の身体に、少しずつ異常が生じはじめる。乳房が張り、思いがけない場所に肉がつき、肌がつやつやとピンクに輝き、さらには生理の間があいて性的興奮の時期と醒めた時期が交互に訪れ、食欲が増して道端に落ちている野菜くずや団栗まで頬張るようになる。臓腑のすみずみに襲いかかる微細な変容の過程がほとんど内視鏡的な目で観察されていくのだが、この内面の激しいゆらぎと相即した外見の変化が劇画ふうにたどられることで、ただグロテスクというだけでは終わらない滑稽さが醸し出されている。つまりここで扱われているのは、豚への転身ではなく、人間と豚との行き来なのだ。マリー・ダリュセックニ十七歳の第一作『めす豚ものがたり』は、一九九六年度のフランス読書界の話題をさらった、いわゆる「衝撃のデビュー作」で、発売と同時にこれほど世界的な注目を浴びたのはフランソワーズ・サガン以来と大いに騒がれた。しかしこの小説の手柄は、作者が高等師範学校出身の若き才媛であることでもなければ、家族や夫婦のしがらみの変奏ばかりが目立つ最近のフランス小説の風潮に母娘の確執をまぶしながら異を唱えてみせたことでもなく、熱く、ポップで、同時にもの悲しい虚構の世界を、純粋に言語で築きあげたところにあるだろう。言語だけで鮮烈な映像世界を創出し、映画作家を嫉妬させるほどの熱量を保持した独自の文体と、ジェンダーを超越した欲望の横溢(ゴダールがこの小説の映画化を計画し、断念している)。そこには、十年ほど前、おなじく高等師範学校出身の秀才でダリュセックの先輩にあたるアンヌ・ガレタが世に問うた『スフィンクス』(新潮社)を連想させるものがある。
けれどもガレタの世界が理性の超伝導的な冷ややかさにあるとするなら、ダリュセックのそれは陽性で潑剌とした邪気にある。日常からの逸脱を変身譚の遺産だけでもたせようとすれば失速したはずの後半が、香水店経営者にして狼男のイヴァンを登場させ、舞台を一挙に近未来へ移したことで救われているのだ。セーヌ河岸を破壊し、ノートル・ダム寺院を廃嘘に追いやった戦争兵器が、人体にも後戻りできないゆがみをもたらした可能性を暗示しつつ、そこに中世以来の文学的記憶を過激に盛り込んだダリュセックの目論見はたしかに成功している。満月の夜に人をあやめなければ生きていけない狼男を追手から護るため、外出をあきらめて宅配ピザを頼み、その配達人を胃の腑にいれるといった黒い笑いも効いている。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする