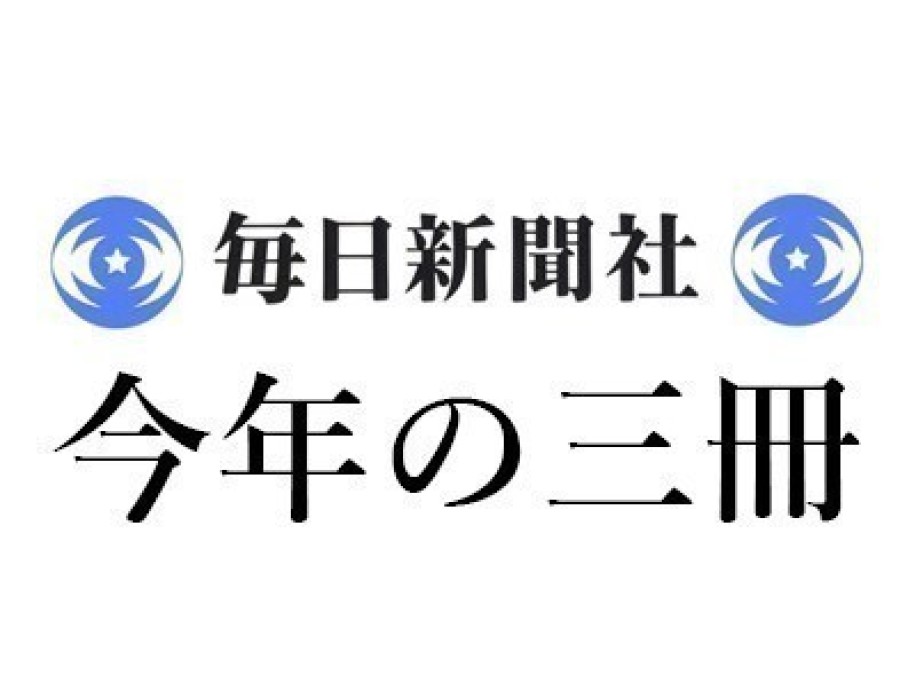書評
『郵便配達夫シュヴァルの理想宮』(河出書房新社)
奇怪な石の迷宮にきらめく無垢な魂
昭和のはじめ、深川に二笑亭と呼ばれる家があったことは聞いているだろう。家全体を迷路のように作り、壁の板のフシ穴にガラスをはめたり、土の代わりに黒砂糖を塗って壁にしたり、まことに不思議な家であった。なお、私が二笑亭の御子息にうかがったところでは、黒砂糖を塗ったというのは正確ではなくて、一度塗ったが蟻が寄ってきて困り、砂糖と蚊取り線香を混ぜてスリ鉢でスリ、それを塗ったのだという。二笑亭のほかにも、近年の例ではリポビタンDの空きビンを積み重ねた家とか、浜辺の漂着物を拾い集めて作った家とか、マアその筋の血脈は絶えない。日本でもそうだから、広い世界にはそういう奇妙な情熱に取りつかれたセルフビルダーは大物小物入り乱れてたくさんいるが、チャンピオンということになると、アメリカのワッツ・タワーズのロディア氏とフランスの理想宮のシュヴァル氏にとどめをさすだろう。そのシュヴァルについての本が日本ではじめて出た。式場隆三郎ほか著『定本二笑亭綺譚』(ちくま文庫)と並んで日仏の奇っ怪建築の本が整った。
慶賀すべきことかどうかは知らないが、子供の頃からいつかはやってみたいと思いながら教養と常識と配偶者に邪魔されてやれないでいる私としては、せめてシュヴァルの本『郵便配達夫シュヴァルの理想宮』(作品社)の紹介でもして一時の渇をいやしたい。
理想宮と名づけられた建物は、いってみれば小石で作られたグロテスクな宮殿で、これをたった一人でコツコツと作りあげたのはフランスの田舎の一郵便配達夫だった。時はおよそ百年前の一八七九(明治十二)年のある日のこと、不惑の年を過ぎた郵便配達夫シュヴァルは、配達中に石につまずいてころびそうになった。そしてそのつまずきの石を眺めて、彼は、年がいもなく惑ったというべきか、啓示を得たというべきか。
それから彼の石探しがはじまった。仕事が終わると、夜、彼は手押車を押し、時には五、六キロも歩いて、昼間目星をつけておいた石をとりにいった。やがて彼は、集めた石を使って、長いあいだ夢に描いてきた夢の宮殿を建てようと決心する。以来三十三年間、彼はその余暇のすべてを使い、誰にも手助けを頼まず、営営として建築に没頭する。
明治四十五年に出来上がった建物は奇怪千万だが、しかし、東南アジアの仏教遺跡とか、南方の民族的建築とか、どこかで見たことのあるイメージが組み合わされている。一方、身近なはずのキリスト教の建築イメージはほとんどない。
このことについて著者は、
「郵便物の中にあった世界中から送られてくる絵はがき、当時広く読まれていた『マガザン・ピトレスク』などの絵入り雑誌に載っていた中近東、アフリカ、アジア、オセアニア、中南米の珍しい挿絵が、彼の想像力を強く刺激していたのである」と説明しているが、ナルホドと思った。
こうした南方的で異国的でもちろん狂気さえ感ぜずにはおれないシュヴァルの理想宮は、当然のようにアカデミズム美学からはゲテモノとして無視され、一方、これまた当然のようにアンドレ・ブルトンやシュールレアリストといった前衛派からは賞讃されてきた。著者はもちろん後者の立場に立つ。そしてシュヴァルの仕事の中に、素朴派の画家アンリ・ルソーと同質の「無垢、断乎たる無垢」を見る。たしかに、生きた時期も、下級公務員という境遇も、南方幻想も、ヘタウマぶりもよく似ている。
こうしたシュヴァルの造形問題を考える時に注意しておいた方がいいのは、これが建築であるという点で、絵とちがって使う材料の影響は決定的に大きい。材料が手を動かし、イメージを導くという性格が建築にはある。
シュヴァルは拾ってきた石をセメントでくっつけて建物を作ったわけだが、ポイントは石ではなくセメントの方じゃないかと私はにらんでいる。文の構造が名詞ではなくてにをはで決まるように、つなぎが利く。
セメントを使ってみると分かるが、木や石とちがい自分の固有の形というものが先天的に欠けた材料で、何の真似でもできるし、どんな形にもなる。粘土と同じように誰でも扱えるが、固まると鉄のように強い。建築用材料としては唯一悪魔的な魅力を持っていて、素人がセルフビルドを計画するときまってセメントに行きつくし、そこでの造形はたいていゴテゴテとする。ゴテゴテとしたくなるような本性も持っているのである。
フランスは世界のコンクリート建築の先進国であったが、シュヴァルの理想宮が生まれたのもそのことと関係があるように思う。
写真も図面もたくさん入り、文章も分かりやすいので、不思議なものや役に立たないことに引かれる人には見逃せない一冊である。
これで日仏がそろったので、次は米のワッツ・タワーズをどなたかお願いします。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする