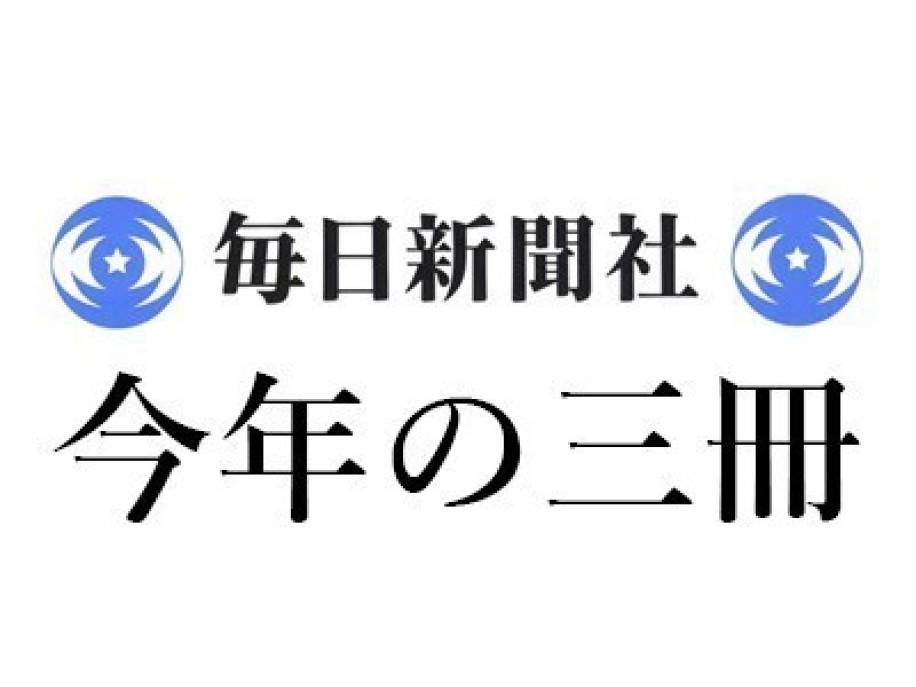書評
『人工現実感の世界』(工業調査会)
コンピューターで作る映像演出の怖さと驚き
東映の「昭和残俠伝」や「唐獅子仁義」を見た後、客はみんな健サンになったみたいに肩をそびやかせて映画館から出てくる、とよく言われた。もっと昔の映画草創期には、ナイアガラの滝を映すと観客は身をそらせて逃げようとした、という。映像というものがいかに人工的に現実感を作り出すのに長(た)けているかを語るエピソードだが、服部桂がこのたび出した本『人工現実感の世界』(工業調査会)は、そうした人工現実感の世界がコンピューターやロボット技術の進歩によって一大飛躍をとげつつあり、このままいけば、映画館の銀幕を突き破って、マスメディアや産業に決定的な変化を与えるだけでなく、現在のわれわれの「現実感」に深刻な転換を強いる、そんなとんでもないところに着地しそうである、ということを分かりやすく説明した本である。
一読して僕は、こんなところまで来てるのかという技術進歩への驚きとともに、やはり怖い。
これまでの映画館の現実感の水準は、視線を銀幕から少しずらせば、たちどころに消え、画面の拳銃を摑もうとすればすぐバレる程度のものだった。せいぜい立体的に見える映像に感心するくらい。
ところが、すでに実用実験の段階に達している新しい映像の中では、画面が客席に向かって飛び出すのではなく、見る人が画面の中に最初から入ってしまっているのだ。椅子に座り、頭からヘルメット状に縮小された“映画館”(頭部搭載型ディスプレー)をスッポリかぶり、手に機械仕掛けのグローブをはめ、そして目を開くと見知らぬ部屋の中に自分は座っている。やってみないと分からぬかもしれないが、本当に座ってしまっている。アレレと思って視線を振ると、見知らぬ部屋の後ろの方がちゃんと見える。素早く振ると素早く見える。コノヤローと思って目の前のテーブルの下をのぞくと脚や底板が見える。立ち上がり、歩いて行きたい方向を、たとえばドアの方を指でさすと、一歩一歩ドアが近づいてくる。手を伸ばしドアのノブを握ると、なんと握れる。隣の部屋に進みながら振り返りざま今いた部屋を見ると、自分の立ち去った椅子とテーブルが淋し気に部屋の中に残されている。そして、“映画館”を脱ぐとすべては消えて、目の前にはこの装置を開発した技術者がうれしそうに笑って立っている。
なんでこんな魔法じみたことが出来るかというと、部屋の作りのすべてがコンピューターに打ち込まれており、視線を振った角度とスピードを計算してそれに合った画像を人工的に作ってくれるからだ。ドアの方向を指すとそっちの方が近づくのも同じ原理。問題はノブで、なぜ架空を握っているのに本当と思うかは、手にはめたグローブのメカが作動して指に握った時と同じ反発力を加えるからである。
これまでの映像の延長上にある、と思って安心したいが、しかし、見る側の主体が映像の中に埋め込まれてしまっている、もう少し積極的にいうなら、見る側が映像の中に参入できる、という点はやはり決定的な差と認めるしかない。見るだけでも肩をそびやかして映画館を出る客たちは、参加してしまったらいったいどうなるんだろうか。
コンピューターによる人工現実感は今のところ映像分野で注目の的だが、本当に切実に求められているのは産業分野といっていい。
たとえば、原子炉の炉内とか深海とか宇宙といった生身の人間をさらすには危険な作業がどんどん増え、最終解決はロボットによるしかないのだが、人間と同じ判断力を期待するのは無理である。そこで考えられているのが、判断を人間がし、作業をロボットがする方法で、たとえば原子炉の中の作りをコンピューターに打ち込み、その“映画館”を熟練の作業者がかぶり、あたかも本当の中にいるように歩き回り、故障個所に行って修理するふりをすると、その動作が本当の炉内にいるロボットに伝えられ、修理が行われる。ロボット製作の最後の難所である脳の働きを人間がやることになれば、開発はぐんとやさしくなる。
この本は、視覚だけでなく五感で感じ、かつ自分もそこに参加しているように心底から感ずる人工的な演出の世界がそう遠くないところまで来ていることを教えてくれるのだが、そうした世界がやってきた時、人間の行動と表現の基盤である「現実感」というものはいったいどうなってくるんだろうか。
自分が身と心の両方で現実と思ったものが、ある時は現実であり、ある時は虚構である。こうした世界について石井威望氏が数学における実数と虚数(二乗するとマイナスになる数のこと)の例を挙げ、現代数学は両方で成立しているのと同じように、未来の社会は本当の現実と虚構の現実の両方で成り立つ可能性を指摘している。
しかし、まれに“映画館”をかぶっているうちはいいが、一日の半分かぶっていたら、あるいは子供のうちからずっとかぶっていたら……。
昔むかし中国の荘子が夢からさめた時考えたテーマを、普通の人が日常として生きる時代が近づいているのかもしれない。山本リンダも歌っているではないか。
〽アッアゥ、蝶~になる
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする