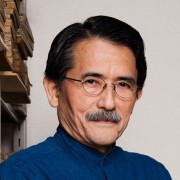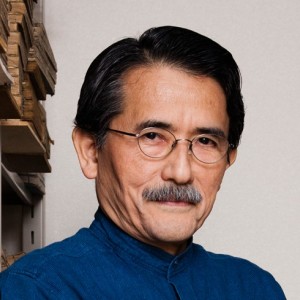書評
『耳嚢』(岩波書店)
消閑の読書に絶好
この聞きなれない書物は、江戸時代の中ごろ、旗本の根岸鎮衛(やすもり)という物好きな人があって、ともかく小耳に挟んだり目に触れたりしたそれこそ「よしなしごと」を、知るに従って帳面に書いていった、その集成である。しかし、その記事は天明年間から下って文化に至る前後三十年にも及ぶ長期間の書き留めなので、量的には頗る膨大なものである。
まあ言ってみれば古文で書かれているのであるが、平安時代の物語なんかとは全然ちがって、べつに辞書などを引くまでもなく、すらすらと読める平易な文体だから、敬遠するには及ばない。
所載の記事はみな長くても一、二ページで完結する程度の短いものでいかにも読みやすい。
どこから読んでもいいし、面白そうなところだけの拾い読みでもいっこうに構わない。
たとえば、「河童の事」という記事がある。なんでも天明元年の八月に仙台河岸伊達侯の蔵屋敷で河童を撃ち殺して塩漬けにしてあるという事を、松本秀持という友人が知らせてきた。子細を聞くと、なんでもその邸ではしばしば子供が濠に落ちて行方知れずになったりするので、調査したところ、河童を発見、鉄砲で撃って仕留めたといって、その塩漬けの絵まで持参したそうである。もとより眉唾な咄だけれど、実名で書いているところが尤もらしい。
また八代将軍吉宗公は、ある夏の夕、ふと思い立って網で蚊をたくさん捕え、それを原料に吸い膏薬を作らせたのだという。これが腫れ物の膿を吸うことずいぶんと奇妙の効能があった、というのだが、なんだかこれもいかにもアヤシイ。蚊が血を吸うからとてその蚊で吸い膏薬を作るなんてのは、狂言の世界に近い。しかし、それが吉宗の名君ぶりの一好話柄として語られているので余計可笑しい。
一々紹介する紙幅はない。ともかく閑暇の折りに、腹の膨れぬ読書をして優雅に暇を消したいという向きには絶好の一書である。
初出メディア
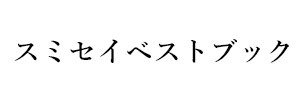
スミセイベストブック 2003年5月号
ALL REVIEWSをフォローする