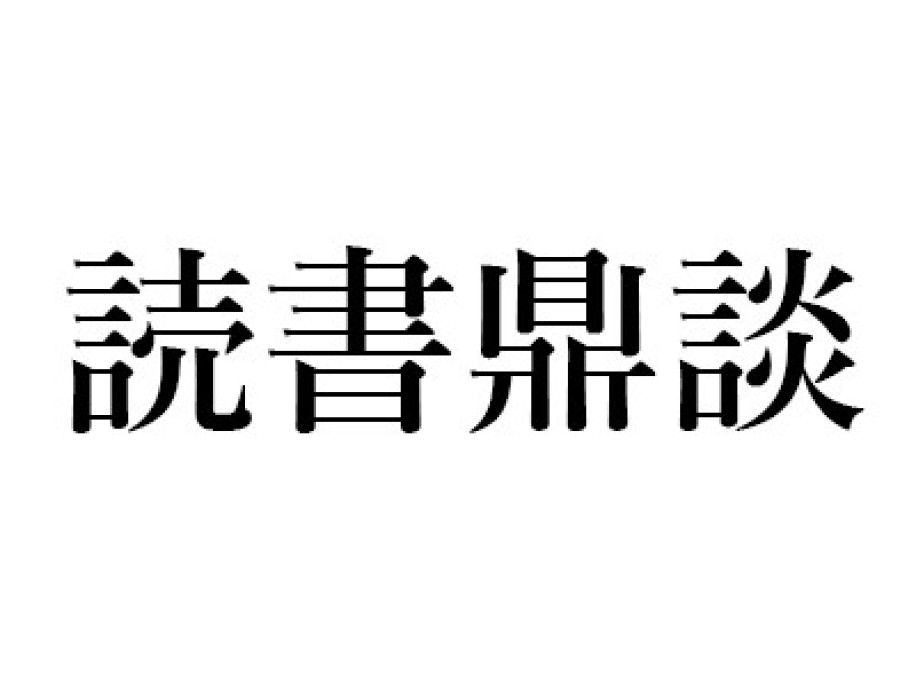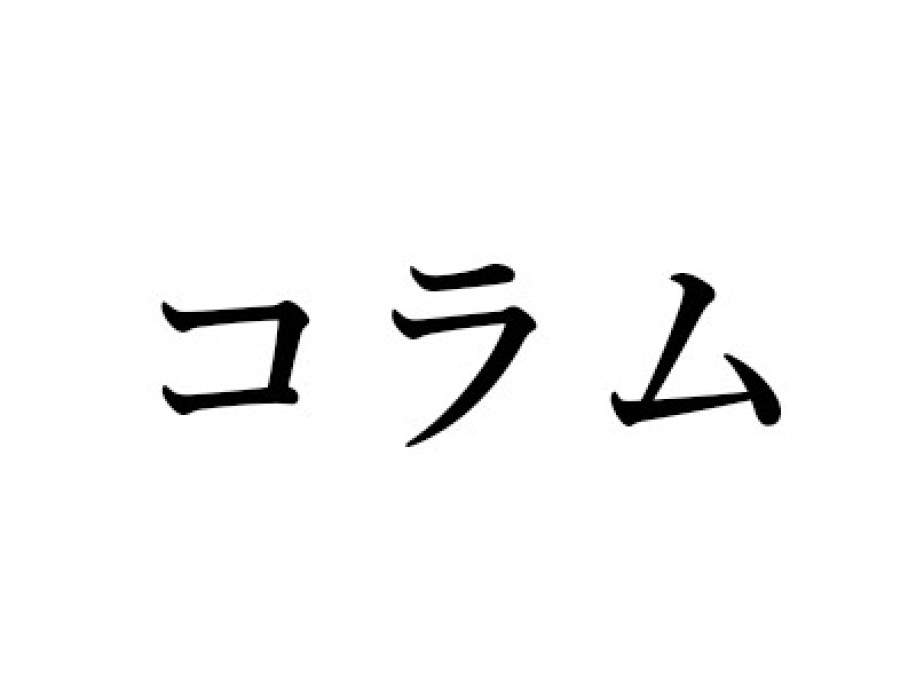書評
『愛はなぜ終わるのか―結婚・不倫・離婚の自然史』(草思社)
結婚や愛情に対する即物的な解釈
人間は四年で離婚する、と著者はいう。日本の結婚式のスピーチなんかでは三年目が危ないというし、映画では七年目の浮気ということになっているが、三年説も七年説も根拠が示されているわけではない。ところが著者の説には世界六十二カ国、百八十八の離婚例という統計的根拠があって(大胆な主張の割には例証数が少ないと思うが)、それによるとたしかに四年目がダントツに危ない。
ここまでは現代人の統計上の話だが、人類学者の著者の思考はすぐさまお得意の狩猟・採集民に向かい、四年目というのが原始的な人間社会にとって特別な年であることを明らかにする。オーストラリアのアボリジニーはじめ多くの狩猟・採集民の出産は四年間隔で行われる。正確に言うと幼児は四年で乳離れし、それを待って次の出産が行われる。
この事実を踏まえて導かれる結論は、
繁殖期間だけつがうキツネやロビンその他多くの種と同じように、ひとの一対一の絆も、もともと扶養を必要とする子供ひとりを育てる期間だけ、最初の四年だけ続くように進化したのである。
人間は生物学的には四年目に別れて当然というわけである。もし別れたくなければ四年ごとに子供を作るしかない、とまでは言わないけれども、この著者の結婚とか夫婦の愛情についての論議はいちじるしく即物的というか、そのあまりの単純明快さについつい引き込まれる。
たとえば一夫一妻制や夫婦の深い愛情の起源については、何もむずかしいことではなくて、人間の赤ん坊の頭がでかすぎたからだと説明する。他の動物にくらべ人間の脳が発達した結果、頭がつかえて母親の産道から出づらくなり、人類は胎児を発達の早い段階で出産し、脳の発達を産後にもちこすように進化した。その結果、乳幼児期がいちじるしく長くなり、他の動物なら一年以内で済むところ四年もの間、母は子の世話をし、父は母と子のための食料を集めなければならない。
この間、母と父の関係を安定させなければならないが、そのためにつなぎ剤として夫婦の愛情が発生し、その延長で一夫一妻制も成立した、と著者は言う。たしかに愛情でもなければ男はいつまでも母と子のための食料集めはせず、とっとと出てってしまうかもしれない。
このあたりの話まではあまりの即物的解釈が逆に面白味を生んでいるが、ペニスの発達の話になると、ちょっとどうも。
「ヒトのペニスは比較的太いが、太い陰茎は摩擦によって(女性の)興奮をもたらし」たので、太いヤツほどもてるようになり、子をたくさん残し、細いヤツを淘汰したというのである。
著者はこの説のもとはダーウィン先生にあると言ってるけれど、A!SOゼミの教授あたりが言いだしっぺじゃないか。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする