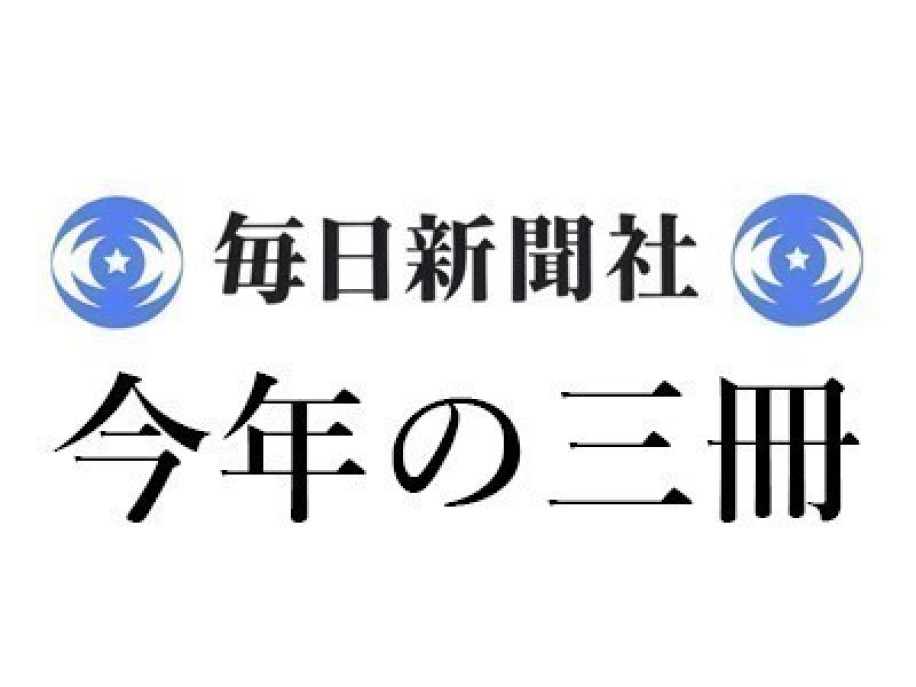書評
『ディングルの入江』(集英社)
「藤原新也」の小説
はじめ、タイトルを、藤原新也の「小説」とつけ、それから思いなおして、「藤原新也」の小説、に変えた。なんだか「週刊新潮」の見出しみたいだ。実はまだ迷っている。どちらのタイトルがいいのかわからない。どっちだって一緒じゃんといわれるかもしれないが、そうではないのである(ぼくにとっては)。
①藤原新也の「小説」、なら……あの伝説のカメラマン藤原新也がついに小説に手をつけた。だが、これは小説と呼ぶべきものなのだろうか……となる。
②「藤原新也」の小説、なら……ここに一冊の小説がある。紛れもなく小説である。書いたのは、その人自体が一つのジャンルでありうるような怪物にして混沌、藤原新也。では、そのことの意味は……となる。
さて、どっち?
ぼくは本屋の店頭で二冊の美しい本を見つけた。『ディングルの入江』(集英社)と『風のフリュート』(集英社)というタイトルで、前者が小説で後者が写真集だった。ぼくは二冊を買い、なんとなく『ディングルの入江』のあとがきから読みはじめた。
二十年にわたる世界放浪の旅の末、アメリカを車で走っていた筆者は深い喪失感に襲われ、そして旅の終わりを感じる。そして、
ある時、私はふと「島」を書いてみたい、そんな衝動を持った。何かはわからなかったがともかく島だった。その島が自分の気持ちのいったい何を投影しているのか。それも見えなかった。それからしばらくたって島は徐々に言葉に置き換えはじめられていた。……。書き終えてのちも、その島の暗喩するもののすべて見えてきたというわけでもない。ただその島はこの二十年の旅の中で次々と無残な喪失を眼前にさらしつづけていったことだけは、私はよく知っている。そして、その島(ヒト・感情・関係・場所・時間・生死・輪廻・沈黙・想像・そして僕)のおそらくエントロピーの最後的なる熱死地帯としてのあの日本のニュータウン。
この人は正直に書きすぎてしまう。そうぼくは思った。小説家は、言葉の陰に身をひそめようとする本能を持っている。なのに、この人は真っ直ぐ人前に出てきてしゃべってしまうのだ。
それから、ぼくは『ディングルの入江』を読みはじめた。
主人公の「私」は、古い友人をたずねて、アイルランドの片隅、世界の果てのような光景を見せる入江と島にたどり着く。そこは世界の果てであるけれど、世界が見失ってしまったかけがえのないものがある場所でもある。
それを見つめる私ののどもとから不意に微温の血がせり上がり、頭部をわずかに加熱しているのを覚える。
……表現は時に古めかしく、
冬、寒風吹きすさぶ荒涼とした場所に、春には緑の衣をうち掛け、白く輝くシャムロックの花をちりばめ、夏には燦々(さんさん)とした陽光でその場のすべてを輝かせ……。
……時に美文に走り、
ところが島に居ついて半年ほど経ったある日、ワシのそんなかたくなな気持ちを打ち砕くような出来事が起きた。そう、あれは春も間近い三月の終わりのことだったな。
……時に説明調になる。全編に漲(みなぎ)る描写への不動の確信も含めて、この小説はあまりにもナイーヴに言葉を使い、だからぼくは不安になる。だがそれにもかかわらず、ぼくは小説にひきこまれていく。カメラの人藤原新也は言葉を信じない。だから、言葉をナイーヴに使うことを恥じない。ぼくたちはいま言葉を彼のように使うことができず、だが信じることもできないのである。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする