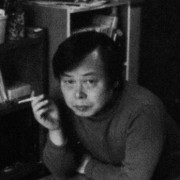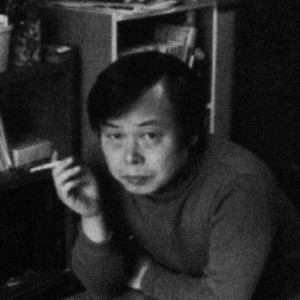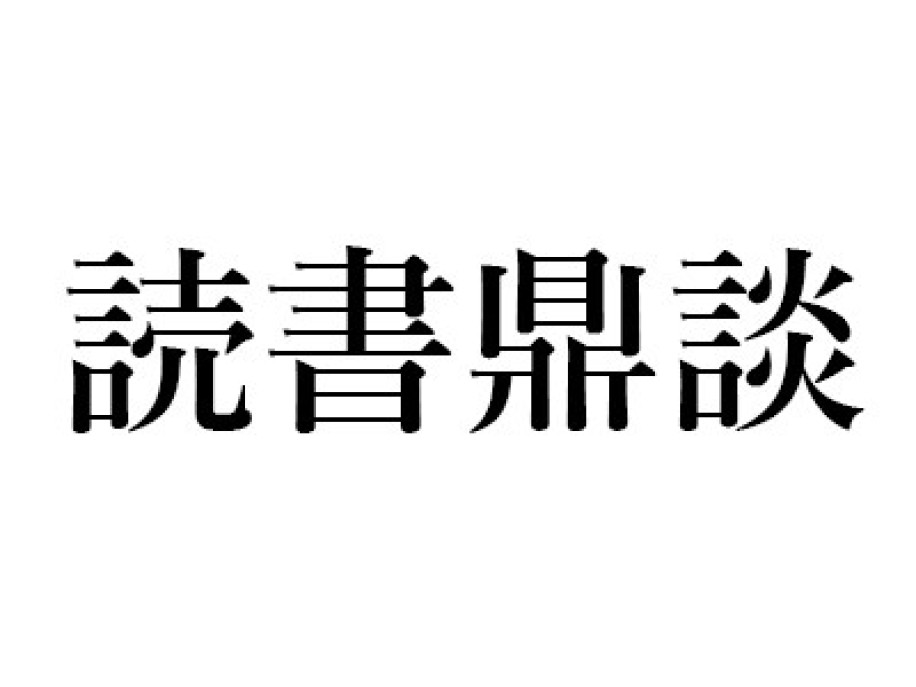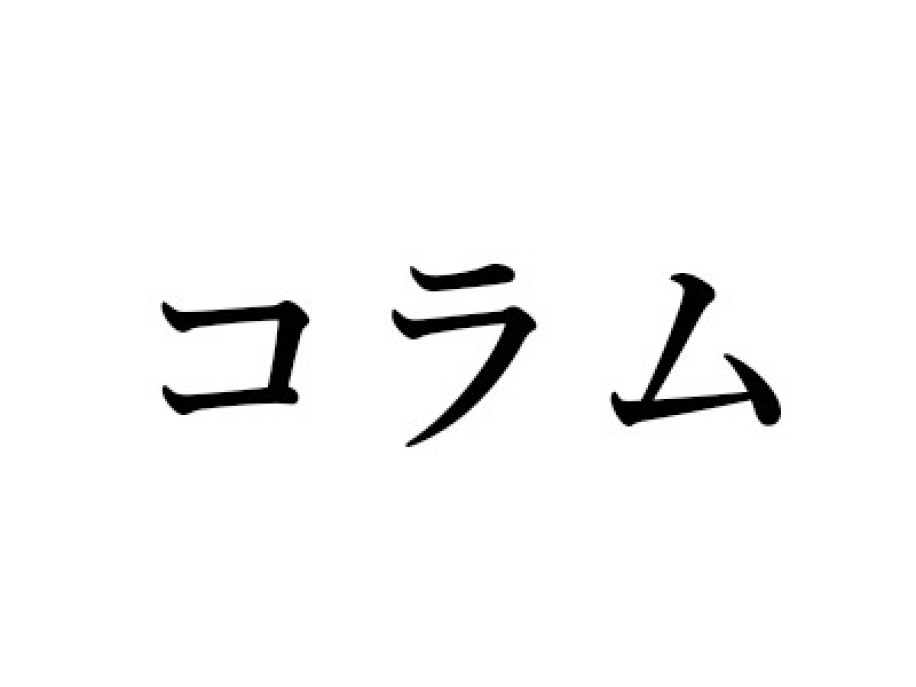書評
『私の昭和史』(青土社)
遠い、だが確かな記憶 詩人の半生
昭和二年(一九二七)生まれ。まだ田園だった大宮(さいたま市)に育った。後年の詩人中村稔は意外なことにスポーツ少年。全大宮が巨人軍と対決した時代の野球ファンで、器械体操が得意だったという。それにエノケンがごひいき。一家で遊びにいくときにはきまって大宮から浅草に出てエノケン一座へ。二・二六事件を遠雷のように感じながら、おおむね豊かな田園と中産階級の家庭にはぐくまれた幼少年時代を過ごし、やがて府立五中から旧制一高へ。ここらでもはや「昭和史」とは無縁でいられなくなる。それにしても今にして思われるのは、戦中の中等・高等教育が部分的にもせよかなり高度のレベルを持続していたことだ。リベラリズムで知られた五中は、戦時色が濃厚になった時代にも当局の意向に反して多様な価値観をはぐくむ教育環境を教師・生徒が共同して維持していた。当然のことに良友・良師にめぐまれる。その先で出会った一高の先輩・寮友も、すでに独自の価値観を形成していて時流に左右されない。
一高では国文学会の寮室に属し、中村真一郎、大野晋、いいだもも、のような戦後文学を用意した錚々(そうそう)たる先輩に伍(ご)して万葉集の輪講に加わる。弱冠十八歳のおどろくべき早熟児。それよりもおどろくのは、三月十日東京大空襲ぎりぎりまで浅草の東橋亭という小屋に通い詰めて娘義太夫を聞き、おそらく同じ小屋で「一人遣いの人形浄瑠璃で文楽のあらましを観(み)た」という稀有(けう)な体験をしていることだ。
一方で「昭和史」は家庭の中にまで入り込んでいた。東京地裁判事だった亡父がゾルゲ事件の担当判事だったからだ。後に亡父の述懐するには、「自分が出会った日本人の中で最も偉いと思ったのは尾崎秀実、外国人ではリヒアルト・ゾルゲ」。
「私」と「昭和」の硬軟両様が切り結ぶ、「私の昭和史」はとりあえず昭和前期の八月十五日で終わる。戦後詩を代表する詩人中村稔と知的所有権の現役第一線の弁護士中村稔の昭和後期については続編が予告されているが、一日も早い実現が待たれる。
朝日新聞 2004年8月8日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする