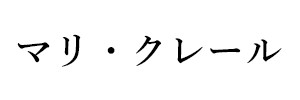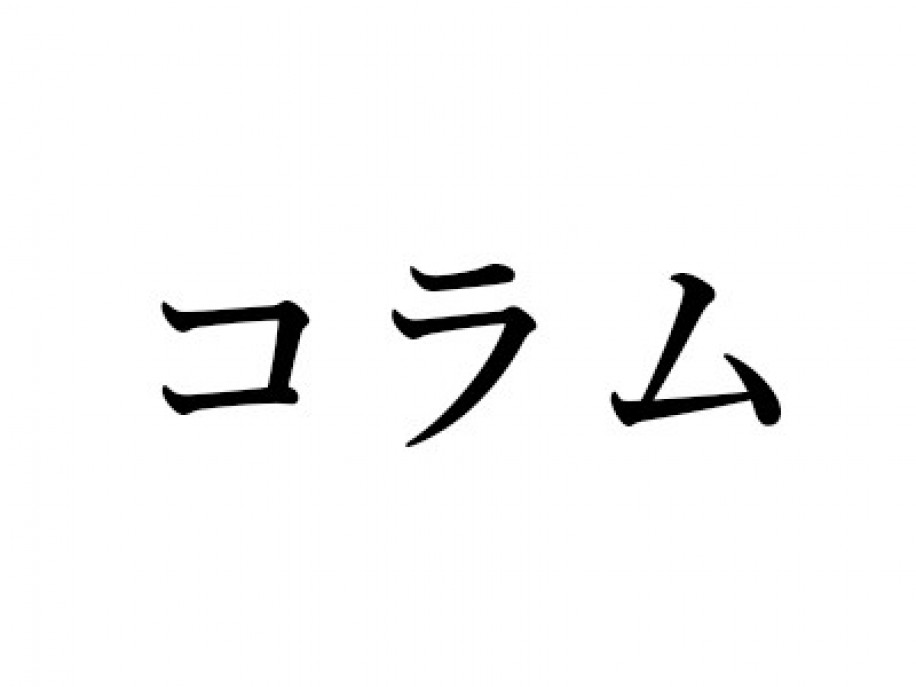書評
『パサージュ論』(岩波書店)
ベンヤミンの未完の大作『パサージュ論』は、これまで、その要約「パリ――十九世紀の首都」だけが晶文社版の『ボードレール』に収録されていたが、私は、この十五年間というもの、キリスト教徒がマタイの福音書を繰り返しひもとくように、この要約を一字一句熟読玩味(がんみ)して読み、そのたびに「ベンヤミンはすごい」と唸(うな)っていた。しかし、賛嘆すればするほど、たとえどのような断片であろうとも『パサージュ論』の草稿を読んでみたいと思う気持ちが募ってきたのも事実である。
草稿のほとんどが引用という話は聞いていたが、たとえそうであっても、その引用はどんなものか、またそれをどのように配列しているのかだけでも知りたいと思っていた。というのも、シュール・レアリスムと同じくアレゴリーとアナロジーを特徴とするベンヤミンの思考法に親しむにしたがって、引用のもつ重要性が次第にわかってきたからである。
とはいえ、そうした引用ばかりの草稿が日本語に翻訳されるとは夢にも思っていなかったし、またたとえ日本語に移しかえられたとしても、それが一般の読者に対してどれほどの意味をもつのか、正直なところわからなかった。
だが、予想はどちらも見事に裏切られた。『パサージュ論』の全訳は現にこうして翻訳が開始されたし、またその内容も、都市と近代性(モデルニテ)に関心をいだく読者であれば、この無数の引用の網目から伝わってくる熱いメッセージに、圧倒されずにはいられぬものだからである。
それに、なによりも目を見張ったのは、引用の間に挟まれたベンヤミンの覚書が、思っていたよりも数が多く、しかもそのどれもが深く彼の本質にかかわるものばかりであることだ。たとえば、つぎの言葉がある。
これは『パサージュ論』のもっとも明白な執筆意図であるといっていい。また「地誌的(トポグラフィッシュ)な観点」が重要であることは、タリド社のパリ地図についての次の断言からもうかがうことができる。
ところで、慧眼(けいがん)なる読者なら、市街地図から想像力を膨らませるのを好む「地誌的(トポグラフィッシュ)な観点」こそは、この『パサージュ論』を読み解くための解読格子(グリッド)であることに気づかれたにちがいない。すなわち、市街地図の愛好家が、二つの離れた通りがパサージュによって結びあわされていることを発見してそこに隠された意味を見いだすと同じように、読者は、一見、なんの脈略もなく羅列されたかに思える引用と引用が、その章題や末尾に添えられた「モード、遊歩者、流行品店、オースマン式都市改造」等のテーマによって一挙に引き寄せられて通底する様を見せられるのである。
いや、「見せられる」というのは適当でない。というのも、グリッドを設定する作業はむしろ我々読者にこそゆだねられているのだから。ちょうど、ゲーム・ブックかコンピュータゲームに熱中する少年のように、読者は各自、引用と引用を結びつけるキーを自分の好きなように選んで空想のトポグラフィーを構成することができる。そのトポグラフィーは当然のように時間軸をも包摂している。
十九世紀パリという特権的なトポスに、ベンヤミンが、パサージュ、モード、パノラマ、万国博覧会といった不意打ち的なキーでもって仕掛けた空間軸と時間軸の永劫(えいごう)回帰。この迷路の中で迷うのはなんという甘美な体験なのだろうか。
我々は、むしろ、この『パサージュ論』が未完に終わったことを喜ぶべきなのかもしれない。
なお、冒頭の「パリ――十九世紀の首都」は、本書では従来のドイツ語草稿のほかに、フランス語草稿からも訳されているが、これは、ベンヤミンのファンにとって、マタイの福音書しか知らなかったキリスト教徒が、マルコとルカとヨハネの福音書を同時に手にしたほどの価値がある。
「ベンヤミンの残した人類への遺産」という帯の惹句(じゃっく)は、大袈裟(おおげさ)なものでは決してない。
【この書評が収録されている書籍】
草稿のほとんどが引用という話は聞いていたが、たとえそうであっても、その引用はどんなものか、またそれをどのように配列しているのかだけでも知りたいと思っていた。というのも、シュール・レアリスムと同じくアレゴリーとアナロジーを特徴とするベンヤミンの思考法に親しむにしたがって、引用のもつ重要性が次第にわかってきたからである。
とはいえ、そうした引用ばかりの草稿が日本語に翻訳されるとは夢にも思っていなかったし、またたとえ日本語に移しかえられたとしても、それが一般の読者に対してどれほどの意味をもつのか、正直なところわからなかった。
だが、予想はどちらも見事に裏切られた。『パサージュ論』の全訳は現にこうして翻訳が開始されたし、またその内容も、都市と近代性(モデルニテ)に関心をいだく読者であれば、この無数の引用の網目から伝わってくる熱いメッセージに、圧倒されずにはいられぬものだからである。
それに、なによりも目を見張ったのは、引用の間に挟まれたベンヤミンの覚書が、思っていたよりも数が多く、しかもそのどれもが深く彼の本質にかかわるものばかりであることだ。たとえば、つぎの言葉がある。
かつてパリがその教会や市場によって規定されたのとまったく同様に、いまや地誌的(トポグラフィッシュ)な観点を十倍も百倍も強調して、このパリをそのパサージュや市門や墓地や売春宿や駅……などといったものから組み立ててみること。さらには、(……)この都市のもっとも人目につかない深く隠された相貌(そうぼう)から組み立てること。
これは『パサージュ論』のもっとも明白な執筆意図であるといっていい。また「地誌的(トポグラフィッシュ)な観点」が重要であることは、タリド社のパリ地図についての次の断言からもうかがうことができる。
この市街地図に没頭してみても想像力が目覚めず、市街地図よりもむしろ写真や旅行手記によって自分のパリ体験に浸るのを好む人、そんな人には手の施しようがない。
ところで、慧眼(けいがん)なる読者なら、市街地図から想像力を膨らませるのを好む「地誌的(トポグラフィッシュ)な観点」こそは、この『パサージュ論』を読み解くための解読格子(グリッド)であることに気づかれたにちがいない。すなわち、市街地図の愛好家が、二つの離れた通りがパサージュによって結びあわされていることを発見してそこに隠された意味を見いだすと同じように、読者は、一見、なんの脈略もなく羅列されたかに思える引用と引用が、その章題や末尾に添えられた「モード、遊歩者、流行品店、オースマン式都市改造」等のテーマによって一挙に引き寄せられて通底する様を見せられるのである。
いや、「見せられる」というのは適当でない。というのも、グリッドを設定する作業はむしろ我々読者にこそゆだねられているのだから。ちょうど、ゲーム・ブックかコンピュータゲームに熱中する少年のように、読者は各自、引用と引用を結びつけるキーを自分の好きなように選んで空想のトポグラフィーを構成することができる。そのトポグラフィーは当然のように時間軸をも包摂している。
大衆の音頭をとるのはつねに最新のものである。だが最新のものが大衆の音頭をとれるのは、実はそれがもっとも古いもの、すでにあったもの、なじみ親しんだものという媒体を使って現れる場合にかぎってなのである。そのつど最新のものが、すでにあったものを媒体として出来上がるというこの劇こそは、モード本来の弁証法の劇なのである。
十九世紀パリという特権的なトポスに、ベンヤミンが、パサージュ、モード、パノラマ、万国博覧会といった不意打ち的なキーでもって仕掛けた空間軸と時間軸の永劫(えいごう)回帰。この迷路の中で迷うのはなんという甘美な体験なのだろうか。
我々は、むしろ、この『パサージュ論』が未完に終わったことを喜ぶべきなのかもしれない。
なお、冒頭の「パリ――十九世紀の首都」は、本書では従来のドイツ語草稿のほかに、フランス語草稿からも訳されているが、これは、ベンヤミンのファンにとって、マタイの福音書しか知らなかったキリスト教徒が、マルコとルカとヨハネの福音書を同時に手にしたほどの価値がある。
「ベンヤミンの残した人類への遺産」という帯の惹句(じゃっく)は、大袈裟(おおげさ)なものでは決してない。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする