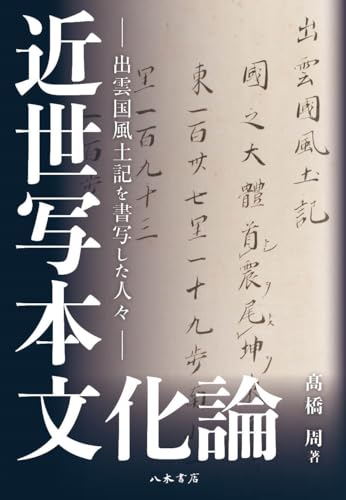書評
『生命の鎖』(飛鳥新社)
からだによい食事
何をどう食べるか。所帯を持って十数年、毎日考えてきたこと。が本書を読むと、私の苦労も、たかだか家族の好みと予算と料理技術のかねあいで決めていたにすぎないことに気づく。『生命の鎖』(丸元淑生、飛鳥新社)は、栄養学の立場から日本の食文化と農業政策を考察した分かりやすい本である。何を食べるかはわれわれを地球全体の経済的、政治的、環境的状況につなげていく、という壮大なテーマ。書きおろしで熱っぽい。
が、情熱はむき出しにされていない。モトモト小説家だけあって文章が読ませる。たとえば書き出しのさりげなさ。
「子母沢寛は、飯は冷やに限ると書いているが、私も冷飯をおいしいと思って食べるようになってもう十年以上になる」。それで知ったのはお櫃(ひつ)がおいしくご飯を冷やす工夫だったこと。食卓の風景を生き生き描きながら、電子ジャーがコメの栄養をいかに奪うかと展開していく。
題名の「生命の鎖」とは私たちが必要とする五十ほどの必須栄養素をさす。どれか一つ欠けても鎖はバラバラに切れてしまう。中でも指標となる栄養素に、葉酸とかパントテン酸なんてあるのは読者のみなさん、知ってるかな?
この鎖を強くする「からだによい食事=オプティマルな食事」とはどんなものか。
まず、腹八分目でも必須栄養素がとれるように多種類を少しずつ食べること。ところがもしコメ輸入が自由化されれば、すでに減少しすぎた農家がさらに減少する。よい食事は小さな家族農家がつくる多品種の食品群にささえられているから、これは大変。この、栄養学から「コメの自由化」を考える視点は斬新だ。私たち消費者は、コメは安い方がいいと思い、「一粒たりとも」と絶叫する族議員の姿に、あれは「農家だけの問題だ」としらけがちではないか。突然、お尻に火がついたかんじ……。
第二に体にストレスを与える添加物や農薬をとらないことだ。コメの自由化によるポストハーベスト米(収穫後に輸送のため農薬をかける)や、工業化されたカリフォルニアのまずい農薬づけトマトのゾーッとする話を満載している。
第三に、炭水化物、脂肪、タンパク質の比率が適正であることが大事だという。が、戦後、脂肪の比率はどんどん高まり(一九六二年二〇パーセント→一九八九年三〇パーセント)それに従い、ガン、心臓病、糖尿病などが増加している。原因は肉食だ。ここでハッとしたのは、小麦がコメを駆逐したのではなく、肉が主食となり、米飯が添えものになって減ったという指摘である。そういえば私がこどものころ、母は「ご飯はいいからおかずを食べなさい」とくり返していた。高度成長期の子どもはコーラでショートケーキを食べ、ハンバーグやステーキが大ご馳走だった。
ご飯は「太る」「栄養がない」という俗信も根深い。著者は反論する。「戦国武士は一日五合も食べていた。清洲から桶狭間まで武装した肥満兵士が駆けられるものか」。これには大笑いした。
なんと一ポンドの牛肉をつくるのに十六ポンドの穀類や豆が飼料にされている。これは資源のムダだ、と環境問題にも筆は及ぶ。休耕田の表土流出、過放牧による砂漠化、食物連鎖(大きな魚が小魚を食べ、豚が殼類を食べるということ)による農薬の蓄積。こうなるとすべて輪廻に見えてくる。が、丸元さんは終末予言者的ペシミストでもなく、自分だけ良けりゃのノアの方舟的自然食論者でもない。「食物連鎖の下位のもの、穀類と豆類を中心に、野菜、果物、小魚、乳製品を食べ、たまに肉を食べる」ことを提唱する。日本の伝統食はこれであり、これこそ環境汚染から自分を守る食事であり、地球を守る食事でもある、と。この明るさがうれしい。
好きな人の弱味をみつけるのも愛のうちというから一つ二つ。タンパク質摂取量と出生率は逆の相関がある。だから人口爆発の解決にはまず十分な栄養摂取を、というのは飛躍だろう。相関関係必ずしも因果関係ではない。
専業主婦の家事時間が二十年で二十八分減ったのは、手間のかかる料理を作らなくなったというのもちょっとね。電子レンジでチンなど電化もその原因だろう。また「家庭料理」にこだわりすぎるのも、「女よ家に帰っておふくろの味をつくれ」に利用される危険がある。が、その解決はじつは最終章「住みよい都市」に明示されている。都市の中に農地があり、職場が近く、住まいの近くに魚屋、八百屋、肉屋、そして手作りの良質な惣菜屋があったらよいのではないか。
本書を読んで衿を正し、きのうは〈サンマの刺し身、大根の味噌汁、さつまいものレモン煮、春菊のおひたし、じゃことスライスオニオン〉を三十分でつくった。刺し身も自分でおろした。私のようなモノグサをも動かす威力ある実用書なのだ。が、のどもとすぎればなんとやら。たまに読み直して慄然(りつぜん)としないとね。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする