書評
『トリエステの坂道』(新潮社)
遠い日の思い出
年に数本の映画さえ見る暇がない。だけど、待望の須賀敦子さんの本はいつも極上の映画を観たような気がする。『ミラノ 霧の風景』『コルシア書店の仲間たち』『ヴェネツィアの宿』とつづく随筆群には、いつも遠い日の人々の思い出が息づいている。私はたまにしか出ないそれらの本を、大事なお菓子を戸棚に隠すようにして、少しずつ少しずつかじる(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1995年頃)。『トリエステの坂道』(みすず書房)には著者の夫、書店で働いていたペッピーノ氏の家族のことが丁寧に語られている。夫の父、ゲジゲジ眉のルイージ氏は、著者が夫と出会う前に亡くなっていたが、鉄道員だった。娼婦たちに信頼され、その身入りを預かっていた人だった。奔放で喧嘩好きの夫をもった姑は自分の菜園を作り、著者が家を訪ねると太った体で椅子を軋(きし)ませて立ち上がった。嫁に菜園を見せたい。一家からは長男のマリオ、末の女の子ブルーナ、そしてルイージ氏が死によって次々とひきちぎられていった。
この人たちは、水の中で呼吸をとめるようにしてつぎの不幸までを生きのびている。そして、それが、この人たちにとって唯一の可能な現実なのかも知れなかった。
そして、著者の夫ペッピーノも二十年前の六月、四十代で息を引き取る。
正直にいうと、かつて西麻布のお屋敷のお嬢さんであり、現在はイタリア文学の翻訳で知られる大学教授であるという著者の、その二つの存在の間に、このような北イタリアの貧しい家の嫁であった時間があったとは不思議なようでもある。しかし与えられた環境だけを潔しとせず、そこから跳び出して真剣に一生懸命に生きた著者の航路が見えるようで胸が熱くなる。
そしてミラノの普通の人々。最小限住宅(カーセ・ミニメ)の少女イヴァーナや、市電に飛び乗ってくるルドヴィーコ神父や、傘もなくて上着の襟を立てて雨の中を走る花売りのトーニ、その生きいきとした姿が深い愛情とともに描写され、彼らの生きていた北イタリアの町が身近に感じられる。
こんな人は私の町にだっていたじゃないか。家の前を通っていた都電二十番線や、千歳湯で会った猛烈な重ね着をする三段腹のおばあさんや、田端の鉄道病院の混み具合いや、町の厄介者ながら愛されていた米屋の娘……そうした自分の大切な風景や人々が思い出され、人の気持ちに国境なんかないと思う。地球の反対側に住む人々をすぐさま信用できる気分がする。
この本は著者が愛する詩人、ウンベルト・サバの住んだトリエステを訪ね、その暮らした町の坂を息を切らせて上り下りするところから始まる。サバの働いていたのは「ふたつの世界の書店」という名だ。著者自身が日本に生まれ育ち、イタリアの男性と結婚してその土地を愛し、書房の経営に参加し、再び日本に帰った。二つの世界をいつも往還している。
東京にいても著者は亡くなった夫の家族を忘れず、義弟アルドやその妻シルヴァーナ、甥のカルロの動静に一喜一憂して、親身に、彼らを大事にして生きている。そればかりか貧しいイタリアの家族の方に身を寄せて、「とりすました中流階級の住宅」や「彼らがみずからの手をよごして得たのではない」毛皮や宝石をもつ人々に、小さく憤ったりする。
閉じこもった悲しみの日々にわたしが
自分を映してみる一本の道がある。
どんな人と懐しく触れあっても人は一人で生きざるを得ない。掲げられたサバの詩の一節は、そのかけがえのない人びとの憶い出を心に繰り返しながら、も少し内面に降りていこうとするとき、私の励ましとなる。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
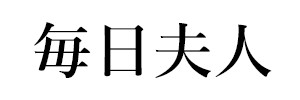
毎日夫人(終刊)
ALL REVIEWSをフォローする




































