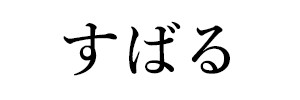書評
『なぜ古典を読むのか』(みすず書房)
案内としての批評
古典文学を論じた書物は数え切れないほどある。だが、論述の対象となっている作品をこちらも読んでみたい、読み返してみたいと感じさせるものは案外少ない。作品の歴史的な位置づけと丁寧で新味のある読み込みの双方をこなしながら、それをまぎれもない現代文学の読解へとつなげていくような、つまり独立した小論やエッセイの完成度を保ちつつ全体として最良のチチェローネたりうる文章とくれば、なおさら稀少だといっていいだろう。ところがここに、その例外があっさりと姿を現わしたのだ。自身すぐれた小説家であると同時に、博覧強記の編集者であったイタロ・カルヴィーノによって。『なぜ古典を読むのか』という地味な表題を付されたこの書物は、一九五〇年代半ばから八〇年代半ばまで、およそ三十年にわたって散発的に書かれた解説や記事の寄せ集めなのだが、そのような時間の経過を感じさせない潑剌とした精神の躍動にあふれている。古典とはなにか、その説得力に満ちた楽しげな定義にはじまって、誰もが「古典」と認める類のよく知られた作品から、カルヴィーノの慧眼と趣味を如実に示す十九世紀の大御所たちの、しかし彼らの経歴のなかでもあまり代表作に挙げられない品目ーディケンズ『我らが共通の友』、トルストイ『ふたりの軽騎兵』、トウェイン『ハドレイバーグを堕落させた男』、スティーヴンソン『砂丘のあずま屋』――に移行し、ガッダ、ヘミングウェイ、ポンジュ、クノーら二十世紀の作家へといたる構成はまた、一貫した視点と編集術の結実でもある。
カルヴィーノは、簡潔で愛情のこもった語りのなかに、ときおり刃物のように鋭利な一文を滑り込ませる。どの章にもはっと眼を見張る指摘が隠されていて、読者の精神をいっときも退屈させない。「行動する作家としてのクセノポン」にローレンス大佐を対置し、『変身譚』や『カンディード』に「速さの詩」を読み、トルストイの「人生」が芸術=技術の複雑な技巧の産物だと看破したかと思えば、クノーの『はまむぎ』がデカルトの『方法序説』を「小説的に注釈しようとした作品」ととらえ、モンターレの詩の特質をボルヘスと連結させて、垣間見られた無の深さを摘出してみせる。けれどもそこに、さかしらな匂いはまったくない。古典を、いや本を読むのは、それがなにかの「役に立つ」からではなく、読まないよりはましだからであるという事情を、カルヴィーノはきちんと弁えていた。明るさと節度を保った彼の言葉は、だからこそ信用に値するのである。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする