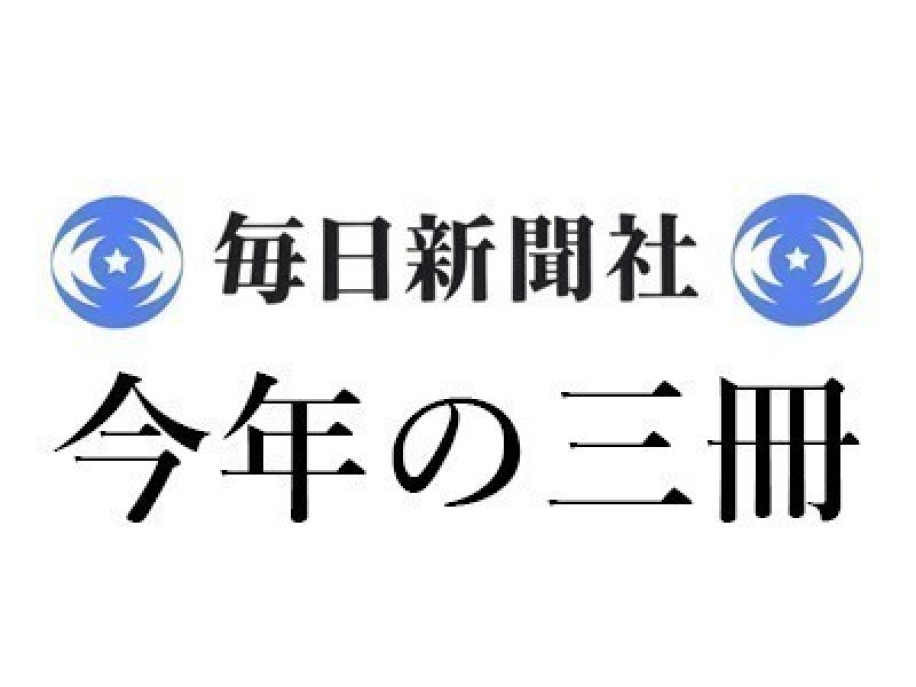書評
『闘牛』(毎日新聞社)
角の破壊力、その技、牛の相撲は激しい
闘牛について、といってもスペインの牛対人のじゃなくて日本の牛対牛の闘いについて、誰でも一度は映像で目にしたことがあるだろう。大きな牛が、土俵のような場所で、頭と頭をウンウン押し合って、そのうちどっちかがスタスタと逃げて勝負あった。同じ動物同士の闘いでも闘犬や闘鶏とちがい、横に人が付いて闘う。映像で何度も目にしたけれど、どこが闘いなのか、何が面白いのかサッパリだった。
大きな牛が押しあう姿は、近年の相撲の技のない腰高の大型力士同士の取り組みみたいで退屈だし、牛の脇にいて首筋をたたいたりしているハッピを着たオジサンは、とても一所懸命なのだが、何のためにいるのか分からない。犬や鶏みたいにどうして動物だけでやらないのか。
こうした疑問が国民的に広がったせいかどうか知らないが、現在、日本の闘牛界は下り坂だという。沖縄、奄美、宇和島、隠岐、新潟、八丈島、この六カ所にからくも伝わる闘牛だが、今や観光用に化したり、休止したり、この先どうなるか予断を許さない。
そうした中で、例外的に奄美とりわけ徳之島の闘牛は昔ながらの熱気に包まれ、観光客が来ようが来まいが、島の人たちは闘う牛を囲んで盛り上っているらしい。一見すると退屈そうな牛の押し相撲のどこが島の人々をかくも夢中にさせるのか、たまたまハブの毒の研究に徳之島に出かけて闘牛にとり付かれてしまった著者が、八年をかけて書いたノンフィクション。
主人公の牛の名は〈実熊(さねくま)牛〉。もちろん実在の牛で、闘牛界の双葉山というかルー・テーズというか、生涯の戦績は四二勝一敗一分け。昭和三十七年の待望の徳之島空港の開港式の日には、島の英雄の朝潮と並んで土俵入りをしたほど。正確にいうと、闘牛場でまず朝潮が土俵入りし、その後、実熊牛が土俵入りして、赤鬼という名の牛と対戦している。朝潮が露を払うかたちだったのである。
牛の相撲の実際を、その時の土俵に見てみよう。対戦相手は角の立派さから赤鬼と呼ばれ、三百キロもの体重差の巨牛。
蹴りたてていた前足を揃え、頭を低くして左角を押し当てる体勢で赤鬼は突進してきた。ガツン、ゴチン。角と角がぶつかる鈍く、重い音が客席の前方には聞こえた。
体重に劣る実熊が後ずさりを余儀なくされると、相手はここぞとばかり攻めたてる。
赤鬼はさらに一歩前に出る。坊(実熊)は頭を低くしてこらえるが、赤鬼の右角の先が坊の額に食いこみ、鮮血が見えた。早くも流血。
ここから、両者のマキツキ(眉間突き)の応酬がはじまるが、相撲の突張り合戦の時に腕の長い方が有利と同じように闘牛でも角の長い方が優勢。赤鬼のマキツキにやられながらも実熊の勢子(例のハッピのオジサン)は反撃を許さず耐えさせる。すると、効果がないと見た赤鬼の勢子は作戦を変え“突き”に転じた。マキツキは額を押し付け合いながらの突きだが“突き”はいったん頭を離してからの突きで、破壊力は大きい。
赤鬼の突きはそれから五分以上続いた。まだ坊は攻撃しない。鮮血に染まりながらも、まだ立っている。強固な精神力だけで立ち尽しているような趣を醸し出し、赤鬼は震え、ついに攻撃をやめた。
この時を待っていた実熊の勢子が、かけ声とともに背をたたくと、実熊は、左の角で相手の頭をいなした後、裂帛(れっぱく)の突きを見せる。
赤鬼と比べれば短い角だが、坊の角は赤鬼の額にめり込んでいる。血が頬を伝わってしたたり落ちた。経験したことのない痛みに赤鬼は思わずアウガンした。
絞り出すような声をアウガンという。勢子がさらに背をたたくと、実熊は三百キロ差の相手を土俵際まで押して行く。するとおびえた赤鬼は柵に沿って逃げ出す。
勢子の判断、角による技のかけ合い、その破壊力、そして敗けた牛の逃走、たしかに牛は人より激しい相撲を取る。
徳之島の人たちが闘牛に熱中するのは、格闘技として面白いからだけではなく、牛がオーナー一家と一族の絆の象徴だからだという。対戦の前夜には一族が集って酒を交わし作戦を立て、勝つと土俵になだれ込んで、牛の回りで手舞い足舞い。そして、牛を先頭に、行列を組んでの勝利の家路。大相撲がわざわざ出身地をアナウンスするのは、もともと力士は地域の大地と社会のパワーの象徴として存在したからだというが、徳之島の闘牛は、その激しさと地域への密着性において、人の相撲よりずっと相撲らしい。
闘牛についての積年の疑問が、この本の出現でやっと解けたが、冬季オリンピック種目のカーリングについても早く誰かその魅力について一冊書いてほしいものだ。
【旧版】
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする