書評
『男流歌人列伝』(岩波書店)
思ひしはみな我のことなり
大岡信『一九〇〇年前夜後朝譚』(岩波書店)は従来の権威主義的な文学史の、いわば関節はずしともいうべき楽しい本です。なかでも従来の文学史は小説偏重でありすぎる、との一言に不意をつかれ、にわかに歌集や句集をひもときはじめました。そんなとき道浦母都子『男流歌人列伝』(岩波同時代ライブラリー)は手ぎわよいガイドとして最適です。「女流」というレッテルはりへの抗議と皮肉も込めたタイトルですが、啄木、赤彦、茂吉、利玄、八一といった巨大な歌人たちに敬意を込めてとりくんだ本で、女性誌に連載されただけにたいへん読みやすい。女性である著者の批評的視点もユニークです。
たとえば恋の勝利者となったのちも、夫鉄幹に添う数多の女性の影に懊悩した晶子。しかし背中合わせのように鉄幹は、
あめつちに一人の才とおもひしは浅かりけるよ君に逢はぬ時
と詠んでいます。日々避けがたい彼と彼女の才能のせめぎ合い。鉄幹もつらかっただろうなあ。
かと思うと、前田夕暮の幸せな妻とされる狭山信乃には、こんな歌がある。
妻といふ名の寂しさよいつしかに若きほこりにのこされし身の
若いころ「夕暮より上手だ」と評された彼女は「どこかで歌人である自分を捨てたのである」と著者は書いています。
さて、ストイックで学問一筋に見える佐佐木信綱に、
ちさき椅子にちひさき身体よせゐたりし 部屋をふとあけておこる錯覚
といった亡き妻をしのぶ痛切な歌があるのも意外ですし、いかつく野暮ったく見える「牛飼い」伊藤左千夫に、
夕ぐれの三日月のうみ雲しづみ胸しづまりぬ妹に逢ひし夜は
なんてロマンチックな歌があるのも驚きです。
若山牧水というと、
幾山河越えさり行かば寂しさのはてなむ国ぞ今日も旅ゆく
はじめ人口に膾炙(かいしゃ)した歌が多すぎ、観光地に行けば牧水の歌碑がごろごろで、やや通俗的の印象が消えませんが、ここで著者は、
山を見よ山に日は照る海を見よ海に日は照るいざ唇を君
という名唱と人妻との秘められた恋を紹介しています。いいよね、この歌。
石川啄木は「数え年二十七歳で夭逝し、年を経るに従っての作風変化をみないまま、歌人として完結してしまった」と評されていますが、この人って本当にネアカでエゴイストですね。
その膝に枕しつつも
我がこころ
思ひしはみな我のことなり
バカヤローといいたくなる。こんな自分しか愛せない男と暮らして「愛の永遠を信じたく候」と願った妻節子はどんな気持ちだったのかしら。
道浦さんは一方で激しくドラマチックな恋に魅かれつつ、同時に一対一で向き合う、つまり“対”の関係にこだわっているように見えます。愛の排他性というのかなぁ。私には、そこがちょっと息苦しい。
それと一つ、正岡子規の、
瓶にさす藤の花ぶさみじかければたゝみの上にとゝかざりけり
を著者は「静止した絵画のよう」と評していますが、そうかしら。
脊椎(せきつい)カリエスで病床からじっと眺めている。花ぶさの先端が畳につくようでつかない。じれったくてつけ、と念ずると花ぶさが伸びたり、縮んだり。大変シュールで動的な歌のように思えます。天井の木目、唐紙の模様、限られた室内を目で追い、それを感性への刺激にするしかなかった子規の痛ましさがしみるのです。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
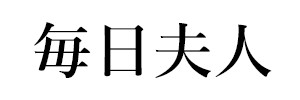
毎日夫人(終刊) 1993~1996年
ALL REVIEWSをフォローする



































