書評
『風の婚』(河出書房新社)
別れること、一人で生きること
朝、一はらのたらこを二つに分けようとするとき、ふと離婚を思う。たらこは薄い膜でしっかりくっついていて、無理に箸で分けると破れて、身がぶにゅ、ととび出してくる。まるで腹わたがとび出るように。ともに暮らした年月が長いほど、別れの手術はつらい。今日われは妻を解(と)かれて長月の
青しとどなる芝草の上
解かれて、という言葉の晴れやかさ。おたがいを縛りあって、からまりあって、根腐れをおこしそうな日々。そこから解かれてみる、おたがいに。そして九月の濡れた草の上に、服が汚れるのもかまわず腰をおろし、手足を思いきりのばしてみよう。
水の婚 草婚 木婚 風の婚
婚とは女を昏(くら)くするもの
ちょっと言葉あそびみたいだけど実感がある。いろんな婚があっていい。風の婚とは通い婚かしら。その上の句の自由さを反転して、「昏くするもの」といい切ってしまう。ちょっと図式的。でもこの言葉のパワーは頼もしい。
人生の半ばをともに暮らした人と別れ、世界が色を失って、毎日、何を見ても、何を聞いても、涙がこぼれてならなかったとき、私を救ってくれた一冊の歌集が、この『風の婚』(道浦母都子、河出書房新社)である。
今朝は雨 秋の雨降る明るさを
身軽(みがる)となりしからだが吸えり
朝の雨の明るさ、あたたかさ。別れも不思議にあたたかい。どちらだけが悪いわけでもない、でも罪悪感は心に澱む。そんなとき、この歌を口ずさむと、生きることを肯定しないでどうしよう、と思う。雨のしめり気を体内に吸い込んで……。
道浦母都子は、政治に遅れてきた世代の私には一つの憧憬だった。思想の上で同じ地点にたつかどうかは別事として。
炎あげ地に舞い落ちる赤旗に
わが青春の落日を見る
第一歌集『無援の抒情』は、「今日生きねば明日生きられぬ」という性急さが占め、張りつめて痛々しい。しかし、その後も全共闘世代の男性たちが、ともすれば過去を美化して絶叫し、あるいは風化させて何くわぬ顔で世渡りするとき、道浦さんはあいかわらずま正直に一つ一つを問うている。じつに不器用に生きている。それが『風の婚』への私の第一の共感だけれど、経験の相似形にはドキリとさせられる。
身延線鰍沢(かじかざわ)駅かつてわれ
夫(つま)と並びて影曳きし駅
元・夫(つま)の姓のままにて夏柑(なつかん)の
匂う木箱が届けられ来ぬ
町角に、駅に、山に、港に、刻まれた思い出は残酷だ。夫への手紙はまだ家に来るし。いまはもう一緒に暮らしてないの、というと電話の向うで息をのむ友がいる。そんな過渡期がすぎて、ようやく生活は落ちつきをとりもどす。
(次ページに続く)
初出メディア
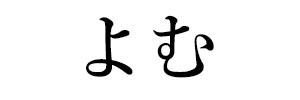
よむ
ALL REVIEWSをフォローする






































