書評
『風の婚』(河出書房新社)
行きずりの虹のごとしも
十年を共に暮らせしひとのことすら
私の場合、間に三人の子がいるので、父親との縁は完全には絶たれない。二人で積んだものもある。それでもあんなに強くあった記憶が、最近はぼんやりしてきた。そのくせ夢にはよく出てきて、記憶は夢のつづきか、夢が記憶のつづきなのか、判然としない。
子守歌うたうことなき唇に
しみじみ生(あ)れて春となる風
道浦さんとは反対に、私は娘時代に歌ったアリアやリートが突然、唇によみがえってきた。そういえばここ十年は子守歌しかなかった。結婚する前の自由さや、伸びようという本能を、家庭が妻や母であることが、知らず抑圧していたのではないかと思う。
五階なる午睡に兆(きざ)す性欲は
ゲンノショウコの花の香ぞする
これはなかなか散文では描き得ないし、作品になりにくい。歌にはかなわない。俵万智さんもさわやかだな、と思うが、道浦さんの歌のようにゆすぶられない。林あまりさんの歌は作りものめいている。胸もとのリボンを結べばもう仕事にもどれるほどの男ならいなくてもいいや、と思ったり、反対に激情と修羅場を逃れられないのは、私の世代までなのかな、とも考える。
『風の婚』のもう一つの特徴は、全編、ひたひたと水音が響いていることだ。
かつて妻いまは独りのわたくしが
神崎川の水面に映る
夢前川 雨のち晴れの空を呑み
草の匂いの水を運ぶも
神崎川に夢前川(ゆめさきがわ)、どちらもなんてきれいな名前なのだろう。水は傷を癒す。ひとつところにとどまり得ぬ自分を映す。制度の外にいったん出たとき、自分がどこまで流れていくのか怖い。私は三人の子供でようやく岸につながれているけれども。道浦さんは父母の血を自分でとざすことを考え、灰ではなくて、いつか自分が水になる、と感じているようだけれども。
明治十九年、東京の神田区では婚姻件数二〇二八に対し、離婚件数は二〇四一あったそうだ(小木新造『東京時代』)。くっつくより別れる方が多かった。「夫婦ハ離レモノ、合ヒモノナレバ厭ナラ直二来レト」と『東京穴探』にもある。高度成長の傾斜生産方式にしたがって都市に流入した人々がたまさか核家族をつくったんなら、そんなもの、五五年体制といっしょに滅びてもいいんじゃないの、とこれはひたすら自分を励まそうとしての合理化だ。
「どうしようもなく一人が好きで、一人の時間の中でこそ、全き自由でいられる私なのに、また、どうしようもなく人恋しい私でもあるから」というこの歌人の歌に、私は「自分に似た人」をさがし、生きる力を取り戻す。
悲しみは一人処理して生きゆかん
街は霜夜(そうや)の光の地上
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
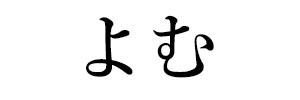
よむ
ALL REVIEWSをフォローする






































