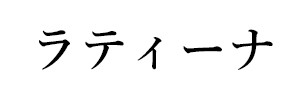書評
『ぼくは始祖鳥になりたい』(集英社)
読まれずに滅びようとしている文学にかろうじて役割があるとしたら、世界の生々しさを甦らせることだと私は思う。私たちは、世界をリアルに感じられないがゆえに生きてゆけないというところまで、追い詰められているからである。この生々しさを「生きる意味」と呼ぶとしたら、『ぼくは始祖鳥になりたい』は、そんな「意味」に満ちた奇跡的な小説である。
かつてスプーン曲げの超能力を持っていた日本人青年ジローは、アメリカ大陸へ渡って、黒人の宇宙飛行士や、北米インディアンの独立闘争の戦士、その仲間の混血女性、ニカラグアの反政府ゲリラのインディオなどと生をともにし、その中で極限的な体験を重ねる。ジローは、現在ある世界に抗う彼らから、「生きる意味」を取り戻そうと祈る声を聞きとり、その声と言葉を自分の意識の中に蓄積することで、彼らと一体になろうとする。
その中で読む者が圧倒的に感じるのは、一瞬一瞬、ひたすら「なまもの」として迫ってくる世界である。「なまもの」というのは、自分になじみがあり共感の持てる日常世界とは、正反対のものである。こちらの理解を拒み、押しつぶしてくるような、むき出しの「物理性」である。ニカラグアの密林の空は「どんな思いを投げかけても、にべもなくはね返す鉱物の青さ」で、「キノコ雲のように野放図に湧きたつ積乱雲があまりにも白く、眩しすぎて、まわりの青空が黒ずんで見えた」りする。夕闇は常に「天が漏水するように」深い藍色に染まる。都会の木立や、冬の砂漠の夜明けの空や、カリブの珊瑚礁や、ニカラグアの密林や、企業の幹部が飼う蛇や、脳波計の波や、ジローが想像する日系人女性の服の色は、どれも「エメラルド・グリーン」である。
このような描写が幾度となく繰り返されるうち、世界の生々しい物理性は、言葉の物理性へと変わっていく。「モノ」と化した言葉は、読む者の脳の中へじかに植えつけられ、例えば何度も反復される「天の漏水」という言葉を見ると、密林の雨水や、恋人のインディアン女性が「川の水を掬って飲むときの、蓮の花の色をした掌」など、この小説に現れるすべての「水」が連想され、言葉の水に溺れてしまう。そして、ただの言葉でしかない「水」を通して、小説の祈りを共有し始めるのだ。
それだけではない。これら地の文の言葉たちは、最後にジローが宇宙へ向けて発する声の中にまで侵入し、インディアンの歌などと混ざりあう。ジローはこの小説に書かれたあらゆる言葉をいま一度再生させることで、世界への「いとおしさ」という意味を体現するのである。
かつてスプーン曲げの超能力を持っていた日本人青年ジローは、アメリカ大陸へ渡って、黒人の宇宙飛行士や、北米インディアンの独立闘争の戦士、その仲間の混血女性、ニカラグアの反政府ゲリラのインディオなどと生をともにし、その中で極限的な体験を重ねる。ジローは、現在ある世界に抗う彼らから、「生きる意味」を取り戻そうと祈る声を聞きとり、その声と言葉を自分の意識の中に蓄積することで、彼らと一体になろうとする。
その中で読む者が圧倒的に感じるのは、一瞬一瞬、ひたすら「なまもの」として迫ってくる世界である。「なまもの」というのは、自分になじみがあり共感の持てる日常世界とは、正反対のものである。こちらの理解を拒み、押しつぶしてくるような、むき出しの「物理性」である。ニカラグアの密林の空は「どんな思いを投げかけても、にべもなくはね返す鉱物の青さ」で、「キノコ雲のように野放図に湧きたつ積乱雲があまりにも白く、眩しすぎて、まわりの青空が黒ずんで見えた」りする。夕闇は常に「天が漏水するように」深い藍色に染まる。都会の木立や、冬の砂漠の夜明けの空や、カリブの珊瑚礁や、ニカラグアの密林や、企業の幹部が飼う蛇や、脳波計の波や、ジローが想像する日系人女性の服の色は、どれも「エメラルド・グリーン」である。
このような描写が幾度となく繰り返されるうち、世界の生々しい物理性は、言葉の物理性へと変わっていく。「モノ」と化した言葉は、読む者の脳の中へじかに植えつけられ、例えば何度も反復される「天の漏水」という言葉を見ると、密林の雨水や、恋人のインディアン女性が「川の水を掬って飲むときの、蓮の花の色をした掌」など、この小説に現れるすべての「水」が連想され、言葉の水に溺れてしまう。そして、ただの言葉でしかない「水」を通して、小説の祈りを共有し始めるのだ。
それだけではない。これら地の文の言葉たちは、最後にジローが宇宙へ向けて発する声の中にまで侵入し、インディアンの歌などと混ざりあう。ジローはこの小説に書かれたあらゆる言葉をいま一度再生させることで、世界への「いとおしさ」という意味を体現するのである。
ALL REVIEWSをフォローする