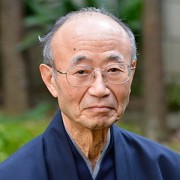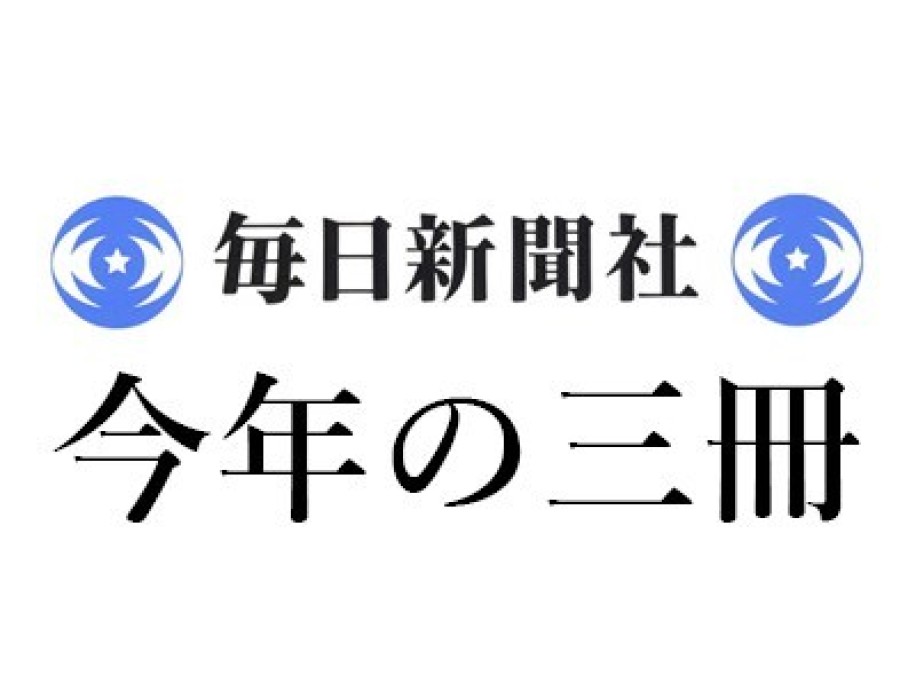書評
『涙の歴史』(藤原書店)
「啓蒙」から「ロマン」へ変貌
私は山本周五郎と藤沢周平のファンである。その小説の主人公たちが流す涙に心をゆさぶられるようになってから、どのくらい経つか。ともかくそれが、読む者の肺腑(はいふ)に喚びさます感情のうねりはただ事ではない。周五郎と周平の「涙」の結晶を味わうだけで、おそらく昭和時代における日本人の感覚をつかみだすことができるだろう。日本の社会に浸透する欲望や愛情や感傷の万華鏡を、一挙に照らしだすことができるはずだ。ひるがえって本書はどうか。フランスの十八世紀は、人びとの流涙現象にたいしてあるかぎりのファンファーレが奏でられた時代だという。小説の中で、劇場で、革命の街頭で涙の花束が交換され、厚手、薄手の感動が打ちあげ花火のように話題になる。その典型がジャンジャック・ルソー、そしてディドロ、さらにどこまでもつづく三文小説の、破片のような言葉の羅列……。総じてこの時代の特徴を啓蒙主義という。とすれば、さしずめ「啓蒙の涙」ということになるか。
だが十九世紀に入って事態は徐々に、そして一気に変貌をとげる。涙の体験に中産階級の抑制が働き、慎み深さという名の内面化、女性にかぎられる感受性の個別化が始まる。真情吐露への反動、神経症的涙の拡散がつづいて発生する。その典型がスタンダール、バルザック、そしてふたたびみたこともきいたこともないようなメロドラマや三文小説の断片群の分列行進……。その時代を眺望して、キリスト教的な苦痛主義とロマン主義が浮上してきたのだという。とすればこちらは「ロマンの涙」という仕儀になるだろう。
著者はフランスの「社会史」の分野で評価される旗手であるそうだ。気のきいた科白(せりふ)、切り口のサエ、驚くべき博識、――いずれをとっても感動的であるのだが、全巻読み終えて私は涙も涸(か)れるような退屈を味わった。「社会史」とはまことに玄妙(げんみょう)な歴史学というほかはない。願わくはこの辛口の一文が、反って本書の紙価を高からしめんことを。持田明子訳。
ALL REVIEWSをフォローする