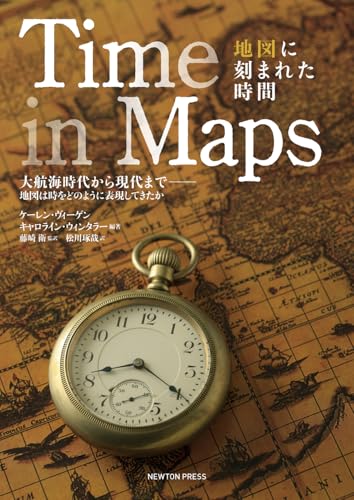書評
『ジョルジュ・サンドセレクション 別巻 サンド・ハンドブック』(藤原書店)
「女性のための闘士」の全貌明らかに
ジョルジュ・サンドという名を聞いてすぐに思いあたる日本人はほとんどいないのではないだろうか。なにしろ、フランス本国にあっても、二十世紀には忘れ去られた作家であった。それが同世紀後半になって、およそ二万通にものぼるサンドの書簡が収集され全二十六巻の『書簡集』として出版されたばかりか、彼女の作品多数が次々と世に出て来たのだ。おりしも、二十年前の二〇〇四年は彼女の生誕二百年にあたり、フランス政府は「ジョルジュ・サンド年」として制定し、祝賀の式典が挙行されたほどである。サンドの本名はオロール・デュパンであり、ルイ十六世の遠縁にあたる貴族の父とパリのしがない商人の娘だった母との間で嫡子として生まれた。この出自のせいか、貴族の娘として育ちながら、凡俗な民衆に心をよせて生きることができたのだろう。
父モーリスは進歩を支持し、旧体制(アンシャン・レジーム)を見切り、有能な軍人でありながら芸術家だったという。だが、四歳の幼子のとき落馬事故でなくなったために、オロールには輝かしい幻のような記憶しかないらしい。
母ソフィーはやっと読み書きができるだけだったが、美しくて陽気だった。だが、父の母つまりオロールの祖母は深い教養を備えた啓蒙期の女性で、孫娘に読書、会話、音楽、優雅さを教えようとした。
彼女は、祖母を亡くした翌年、十八歳のとき、九歳年上の男爵と結婚したが、たちまち幻滅を感じたという。思いやりのない男であり、狩猟と馬と犬だけが好きで、読書も音楽も会話も愛さない粗野な男だった。息子が生まれても、陰うつなばかりで、伴侶と理解し合えないまま、彼女はパリに出て、何人もの愛人ができたという。
一八三二年、二十八歳のとき文学活動を始め、最初の小説でジョルジュ・サンドと名のったのである。この時代、離婚はありえなかったので、やがて合法的な別居が成立し、祖母から相続した故郷ノアンの実家と子どもたちの親権を持つことになったという。この経験のせいで、彼女は結婚制度に反対するとともに、女性たちの民法上の平等のために闘った。
作家として世に出てからのサンドの活躍は、目をみはるものがある。おびただしい書簡のために、その交友関係は華々しいばかりだ。なによりも愛の交流であり、彼女にとっては「束縛されない愛」が大切であった。だからといって、彼女は男性の気を引こうとする女性ではまったくなかった。多くは男性を愛したというが、ときには女性も愛したらしい。さらに、友情はサンドの人生のなかで愛以上に大きな位置を占めていた。
名高い人物をあげるだけでも、作曲家リスト、文豪バルザック、大作家フローベール、さらにはイタリアの政治家マッツィーニなど枚挙のいとまがない。なかでも熱烈な恋情の浮名があったロマン派詩人ミュッセや作曲家ショパンなど目もくらむほどである。
ドストエフスキーはサンドの熱烈な読者であり、プルースト文学の始まりはサンドの小説にあるともいう。本書の後半はサンドの主要作品の紹介があり、彼女の全貌が明らかになるのだから、人類史の新しいページが開かれたかのようである。
ALL REVIEWSをフォローする