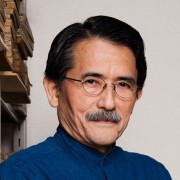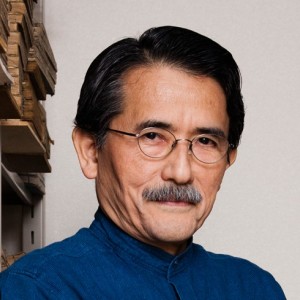書評
『幕末明治 女百話』(岩波書店)
昔の健脚
中里介山の超長編小説『大菩薩峠』に、七兵衛という盗賊が出てくる。この盗賊がまだ十一、二の子供の頃、夜半から夜明けまでのわずかな時間に、青梅宿から八王子までの往復十二里を速足に往来したと書いてある。もちろん小説だから、誇張してそのように書いてあるのであろうけれど、普通私どもが歩いたとしたら、十二里四十八キロというのは優に一日の道のりである。
しかし、最近、あれこれの書物を渉猟しているうちに、昔の人は恐ろしいほどの健脚だったことを知り、この七兵衛の速足とて、もしかしたら現実にあり得たかもしれないと考えるようになった。
篠田鉱造という人の著した『幕末明治女百話』という面白い本があるのだが、そこにこんなことが書かれている。
「昔の女は八十八ヶ所の、お大師さん参りが一番楽しみで・・・その頃のお詣りは、一日十二里と極っていました」
この八十八ヶ所のお大師さんというのは、江戸中期宝暦時代に定められた江戸とその近郊併せて八十八ヶ所の霊場を巡る、一種の巡礼詣でである。
こういうお参りというものは、信心半分娯楽半分で、倅に嫁でも来たら、家のなかのあれこれはもう若い者に譲って、町内の年配の男女が大勢集うて、ともかく賑やかにお喋りしながらせっせと歩いたのだそうである。
そうすると、女の足でも結構この一日十二里という長道がさまで苦労もなく歩けたというのだが、それにしても十二里といえば大変な長距離である。
一時間に四キロとして、およそ十二時間、相当な速度で歩きづめに歩かなくてはこの距離はいかれない。
で、そういうお参りには、樫の歯の日和下駄を履いて歩いたものだというが、その樫の歯が一日でペシャンコにすり減ったというのだからただ事でない。
しかも、この一日がかりのピクニックを終えて帰ると、胸がすっきりとして、頭がすーっと気持ち良くなり、すなわちここにお大師さんの御利益が実感できたというわけである。
今の人間は全体ヤワになってしまって、一日に十二里四十八キロなんて距離は、よほど強壮な若者でもなければ踏破出来ないだろうと思われる。
現に、私が大学一年の夏の、元気横溢の頃、新潟の直江津から出発して、糸魚川を経て姫川沿いに南下し、葛葉峠越えに信州信濃大町まで一週間の徒歩旅行をしたことがあるが、一日に十二里などは足が痛んでとても歩けなかった。せいぜいその半分くらいではなかったろうか。
ただし、こういう霊場参りの道筋には、お接待と言って、お茶やら飯やら、あるいはお菓子やらを布施してくれるところがあちこちに設けてあったらしい。
今も、四国のお遍路道や、長州の海辺の村々には、こうした風習がなお残っているところもあるが、幕末まで遡れば将軍お膝元の江戸でさえ、そんな牧歌的なことが行なわれていたのである。なんだかのんびりと懐かしい話しである。
【下巻】
初出メディア
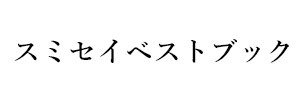
スミセイベストブック 2004年1月号
ALL REVIEWSをフォローする