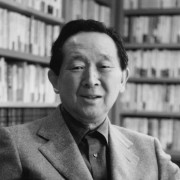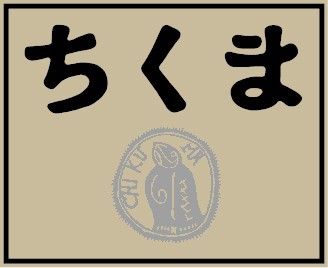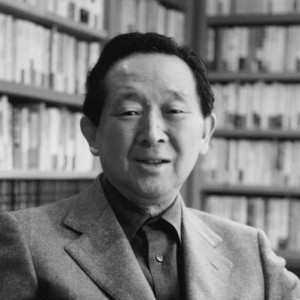書評
『自らを欺かず―泡鳴と清子の愛』(筑摩書房)
ヨーロッパには伝統的に伝記という文学のジャンルがある。しかし我が国の近代には、調査報告としての〝伝記〟死者を悼むオマージュとしての〝伝記〟はあっても、文学的作品としての伝記の流れは明治以後森森鷗外から中村真一郎に至る極めて細い流れとして存在しているだけであった。
尾形明子のこの本は、そうした中にあっての貴重な達成ということが出来よう。
もし晩年、心の優しい画学生遠藤達之助に出会わなかったら、遠藤清子の生涯は不幸なものであった。しかしこのことは彼女と岩野泡鳴の結婚の価値を低めるものでは決してない。清子の「肉体関係の拒否」と、「それまでの恋人との交際」を条件にした同棲生活からはじまった泡鳴と彼女の愛は、自分との、そして泡鳴との烈しい葛藤の連続であった。そして実はこのことは二人の結婚生活が輝かしいものであったことをも証明するかのようである。彼女には、妻の座を得ないままに男に身を委せることは、男と女の関係が性をはさんで支配者と被支配者になってしまうのではないかという恐怖があった。
この彼女の気持は忠実にその頃の社会の状態を反映していたといってもいいだろう。明治維新が日本社会の古い要素をそのままにして富国強兵に向ったのは周知の事柄であるが、日露戦争の勝利は、わが国の近代国家としての立場を一歩進めることによって、社会内の矛盾をも人々の意識の前面に押し出したのであった。遠藤清子はその矛盾を一身に引受けて生きた〝時代の女〟であった。
泡鳴との確執に悩んで、「理智の判断をすてて(中略)恋に身を投げ出さう」と思っても「甘えることを『醜業婦の行為』とし屈辱と思う」清子にそれは出来なかった。
ここには理智と感性を対立物と考えている当時の風潮がそのまま現れている。一方、相手の泡鳴は作家としてしたたかな認識力を持っていた。乃木将軍夫妻の天皇への殉死を「かうなつて来ては、お芝居同様、寧ろ滑稽だ」と日記に書き「『馬鹿な奴だ』という気がした」という感想を述べた志賀直哉と同じ批評精神を示している。しかし、こうした精神の構造は決して女性に対する男の感性への自己点検には至らなかった。それは彼が一緒に小舟に乗っていた平塚らいてうを誤って池に落してしまった時、とんちんかんに謝って、「女といへば着物としか考へないものか」と、らいてうに批評されてしまうような本質を持っていた。
清子との結婚後も少しも変らないそんな泡鳴の前に青鞜社社員の蒲原英枝が現われる。彼女のことを清子と比較して、
と書く尾形明子の観察は鋭い。やがて清子と別れることを決めた泡鳴は『青鞜』への過剰なまでの批判とも似通うすさまじい泡鳴叩きに苦しめられる。この現象を、マスメディアは当時から軽薄だった、といった一般論に解消させずに、
と著者は分析する。ここには明治末期という時代を見ている社会批評の目がある。
こうした著者の歴史認識と社会認識に支えられ、かつ登場人物への愛情の通っている筆写に抱かれて、この伝記は一級の文学作品になっている。
それにしても、この遠藤清子が苦しみつつ生きた時代と、敗戦によって国家の構造が変ったはずの今日と、私たちの社会はどれほどの前進があったのだろう。この著作は一級の重厚な伝記であることによって、鋭い疑問を現代社会にも投げかけているのである。
尾形明子のこの本は、そうした中にあっての貴重な達成ということが出来よう。
もし晩年、心の優しい画学生遠藤達之助に出会わなかったら、遠藤清子の生涯は不幸なものであった。しかしこのことは彼女と岩野泡鳴の結婚の価値を低めるものでは決してない。清子の「肉体関係の拒否」と、「それまでの恋人との交際」を条件にした同棲生活からはじまった泡鳴と彼女の愛は、自分との、そして泡鳴との烈しい葛藤の連続であった。そして実はこのことは二人の結婚生活が輝かしいものであったことをも証明するかのようである。彼女には、妻の座を得ないままに男に身を委せることは、男と女の関係が性をはさんで支配者と被支配者になってしまうのではないかという恐怖があった。
この彼女の気持は忠実にその頃の社会の状態を反映していたといってもいいだろう。明治維新が日本社会の古い要素をそのままにして富国強兵に向ったのは周知の事柄であるが、日露戦争の勝利は、わが国の近代国家としての立場を一歩進めることによって、社会内の矛盾をも人々の意識の前面に押し出したのであった。遠藤清子はその矛盾を一身に引受けて生きた〝時代の女〟であった。
泡鳴との確執に悩んで、「理智の判断をすてて(中略)恋に身を投げ出さう」と思っても「甘えることを『醜業婦の行為』とし屈辱と思う」清子にそれは出来なかった。
ここには理智と感性を対立物と考えている当時の風潮がそのまま現れている。一方、相手の泡鳴は作家としてしたたかな認識力を持っていた。乃木将軍夫妻の天皇への殉死を「かうなつて来ては、お芝居同様、寧ろ滑稽だ」と日記に書き「『馬鹿な奴だ』という気がした」という感想を述べた志賀直哉と同じ批評精神を示している。しかし、こうした精神の構造は決して女性に対する男の感性への自己点検には至らなかった。それは彼が一緒に小舟に乗っていた平塚らいてうを誤って池に落してしまった時、とんちんかんに謝って、「女といへば着物としか考へないものか」と、らいてうに批評されてしまうような本質を持っていた。
清子との結婚後も少しも変らないそんな泡鳴の前に青鞜社社員の蒲原英枝が現われる。彼女のことを清子と比較して、
知的ではあってもふくらみのない直線的な清子の文章にくらべてはるかに肉体を思わせる文章であり、その意味でまだ幼いながら泡鳴に近い。
と書く尾形明子の観察は鋭い。やがて清子と別れることを決めた泡鳴は『青鞜』への過剰なまでの批判とも似通うすさまじい泡鳴叩きに苦しめられる。この現象を、マスメディアは当時から軽薄だった、といった一般論に解消させずに、
この期、風俗紊乱による発禁処分の急増と合わせ、国家が、文学による国体の侵蝕を怖れ出したことと無縁ではないだろう。
と著者は分析する。ここには明治末期という時代を見ている社会批評の目がある。
こうした著者の歴史認識と社会認識に支えられ、かつ登場人物への愛情の通っている筆写に抱かれて、この伝記は一級の文学作品になっている。
それにしても、この遠藤清子が苦しみつつ生きた時代と、敗戦によって国家の構造が変ったはずの今日と、私たちの社会はどれほどの前進があったのだろう。この著作は一級の重厚な伝記であることによって、鋭い疑問を現代社会にも投げかけているのである。
ちくま 2001年5月
筑摩書房のPR誌です。注目の新刊の書評に加え、豪華執筆陣によるエッセイ、小説、漫画などを掲載。
最新号の目次ならびに定期購読のご案内はこちら。
ALL REVIEWSをフォローする