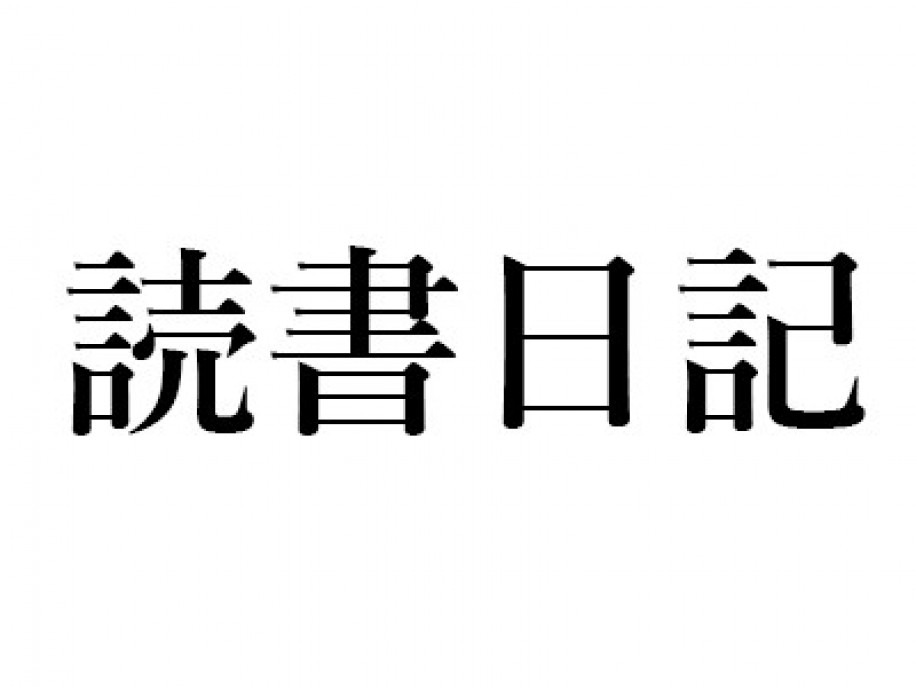書評
『アトランティスのこころ』(新潮社)
五つの作品が収められたこの大きなひとつの物語の中には、スティーヴン・キング作品のテーマと魅力のすべてがある。少年時代の終焉、それに伴う喪失と再生の物語。善と悪の相克。なぜ、どこで、どうやって、悪は生じるのかという問いかけ。理想と幻滅。輝きと翳(かげ)り。暴力。そして恐怖。恐怖を抱えて生きていくことの苦痛。ここには、キング作品のすべてがあるのだ。
なかでもっとも長い物語が、十一歳の少年ボビーのひと夏の経験を描いた「黄色いコートの下衆男たち」だ。親友のサリー・ジョンやキャロルと海に行く時に更衣室代の五セントすら出し渋る怒りっぽい母親と、狭いアパートメントで暮らしているボビー。ある日、彼は上の階に越してきたテッドという老人と知り合う。本好きのボビーは博識で読書家のテッドに惹かれ、しばしば老人の部屋を訪れるのだが、母親はそれを快く思っていない。テッドはボビーに頼む。「町で起きていることによく目をこらしておくれ」と。ペット探しの貼り紙や、石蹴り遊びの格子の横に描き添えられた謎めいた記号等。それらはすべて、自分を追っている「下衆男たち(ロウ・メン)」による暗号なのだ、とテッドは説明する。はじめのうちは妄想だと思っていたボビーだが――。
『スタンド・バイ・ミー』を想起させる物語に、『シャイニング』や『デッド・ゾーン』を彷彿させるエピソードと〈暗黒の塔〉シリーズの設定を盛り込みながら、キングはストーリーテラーとしての技量を存分に発揮する。父親のいないボビーがテッドに抱く尊敬の念や深い愛情。初めての恋、初めてのキス。野球。大人の本の世界への扉を開く一冊の本との出会い……。誕生日に自転車をもらえなくたって、母親から存分な愛をそそいでもらえなくたって、その輝きと喜びは決して色褪せることのない十一歳の夏。誰もが経験したあの夏の日々を、キングは色彩や匂いまでもが伝わってくるような活き活きとした語り口で再現してくれる。だからこそ、終盤でボビーが直面しなくてはならない喪失や幻滅の物語もまた、リアルな痛みを伴って読み手の心に突き刺さるのだ。
泥沼化するヴェトナム戦争を背景に、トランプゲームに夢中になっている大学生たちの姿をピートという青年の視点で描いた「アトランティスのハーツ」は、キングの半ば自伝的なパートになっている。ここでピートの恋人という形で顔を見せるのが、「黄色いコート――」でボビーと初めてのキスを体験したキャロル。自分たちの力で世界を善の側に取り戻すことが出来ると信じていた世代(ピート曰く「アトランティス人」)の希望と挫折を通奏低音に響かせながらも、しかし、一方でキングは悪というものがどれほど簡単に生起し、高邁な理想だっていずれは腐臭を発する、というつらい現実にもしっかり目を向けている。
「盲のウィリー」と「なぜぼくらはヴェトナムにいるのか」で描かれているのは、ヴェトナム戦争に従軍した側の物語だ。人から正気を奪わずにはいなかった戦争の現実とその後遺症。「黄色いコート――」と「アトランティス――」で顔を見せた脇役たちが登場し、革命闘争の最前線にいたキャロルの挫折の経緯についてもここで知ることができる。でも、戦争がテーマだからといってリアリズムに終わらないのが、我らが時代の物語王の王たるゆえんだ。これから読む喜びを削ぐ怖れがあるので詳述はしないけれど、二作品それぞれに寓話の雰囲気をまとわせたり、阿鼻叫喚の幻想的なクライマックスを用意したりと語り口に仕掛けがこらされており、ここでも巻を措く能(あた)わずのキング節は健在なのである。
最後の物語が「天国のような夜が降ってくる」。ここで、読者は懐かしい人物と再会できる。そう、ボビー。そして、彼もまた大切な人との再会を果たす。“アトランティス人”世代の子供時代から、ヴェトナム戦争を背景にした青春時代、その痛みを抱えながら老いのとば口に立つ現在までを描いたこの連作集が、ここでひとつの物語として結び合わされるのだ。それも、あのテッドの魔法によって。「魔法のほんの小さなひとかけらが残って、あとあとまでついてまわる……そんなこともあるんじゃないかな」。ボビーは、「人は成長して、子ども時代の自分をあとに捨てていく」と語る再会の人の諦観をたしなめる。その魔法のほんの小さなひとかけらこそが“アトランティスのこころ”――キングがタイトルに込めた想いが伝わる見事な最終章ではないだろうか。
この長い物語の中では、たくさんの悪が生まれる。たくさんの幻滅や挫折や悲嘆も。にもかかわらず読み終えた後、わたしたちは希望を抱かずにはいられない。無垢なるものは汚され、美しい何かは損なわれてゆくこの世界にあっても、人は魔法の小さなかけらを信じることができるのだ、と。それが、キングの全魅力を投入した傑作が読者に手渡してくれる“こころ”なのだと思う。
【下巻】
【文庫版】
【この書評が収録されている書籍】
なかでもっとも長い物語が、十一歳の少年ボビーのひと夏の経験を描いた「黄色いコートの下衆男たち」だ。親友のサリー・ジョンやキャロルと海に行く時に更衣室代の五セントすら出し渋る怒りっぽい母親と、狭いアパートメントで暮らしているボビー。ある日、彼は上の階に越してきたテッドという老人と知り合う。本好きのボビーは博識で読書家のテッドに惹かれ、しばしば老人の部屋を訪れるのだが、母親はそれを快く思っていない。テッドはボビーに頼む。「町で起きていることによく目をこらしておくれ」と。ペット探しの貼り紙や、石蹴り遊びの格子の横に描き添えられた謎めいた記号等。それらはすべて、自分を追っている「下衆男たち(ロウ・メン)」による暗号なのだ、とテッドは説明する。はじめのうちは妄想だと思っていたボビーだが――。
『スタンド・バイ・ミー』を想起させる物語に、『シャイニング』や『デッド・ゾーン』を彷彿させるエピソードと〈暗黒の塔〉シリーズの設定を盛り込みながら、キングはストーリーテラーとしての技量を存分に発揮する。父親のいないボビーがテッドに抱く尊敬の念や深い愛情。初めての恋、初めてのキス。野球。大人の本の世界への扉を開く一冊の本との出会い……。誕生日に自転車をもらえなくたって、母親から存分な愛をそそいでもらえなくたって、その輝きと喜びは決して色褪せることのない十一歳の夏。誰もが経験したあの夏の日々を、キングは色彩や匂いまでもが伝わってくるような活き活きとした語り口で再現してくれる。だからこそ、終盤でボビーが直面しなくてはならない喪失や幻滅の物語もまた、リアルな痛みを伴って読み手の心に突き刺さるのだ。
泥沼化するヴェトナム戦争を背景に、トランプゲームに夢中になっている大学生たちの姿をピートという青年の視点で描いた「アトランティスのハーツ」は、キングの半ば自伝的なパートになっている。ここでピートの恋人という形で顔を見せるのが、「黄色いコート――」でボビーと初めてのキスを体験したキャロル。自分たちの力で世界を善の側に取り戻すことが出来ると信じていた世代(ピート曰く「アトランティス人」)の希望と挫折を通奏低音に響かせながらも、しかし、一方でキングは悪というものがどれほど簡単に生起し、高邁な理想だっていずれは腐臭を発する、というつらい現実にもしっかり目を向けている。
「盲のウィリー」と「なぜぼくらはヴェトナムにいるのか」で描かれているのは、ヴェトナム戦争に従軍した側の物語だ。人から正気を奪わずにはいなかった戦争の現実とその後遺症。「黄色いコート――」と「アトランティス――」で顔を見せた脇役たちが登場し、革命闘争の最前線にいたキャロルの挫折の経緯についてもここで知ることができる。でも、戦争がテーマだからといってリアリズムに終わらないのが、我らが時代の物語王の王たるゆえんだ。これから読む喜びを削ぐ怖れがあるので詳述はしないけれど、二作品それぞれに寓話の雰囲気をまとわせたり、阿鼻叫喚の幻想的なクライマックスを用意したりと語り口に仕掛けがこらされており、ここでも巻を措く能(あた)わずのキング節は健在なのである。
最後の物語が「天国のような夜が降ってくる」。ここで、読者は懐かしい人物と再会できる。そう、ボビー。そして、彼もまた大切な人との再会を果たす。“アトランティス人”世代の子供時代から、ヴェトナム戦争を背景にした青春時代、その痛みを抱えながら老いのとば口に立つ現在までを描いたこの連作集が、ここでひとつの物語として結び合わされるのだ。それも、あのテッドの魔法によって。「魔法のほんの小さなひとかけらが残って、あとあとまでついてまわる……そんなこともあるんじゃないかな」。ボビーは、「人は成長して、子ども時代の自分をあとに捨てていく」と語る再会の人の諦観をたしなめる。その魔法のほんの小さなひとかけらこそが“アトランティスのこころ”――キングがタイトルに込めた想いが伝わる見事な最終章ではないだろうか。
この長い物語の中では、たくさんの悪が生まれる。たくさんの幻滅や挫折や悲嘆も。にもかかわらず読み終えた後、わたしたちは希望を抱かずにはいられない。無垢なるものは汚され、美しい何かは損なわれてゆくこの世界にあっても、人は魔法の小さなかけらを信じることができるのだ、と。それが、キングの全魅力を投入した傑作が読者に手渡してくれる“こころ”なのだと思う。
【下巻】
【文庫版】
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする