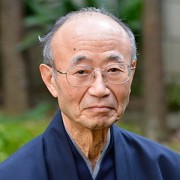書評
『外法と愛法の中世』(平凡社)
院政期に呪術が演じた役割
日本で「古代」が流行るのはきまってロマンチックなルーツ探しであるが、それと並んで「中世」の人気もなかなかのものだ。一向に衰える気配がない。それは何故かといえば、おそらく価値観の多様化という特徴が、現代と中世を共通のイメージで直結させるためではないだろうか。まず言葉や文字のような表現手段が中世になって一挙に多様化している。公家と武家が入り乱れて権力の多重化が生じている。寺と神社の区分が薄れ、神道と仏教・職業と芸能などの境界がはてしなく融解していった。総じて異質なものとの同化、価値あるものの異化が錯綜して進行し、セックス崇拝、呪物信仰がせきを切ったように社会の表面に流出した時代だ。
本書はそうした中世の面白さを、国文学者の眼で三つの観点からとらえようとした仕事である。第一が女神論。古代的な「竜女(りゅうにょ)」が中世の説話・伝承の世界でどのような変容をとげたかを吉祥天や弁才天との関連でとりあげ、親鸞が夢に見たという「玉女(ぎょくにょ)」とも結びつけて掘りさげている。第二は、仏教によって伝えられた仏舎利がしだいに呪的な秘宝として転生していく道筋を明らかにし、それがとりわけ院政期における重要な王権シンボルとみなされていく謎を解いている。第三が「ダ枳尼天(だきにてん)法」といわれる、狐妖(こよう)を駆使する密教秘法の分析と解読という仕事である。この秘法には異端の呪術(外法(げほう))と欲望達成の呪術(愛法)という二面が含まれているが、それが院政期の政治の舞台裏でどのような陰微な役割を演じたかを克明に論じている。
新資料に大胆にメスを入れ、先学の研究にも遠慮会釈のない批判を加えているところが気持ちよい。著者にはすでに「悪女論」という話題の作品があるが、本書でもフェミニズムの立場がつらぬかれている。ただ、それがときに紋切り型の表現になっていて、もう一つ奥深いところにとどかないのが惜しまれる。
ALL REVIEWSをフォローする