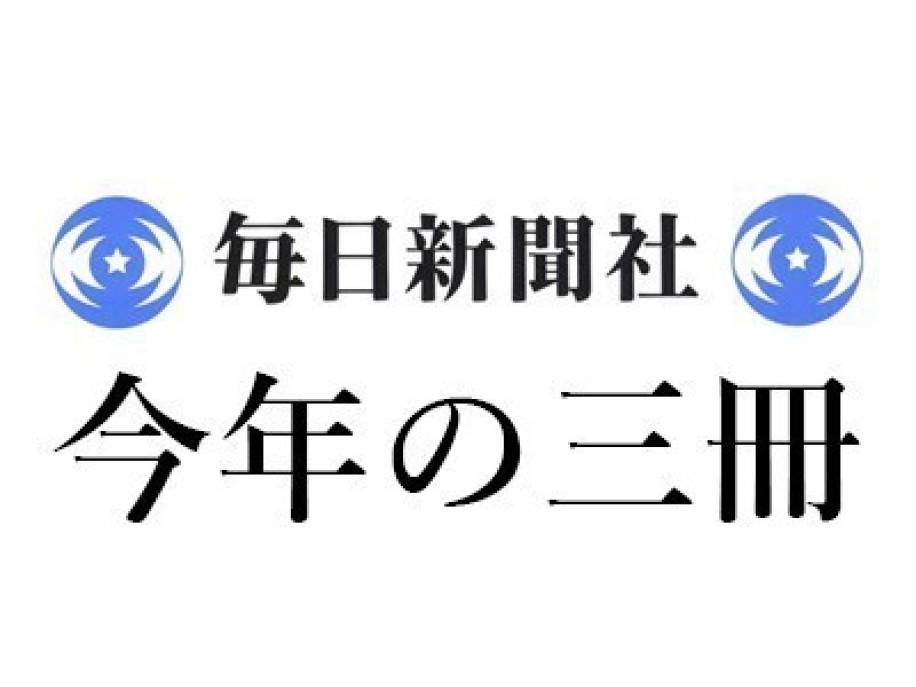書評
『わたしの東京物語』(丸善)
はずれた場所にいる誇り
東京はだんだん西にのびてゆく。昔は隅田川も東京の真ん中を流れていたのに、東がさびれ、西が栄えて、大川と愛称された隅田川はかなり都心をはずれてしまった。幸田露伴、永井荷風、谷崎潤一郎、芥川龍之介、岡本かの子らはこの川を美しく描いたのに、いまや川沿いに住み、またそこを描く作家はじつに少ない。
増田みず子さんくらいだろうか。
子供がどうやって生まれてくるか知らなかったころ、子供は橋の下に落ちていて、おとなたちがそのなかからかわいい子を選んで拾ってきて育てるのだ、というストーリーがわたしの頭のなかにあった。(『わたしの東京物語』丸善ブックス)
川べりに育った人でないとピンと来ない話だろう。私も母に不忍池の畔で拾ったのだとよくおどかされた。増田さんは関屋の王子製紙の社宅に育ったという。
千住という町は広い。広く平らである。どこまでいっても小さな低層の木造家屋がみっしりと詰まっていて、道が狭く、殺風景だ。どの家も古くて傾きかけているようだ。瓦屋根の向こうには煙突がたくさん突き立っている。太いのや細いのや、高いのや低いの、どの煙突からも煙がもくもくと出ている。
下町といっても浅草のような門前町ではない。日本橋のような老舗もない。神楽坂のような色町でもない。谷中のような寺町でもない。とくべつ冴えないどんよりした灰色の町。だがまぎれもなく庶民の町である。昭和三十年ころには、まだまだ空地があり、川を汽船が通り、庭にはイチジクが実り、よそのおねえさんが嫁にいく姿が見えた。この本を読むと、そんな殺風景な町の中にも、ふつうの人間の喜びや悲しみがふんだんに息づいていることがいとおしい。現実には声高で派手な町より、そうした物いわぬ地味な町の方が圧倒的に多く、そこにこそ大半の人々が暮らしているのだ。
私がお目にかかった増田さんも、ご自身でおっしゃるように、「はじっこのほうでひっそりしている方」だった。まるで育った町のように。控え目とかつつましいというのは当たらない。「はずれた場所にいる誇り」に満ちた、位置の確かさといえる。
いつも見て育った隅田川のことがひたひたと語られる。旅に出てまたきらめく東京に帰ればほっとし、都会の川が汚れているのはありのままの姿だからかまわないと思い、でもそんな汚れた水にもなお暮らしつづける生物に心を寄せる。懐古趣味に引きずられたくないと思う一方、変遷の様子を忘れたくないとも念ずる。そのたゆたいがまた水のようで、町っ子の私は共感に身をゆだねて読んだ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする