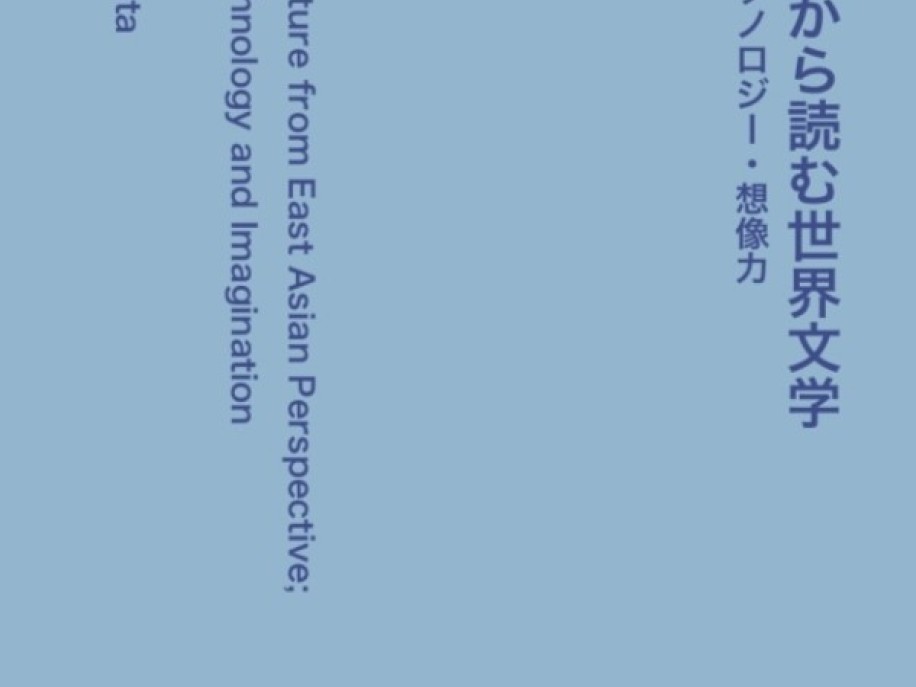書評
『突囲表演』(河出書房新社)
不倫もお国柄や書き手の資質が違えば、まるでその表情を変えてしまうわけで、たとえば一世を風靡した渡辺淳一の『失楽園』と、現代中国文学の巨匠・残雪の『突囲表演』。両者の間に横たわるさまざまなレベルの溝を考えると、この国の住人であるわたしはガックリを超えていっそ痛快ですらある。五香街(ウーシャンチェ)で起こったX女史とQ男史の姦通事件の謎をめぐって住人が侃々諤々(かんかんがくがく)の大騒ぎ。その醜態を描くことで人間性に内在する卑小と尊大、社会による個人の圧殺の構図を暴いて戦慄的な傑作が、この『突囲表演』という小説なのだ。
昼間は夫と煎り豆屋を営み、夜は鏡を使った巫術(ふじゅつ)を操り、周囲と同調せず、我が道を突き進む強烈な個性の持ち主X女史。虚像を看破し、ものの姿をありのままに捉えることができるX女史の心眼ともいうべき第三の眼に魅入られて、真面目な小役人で良き夫を演じてきた自分の殻から飛び出し、徐々に共同体から逸脱していくQ男史。その二人の交情が、自分たちの倫理観や思想に合致しないという理由で彼らを監視し、言動を非難し、嫉妬のあまり人格を貶(おとし)めることで、自らの心の安寧とする街の人々。ここにはその時々の思想や政治を盲信することで(たとえば文化大革命)、隣人同士糾弾しあい、財産や人権を略奪しあってきた近代中国が抱える深い闇が描かれている。
本書は、幼時にそうした理不尽にさらされた経験から一貫して批判精神旺盛な人生を送っている作家・残雪の自伝的要素が強い作品と目されている。が、そうした暗いリアルな心情から生まれたにもかかわらず、『突囲表演』の全体的な印象は賑やかかつユーモラスかつ幻想的。南米文学のマジックリアリズムを思わせる豊饒がここにはある。セックスのことを「業余文化生活」と言い換えたり、昨日までの生け贄(にえ)を今日は指導者に持ち上げたりといった明らかな自己欺瞞にも一切反省することなく、今を生き延びていく中国人民のたくましさと議論好きの貌(かお)、大陸レベルに壮大なユーモア感覚が横溢して、ポリフォニック(多声的)な味わいと驚愕に満ちた作品になっているのだ。
『失楽園』レベルの通俗的な物語性と言語性に囲まれている日本人にとって、この饒舌な文章が最初は馴染みにくいかもしれない。けれど一旦、語りのペースにハマれたらしめたもの。奇想天外な物語に没入させられること必定だ。わたしたちの国では二十年に一冊出るかどうか、そのくらいの傑作小説なんである。
【この書評が収録されている書籍】
昼間は夫と煎り豆屋を営み、夜は鏡を使った巫術(ふじゅつ)を操り、周囲と同調せず、我が道を突き進む強烈な個性の持ち主X女史。虚像を看破し、ものの姿をありのままに捉えることができるX女史の心眼ともいうべき第三の眼に魅入られて、真面目な小役人で良き夫を演じてきた自分の殻から飛び出し、徐々に共同体から逸脱していくQ男史。その二人の交情が、自分たちの倫理観や思想に合致しないという理由で彼らを監視し、言動を非難し、嫉妬のあまり人格を貶(おとし)めることで、自らの心の安寧とする街の人々。ここにはその時々の思想や政治を盲信することで(たとえば文化大革命)、隣人同士糾弾しあい、財産や人権を略奪しあってきた近代中国が抱える深い闇が描かれている。
本書は、幼時にそうした理不尽にさらされた経験から一貫して批判精神旺盛な人生を送っている作家・残雪の自伝的要素が強い作品と目されている。が、そうした暗いリアルな心情から生まれたにもかかわらず、『突囲表演』の全体的な印象は賑やかかつユーモラスかつ幻想的。南米文学のマジックリアリズムを思わせる豊饒がここにはある。セックスのことを「業余文化生活」と言い換えたり、昨日までの生け贄(にえ)を今日は指導者に持ち上げたりといった明らかな自己欺瞞にも一切反省することなく、今を生き延びていく中国人民のたくましさと議論好きの貌(かお)、大陸レベルに壮大なユーモア感覚が横溢して、ポリフォニック(多声的)な味わいと驚愕に満ちた作品になっているのだ。
『失楽園』レベルの通俗的な物語性と言語性に囲まれている日本人にとって、この饒舌な文章が最初は馴染みにくいかもしれない。けれど一旦、語りのペースにハマれたらしめたもの。奇想天外な物語に没入させられること必定だ。わたしたちの国では二十年に一冊出るかどうか、そのくらいの傑作小説なんである。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
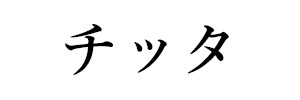
チッタ(終刊) 1997年12月号
ALL REVIEWSをフォローする