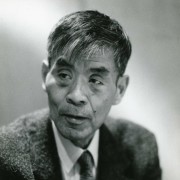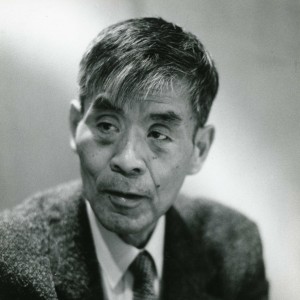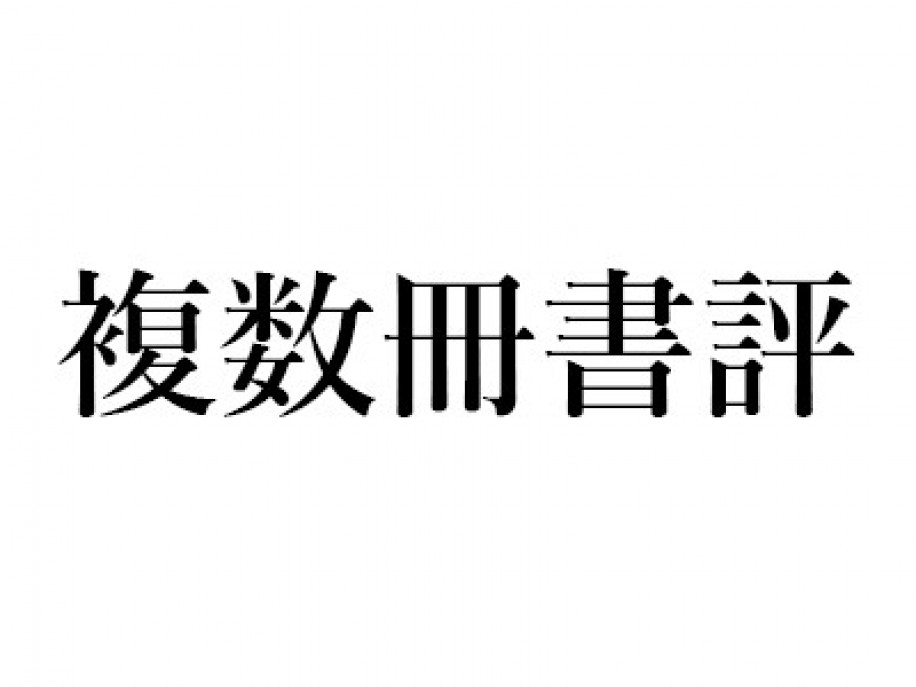書評
『家族解散』(新潮社)
『家族解散』を読んだ
この作品は糸井重里の文学作品としては、村上春樹との共作『夢であいましょう』についで第二作ということになりそうだ。でも、本格的な作品という意味では、はじめての作品だといえよう。二十ほどある小さな挿話を機械のように配置し、一つ一つの機械はまた、もっと小さな挿話から成立っている。それはさらに、数行ほどのコピーからできている。そう言えば、およそこの特異な作品の文体上の特徴は言い当てたことになりそうだ。もしもっと微細に文体の雰囲気まで伝えようとすればどうなるか。ひとつは「事物」にたいする描写の偏愛、もうひとつは、心臓の在り所を匿したい内密な、いくらかシニカルな眼差だといえそうだ。「ちゃぶ台」「マーマレードびん」「カナブン」「便所」など、ふつう小説では作者が歯牙にもかけないありふれた「事物」が、ほとんど各章を集約するコピーになるほど重要な役割をはたしている。作者は偏愛の眼差をこらして、こういったありふれた「事物」の描写にうち込んでいる。作者の特異な資質は、本来なら私小説的な情念と心境の作品になりそうな主題を描きながら、ほんとは「事物」が物を言い、そのあいだをぬいながら、ある一家に解散が宣言されるまでの家族各々の言動が描きだされるといった、超「事物」主義風の作品を作りあげている。一家の主人小倉文彦氏は、子供達を申分のない自由放任にゆだね、妻絹枝の衛生的だが面白味のない性格の支配する家のムードにも、つきつめた異議をはさまず、遠慮がちなことなかれの寛大さを発揮する。だがときには、毎日が無事であればどんな亭主でも子供でもいいとしかかんがえていない妻や、勝手な振舞いしかしない子供たちをみて、なぜこんな者のために、日銭を貢いで暮さなくてはいけないのかという危険な破滅的な思いを、まるで間歇泉のように心の中で噴出させている。そして、ヒロコちゃんという美容学校の生徒と、ひょんなことから知りあい、家族に内緒で面倒をみている。ある日文彦氏がヒロコちゃんのところから「ちゃぶ台」をもってきて、和風の食卓にしようと家族に強要したところから、小倉家崩壊の兆候が露出しはじめる。いいかえれば、家族機械が、ほんのすこしいつもと異なった回転音を響かせたときから、子供たちの小さな歯車も異常音を発しはじめ、しまいには「ヒマラヤ不動産」のおやじという夾雑物まではさまってきて不協和音を高め、形さえあればどんなガタガタでもいいからと必死に油をさす妻の努力も効力を失い、いわば暖昧で故障らしい故障もないように見えながら、文彦氏(という機械)によって家族に解散が宣せられてしまうまでの物語なのだ。
文彦氏が「ちゃぶ台」を運び込んだ日に、さっそく高校生の明彦は、煙草盆代りの「マーマレードびん」を「ちゃぶ台」のうえにどっかと置き、それまで内緒で吸ってきた煙草を公然とふかして家族解散の徴候の二番手を演じる。長女の明子は、はじめて自分を愛してくれる恋人を得、そのことで両親からたんにそつなく扱われていただけという幼児体験を想起させられ、奪いあうような心からの愛情か、それとも波立たない生活の幸福感を求めるべきかで、母絹枝とはじめて衝突してしまう。次女文枝は、クラスの子から鞄にそっと入れられたエロ本の処理に悩んでいるのを居候の「ヒマラヤ不動産」に見つけられ、アコーデオンカーテンで仕切られた居間の向う側にいる母に見透かされるのではないかと、気に病みはじめる。こんな家族のメンバー一人一人が、崩壊へいたる一見何でもない布石を否応なくむきだしてしまい、そこから機械の連動作用のように家族の破局のない破局までベルトを回すことになってゆくのだ。
わたしはこの作品を読みながら、すぐに横光利一の『機械』や、小島信夫の『抱擁家族』を思い出した。横光利一の『機械』が、心理の磁場で作動する登場人物たちそれぞれの歯車が必然的に噛みあいながら解体してゆく人間関係を描いており、小島信夫の『抱擁家族』が、家族相互の人間関係の齟齬が組み合わされて分解してゆく物語だとすれば、糸井重里の『家族解散』は、家庭のなかに日常置かれたり使われたりするつまらない日用品や、部屋にはっていたり、とび込んだりする虫たちや、作品の中で妻の絹枝がやるように掃きすてようとすればすぐにひとの眼から消えてしまうつまらない心の片隅の塵芥のような違和感を通じて、ひとつの家庭が解体してゆく姿を描き出している。横光利一の『機械』や小島信夫の『抱擁家族』と、糸井重里のこの作品をならべてみせると、純文学に慣れ、それだけが高級だとおもっている読者は、冗談じゃないとおもうかも知れない。だがわたしには、糸井重里のこの作品は、無意識のうちに、いや存在するのは冗談だけなんだと主張しているか、あるいは意識的につまらない「事物」の動きを描写することを通じ、卑小の外見を介して現在の家族の当面している普遍的な課題に肉薄しようとしているようにおもえてならない。
横光利一は昭和十年代のもっともすぐれた純文学の作家だ。そして小島信夫は、現代の純文学のもっともすぐれた作家のひとりであり、糸井重里は、現代のもっともすぐれたコピーライターだ。これがどんな意味をもち、どんな相互関係にあるかが、この対比にとても鮮やかに象徴されている。そして、現在では、重要なことはつまらない仮面をかぶって表象されるものだということを、読者の偏見にむかって問いかけているのかも知れない。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする