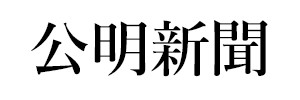書評
『専門知を再考する』(名古屋大学出版会)
『専門知を再考する』(H・コリンズ、R・エヴァンズ著)の周辺
科学と政治の関係の難しさ
今年はコロナの年と記憶されそうである。ロックダウンや緊急事態宣言による社会経済活動の抑制、マスクの常態化、感染の波状的拡大と、新型コロナウイルスは世界で猛威を振るっている。経済の落ち込みも甚だしい。この間、各種メディアを通じてさまざまな専門家の発言を聞かされてきた。政府も専門家を招集して対策を打ち出している。たしかにコロナウイルス対策を考えるには、専門家の助言が不可欠である。しかしここ数力月われわれが経験したことは、専門家の発言が必ずしも一致していないということであった。科学の専門知がなぜ対立するのだろうか。
イギリスの科学技術社会論の研究者の手になる本書は、この「専門知」を腑分けし、「誤りうる科学技術を科学技術として正当に扱う」にはどうするかを論じている。イギリスは、専門家による助言の扱いをめぐって大失敗した歴史を持つ。1980年代後半のBSE(いわゆる狂牛病)事件の際、専門家は人間への感染の可能性は低いと助言し、政府は安全を主張し続けたが、その後人間への感染が生じた。この事件の教訓は「政治の速さは、科学の合意形成の速さを上回る」、そして「問題に関する最適な専門家を選ぶことは容易ではない」ということだった。
科学は人類が手にする強力な知的ツールではあるが、コロナウイルスのような未知の現象を解明するにはそれなりの時間を必要とする。しかし具体的な政策決定に必要な時間はずっと短い。そうすると、科学者は科学的には不確実で意見が一致していない状態で助言を求められることになる。BSE事件の際にも、科学者は「現在の手持ちの材料から判断する限り」という但し書きをつけて、感染の可能性が低いと述べていたが、政治家はそれを無視したのだった。現実の科学は高校の理科とは異なり、いつも正解を手にしているわけではない。これは言い換えると、科学は、そして助言は間違える可能性があるということである。
さらに厄介なことに、コロナウイルスやBSEといった新奇で未知の現象に関して、最適な専門家をどうやって選ぶかが難問なのである。「本当に最適な」専門家を動員できているかどうかは誰にも分らない。結局のところ、例えば政府の委員会が、なるほど可能な限り検討して最適と思われる専門家から構成されているのだと社会が納得できるか否かという問題なのである。
ここに科学と政治の関係の難しさがある。政治は科学を活用するためには、科学の不確実性を理解し、専門家の選定に留意しなければならない。そしてこのような専門家が提示する「誤り得る」助言に政策決定の責任を押し付けるのではなく、科学以外の観点も考慮した総合的な判断を「政治の責任」で下すことが求められている。
[書き手]小林傳司(大阪大学名誉教授、科学哲学・科学技術論)
ALL REVIEWSをフォローする