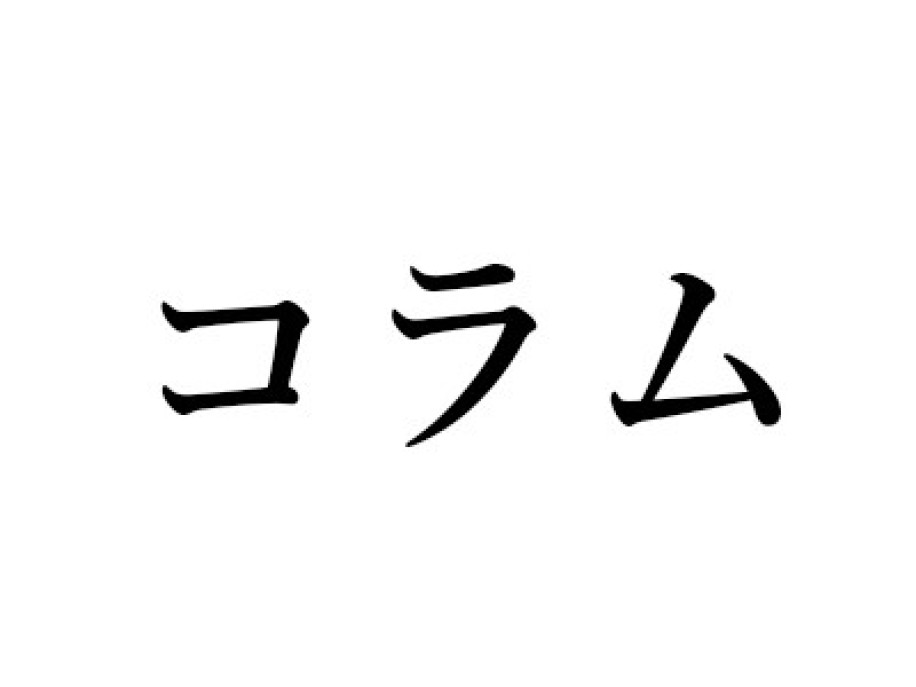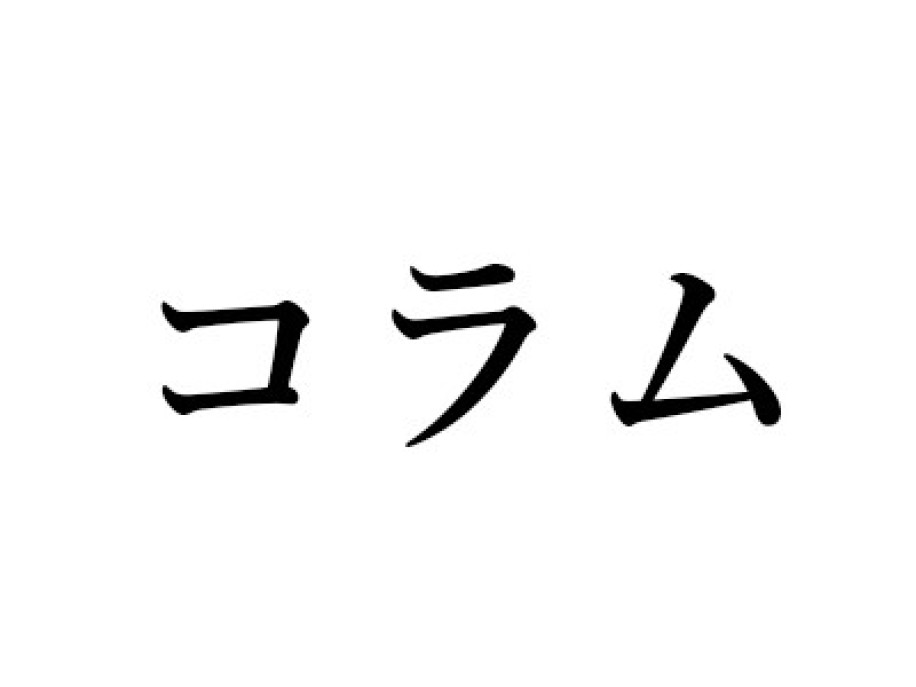書評
『玄鳥』(文藝春秋)
二度と帰らない「むかし」
藤沢周平の短篇「玄鳥」を読む。路(みち)という若い武家の奥方がいる。兄が夭逝して、彼女が婿をとった。この婿が武士官僚を絵に描いたような男で、路が小さい頃から燕が毎年やってきて門に巣をかけた、その巣を壊せという。城からの使者、上役がくぐることもある門にみっともない。路は逆らうことができない。
路には心の奥深く秘めたものがある。父は無外流の剣の達人で、死に臨んで彼が考案した極意を路に伝えた。路は剣をつかわない。だからこの極意伝授は言葉、口伝である。やさしい路の心に秘められた必殺の剣の極意が、いったいどのようなかたちで表に噴き出してくるか。ストーリーはスリリングに展開する。
ある時、一人の藩士が上役を斬り伏せ、自分の妻を刺殺して逐電する。藩は三人の討手(うって)を放つ。一人が曾根兵六という男。この男、路の兄の親友で、父の剣の秘蔵弟子だった。
噂が伝わる。討手は返り討ちにあい、敵を逃がしてしまった。一人は死に、一人は重傷、一人は無傷だったらしい、と。
路は、無傷だった男は曾根兵六に違いないと確信する。なぜか。少女の頃から兵六を知り、慕ってもいた路は、兵六の本質、粗忽を見抜いていた。父も一度は極意を授けようとしたが、決局兵六の粗忽に気付いて伝授はおこなわれなかった。粗忽、それを作者は、「奇妙な虚(うろ)の部分」と書く。
その言葉を裏書きするような事件が父の死後に起きた。兵六は命ぜられて、命を狙われているある武士の警護に立ったが、腹が空いて近くのそば屋で昼飯のそばを食っているすきに守るべき武士が殺されるという失態を犯す。警護すべき男の許可を得ていたとはいえ彼の弁明は許されず、減石処分を受ける。
きっと今回も一人だけ、何かの事情で現場にいなかった。つまり、兵六という男は人柄も良く、剽軽(ひょうきん)で、剣のつかい手ではあるが、肝心な時に不在、虚なのだ。兵六に藩の処分が下る。減石の上、大坂へ左遷。しかし左遷とは表向きで、大坂にむかう兵六に藩は討手を放つことになっている。それを夫から聞き及んだ路は、ついに時がきた、と旅支度をしている兵六をひそかにたずねる。
口伝が終わる。路の目が不意にうるむ。兵六がこの剣で危難を切り抜けられるかどうかはわからない。しかし、すべてが終わった。父、兄、妹、兵六、あの頃の家の屋敷を照らしていた日の光、吹きすぎる風の匂い、そして恋。路も妹も粗忽でおもしろい兵六のお嫁さんになりたかった。巣を壊された燕はもう来年はこない。すべてが終わり、変わって、二度と戻らない。
藤沢周平の時代小説には、長篇『蟬しぐれ』や『海鳴り』、その他の無数の短篇群にしても、まさにこの路のまなざし、こころざしに似たものが通底して鳴り響いている。えもいわれぬノスタルジー。それが藤沢周平の時代小説だ。この場合、時代とはむかしと同義だ。二度と帰らない、むかしという時と場所、人と物。むろん、描かれたむかしと、実際のむかしは何の関係もないことはいうまでもない。
サウダーデ(Saudade)という美しいポルトガル語がある。ノスタルジーに似ているが違う。この言葉は他国語には訳せないのだとポルトガル人の友人はいった。心象の中に、風景の中に誰か大切な人が、物がない。不在が、淋しさと憧れ、悲しみをかきたてる。と同時にそれが喜びともなる。えもいわれぬ虚の感情……。とすれば、兵六の粗忽こそ路の、読者のサウダーデをかきたてるものだ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする