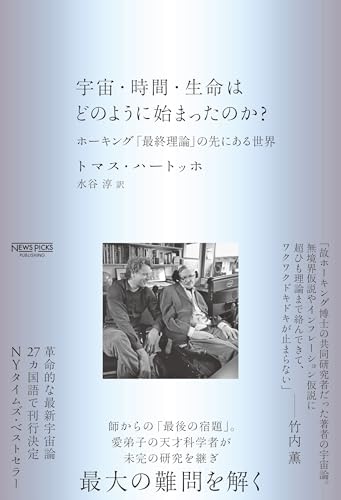書評
『「第二の不可能」を追え! ――理論物理学者、ありえない物質を求めてカムチャツカへ』(みすず書房)
不可能を可能にした30年
三五〇ページほどの本を読み終えパタンととじた時の爽快感は格別だった。研究はこうでなくっちゃ。どうしても知りたいことを三〇年以上かけて、しかも補助金なしでやり遂げたのだ。宇宙論が専門の著者は、確立した科学原理の一つに抜け道を見つけ新しいタイプの物質(準結晶)を作り出せるという画期的概念を生み、発表した。「ありえない!」。会場にR・ファインマンの声が響いた。彼は時に、「おお! ふつうは正しいとは思えない意外なことだ。よく知る価値があるぞ!」という意味でこの言葉を発する。不可能には「1+1イコール3」のように決してありえないことの他に、前提が必ずしも正しくないために不可能とされているものがある。事と次第によっては可能となる不可能だ。著者らが挑んだ結晶学の原理の一つに「原子の周期的な並びは対称性で分類でき、対称性の数は限られる」がある。タイル貼りでわかるように対称性は一、二、三、四、六回しかなく、五回と七回以上はありえない。著者はこの規則に異を唱えたのだ。「異なるまとまりが異なる間隔で繰り返される」ことがあるとして、これを「準結晶」と名付けたのである。著名な物性物理学者、材料科学者からは「数学的には可能かもしれないが、実在するには複雑すぎる」という否定的な反応ばかりが聞こえてきた。よくあることだ。
ところで、その頃若い科学者シェヒトマンが、アルミとマンガンの合金で一〇回対称性を持つ物質を作り出していた。数千年もの間不可能とされていたことが、同時に理論と実験で可能の世界に持ち込まれたのだ。科学の世界では時々ある。
しかも著者がセミナーを依頼した旧友に準結晶の話をしようとしたら、「面白いものを見せよう」と取り出したのがシェヒトマンの論文だったのだそうだ。まさに、小説より奇なる展開に、著者がどれほど驚いたか。その後、東北大学の蔡安邦(ツァイアンパン)らがアルミと銅と鉄から成る美しい正二十面体の準結晶をつくり、「とうとう、初めて明白に本物と言える正二十面体の準結晶が見つかった」と著者は記す。
ここでドラマは「天然の準結晶はあるか」と問う第二幕に入る。標本データを探し八年も成果が上がらないところへ、フィレンツェで「不整合結晶」を研究しているルカ・ビンディから協力申し出がある。そしてフィレンツェ博物館にあるカムチャツカ半島で採取したサンプル、カティアカイト(銅とアルミの結晶鉱物)が有力候補として浮かび上がった。画像解析センターの機械が唯一空いていた一月二日午前五時に見えてきたのは一〇回対称性。「自分たちが『第二の不可能』の瞬間に立ち会っているのだとわかっていた」。ただ押し黙ったままだったと著者は書く。『サイエンス』誌に投稿すると、案の定分野の大御所二人から「不可能」の声が出る。またもよくある話だ。
第三幕は思いがけない展開で、カムチャツカへサンプル探しに行く。キャンプの経験もない著者を隊長とする探検隊の日々は楽しい読み物だ。ここで自然界に準結晶は存在し、それは宇宙からの訪問者とわかる。ドラマは一巡し、著者の専門の宇宙へと戻ったのだ。
もう一度書く。研究はこうでなくっちゃ。
ALL REVIEWSをフォローする