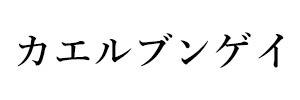書評
『ホワイト・ティース』(新潮社)
わたしもテレビ朝日で放映されてる「ほんパラ!関口堂書店」の店員になってみたい。近頃訳出あいなった『ナボコフ短篇全集Ⅰ・Ⅱ』(作品社)を取り上げて、ゲストの釈(由美子)ちゃんに「なんかぁすごぉくおもしろそーなのでぇよんでみたいでぇーす」と言わせてみたい。でもって翌日、全国の主要書店で一冊四千円近くするナボコフ本が売り切れ続出、なんて奇蹟を起こしてみたい。みたいよみたいよみたいよ、みたいよの一億光年倍だよっ(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆は2001年)。
「無理」
んなこたぁ、わかってるんである。ちょっと思ってみただけ。釈ちゃんが「この本はいいね」と云ったから「ほんパラ!」お薦め本を買うオレら――そんな五七調に収まる世相に、ちょっとひがんでみただけ。でも、活字の世界の書評家もいかんよね。たしかにテレビの影響力は凄まじいものがあるけど、釈ちゃんにすら「おもしろそー」と思ってもらえるような、わかりやすい書評を書かないオレらもいかんのよ。というわけで、今回は釈ちゃん的なる存在に向けて書いてみたいと思う。ゼイディー・スミス『ホワイト・ティース』for釈ちゃん、そんな感じ。
第二次世界大戦従軍中に知り合った、ロンドン下町育ちのアーチーとバングラデシュ出身の敬虔なイスラム教徒サマード。『ホワイト・ティース』は、人種も違えば主義主張も異なるこの二人の奇妙な友情を軸に、十九世紀から二十世紀末に至る時空間を自在に行き交う小説なのね。釈ちゃんはジョン・アーヴィングって知ってる? 『ガープの世界』や『ホテル・ニューハンプシャー』とかって映画の原作を書いた人で、「次はどうなんの?」のワクワクでページをめくる指が止まらないくらい楽しいストーリーを、笑えたり、胸がほんわか温かくなったりできるエピソードもてんこ盛りに描くすごく人気の高い作家なわけ。で、そのアーヴィングの小説をワールドワイドに拡大したスケールと、猥雑さと、ユーモアを想像してみてね。『ホワイト・ティース』はそのくらい面白い小説なんだってば。
アーチーとジャマイカ出身の妻クララ、娘アイリー。サマードと同郷の妻アルサナ、双子の兄弟マジドにミラト。物語の前半は、主にこの二家族を軸に展開していくのね。アーチーとサマードの戦争体験。エホバの証人の信者である母親に育てられたクララの半生。アーチーとクララ、サマードとアルサナ、それぞれの出会いと結婚。我が子を真っ当なイスラム教徒に育て上げたいというサマードの願いでバングラデシュに帰されてしまうマジド。この前半部は、つまり人物紹介だよね。読者にしっかり感情移入してもらうため、作者が丁寧かつ面白おかしく登場人物のキャラクターを立体化しようとしてるわけ。優柔不断なアーチー、高学歴なのにロンドンではウェイターをするしかない不公平に怒りを覚え、息子たちが西欧文化に染まることを苦々しく思うプライド高きサマード。この二人を筆頭に、全キャラクターがどれほど活き活き描かれていることか。あ、言い忘れたけど、ゼイディー・スミスってこの作品を書いた時、まだ二十四歳だったんだよ。これがデビュー作なんだよ。マジやばくない?
後半に入ると、そこにチャルフェン一家っていうユダヤ系インテリ家族まで絡んでくんの。科学に対する正しい理解と率直な物言いが信条の“チャルフェニズム”を名乗る、つまり、自分たち一族がいかに優秀かを周囲に誇示してやまない嫌味な家族なんだけど、ここにアイリーとミラトが取り込まれていっちゃうのね。アイリーは教養の匂いに惹かれて、かたや美しい不良少年に成長したミラトはお金目当てに。ミラトがチャルフェン家に入り浸るもんだから、息子を取られたみたいで面白くないアルサナ。あまつさえ、正しきアッラーの道を歩ませるつもりで故郷に帰したマジドでさえ、ネズミを使った遺伝子工学の実験に夢中なチャルフェン家の主人マーカスと、文通を通じて師弟関係を結んじゃう。やがてミラトは過激なイスラム原理主義グループの一員と化してしまい――。そうした紹介しきれないくらいたくさんのエピソードが、終章へと賑々しくなだれ込んでいく構成になってるわけ。
いろんな国から移民を迎えて、カオス(混沌)の都と化したロンドン。人種的にも文化的にも政治的にもハイブリッド(雑種)な世代が生まれていく過程で生じる熱気と混乱を描いたっていう読み方もありだけど、この作品は他にも色々考えさせる作りになっていて、そこがわたしはすごいと思ってんだよね。たとえば、最初のほうでアーヴィングの名前を出したけど、十九世紀の物語文学が好きな人ならディケンズを思い浮かべるだろうし、現代文学が好きな人ならトマス・ピンチョンの名前を挙げると思うのね。ピンチョンは文学にエントロピー理論を取り上げた作家なんだけど、「分離(秩序)の状態が次第に混合(無秩序)という結果に変化し、終局的に宇宙は熱死に至る」っていうエントロピーの増大に関する仮説は、まさにハイブリッドの熱量増大を伝えるこの小説にも当てはまるから。
けど、そういうこと何にも思い浮かばなくたって、この小説は十二分に楽しめるはずなの。饒舌にしてユーモラスな語り口と、奇想天外なエピソードを二世紀分堪能しているうちに、今まで説明してきたみたいなテーマらしきものは、アーヴィングやディケンズやピンチョンやエントロピーなんて知らなくても、するするっと頭の中に入ってきちゃう。それが、この作品の素晴らしいとこ。難しくなんかなくて、ただただ面白い物語なのに、そこには重大なことが書かれている、――そういう小説、世界にはいっぱいあるんだよー。だから釈ちゃん、ネズミとチーズ探したり、金持ち父さんと一緒に貧乏父さんをバカにしたり、天然ボケ演じたりするのはやめて、小説を読もうよ読もうよ読もうよ、読もうよの一億光年倍だよっ!
【下巻】
【文庫】
【この書評が収録されている書籍】
「無理」
んなこたぁ、わかってるんである。ちょっと思ってみただけ。釈ちゃんが「この本はいいね」と云ったから「ほんパラ!」お薦め本を買うオレら――そんな五七調に収まる世相に、ちょっとひがんでみただけ。でも、活字の世界の書評家もいかんよね。たしかにテレビの影響力は凄まじいものがあるけど、釈ちゃんにすら「おもしろそー」と思ってもらえるような、わかりやすい書評を書かないオレらもいかんのよ。というわけで、今回は釈ちゃん的なる存在に向けて書いてみたいと思う。ゼイディー・スミス『ホワイト・ティース』for釈ちゃん、そんな感じ。
第二次世界大戦従軍中に知り合った、ロンドン下町育ちのアーチーとバングラデシュ出身の敬虔なイスラム教徒サマード。『ホワイト・ティース』は、人種も違えば主義主張も異なるこの二人の奇妙な友情を軸に、十九世紀から二十世紀末に至る時空間を自在に行き交う小説なのね。釈ちゃんはジョン・アーヴィングって知ってる? 『ガープの世界』や『ホテル・ニューハンプシャー』とかって映画の原作を書いた人で、「次はどうなんの?」のワクワクでページをめくる指が止まらないくらい楽しいストーリーを、笑えたり、胸がほんわか温かくなったりできるエピソードもてんこ盛りに描くすごく人気の高い作家なわけ。で、そのアーヴィングの小説をワールドワイドに拡大したスケールと、猥雑さと、ユーモアを想像してみてね。『ホワイト・ティース』はそのくらい面白い小説なんだってば。
アーチーとジャマイカ出身の妻クララ、娘アイリー。サマードと同郷の妻アルサナ、双子の兄弟マジドにミラト。物語の前半は、主にこの二家族を軸に展開していくのね。アーチーとサマードの戦争体験。エホバの証人の信者である母親に育てられたクララの半生。アーチーとクララ、サマードとアルサナ、それぞれの出会いと結婚。我が子を真っ当なイスラム教徒に育て上げたいというサマードの願いでバングラデシュに帰されてしまうマジド。この前半部は、つまり人物紹介だよね。読者にしっかり感情移入してもらうため、作者が丁寧かつ面白おかしく登場人物のキャラクターを立体化しようとしてるわけ。優柔不断なアーチー、高学歴なのにロンドンではウェイターをするしかない不公平に怒りを覚え、息子たちが西欧文化に染まることを苦々しく思うプライド高きサマード。この二人を筆頭に、全キャラクターがどれほど活き活き描かれていることか。あ、言い忘れたけど、ゼイディー・スミスってこの作品を書いた時、まだ二十四歳だったんだよ。これがデビュー作なんだよ。マジやばくない?
後半に入ると、そこにチャルフェン一家っていうユダヤ系インテリ家族まで絡んでくんの。科学に対する正しい理解と率直な物言いが信条の“チャルフェニズム”を名乗る、つまり、自分たち一族がいかに優秀かを周囲に誇示してやまない嫌味な家族なんだけど、ここにアイリーとミラトが取り込まれていっちゃうのね。アイリーは教養の匂いに惹かれて、かたや美しい不良少年に成長したミラトはお金目当てに。ミラトがチャルフェン家に入り浸るもんだから、息子を取られたみたいで面白くないアルサナ。あまつさえ、正しきアッラーの道を歩ませるつもりで故郷に帰したマジドでさえ、ネズミを使った遺伝子工学の実験に夢中なチャルフェン家の主人マーカスと、文通を通じて師弟関係を結んじゃう。やがてミラトは過激なイスラム原理主義グループの一員と化してしまい――。そうした紹介しきれないくらいたくさんのエピソードが、終章へと賑々しくなだれ込んでいく構成になってるわけ。
いろんな国から移民を迎えて、カオス(混沌)の都と化したロンドン。人種的にも文化的にも政治的にもハイブリッド(雑種)な世代が生まれていく過程で生じる熱気と混乱を描いたっていう読み方もありだけど、この作品は他にも色々考えさせる作りになっていて、そこがわたしはすごいと思ってんだよね。たとえば、最初のほうでアーヴィングの名前を出したけど、十九世紀の物語文学が好きな人ならディケンズを思い浮かべるだろうし、現代文学が好きな人ならトマス・ピンチョンの名前を挙げると思うのね。ピンチョンは文学にエントロピー理論を取り上げた作家なんだけど、「分離(秩序)の状態が次第に混合(無秩序)という結果に変化し、終局的に宇宙は熱死に至る」っていうエントロピーの増大に関する仮説は、まさにハイブリッドの熱量増大を伝えるこの小説にも当てはまるから。
けど、そういうこと何にも思い浮かばなくたって、この小説は十二分に楽しめるはずなの。饒舌にしてユーモラスな語り口と、奇想天外なエピソードを二世紀分堪能しているうちに、今まで説明してきたみたいなテーマらしきものは、アーヴィングやディケンズやピンチョンやエントロピーなんて知らなくても、するするっと頭の中に入ってきちゃう。それが、この作品の素晴らしいとこ。難しくなんかなくて、ただただ面白い物語なのに、そこには重大なことが書かれている、――そういう小説、世界にはいっぱいあるんだよー。だから釈ちゃん、ネズミとチーズ探したり、金持ち父さんと一緒に貧乏父さんをバカにしたり、天然ボケ演じたりするのはやめて、小説を読もうよ読もうよ読もうよ、読もうよの一億光年倍だよっ!
【下巻】
【文庫】
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする