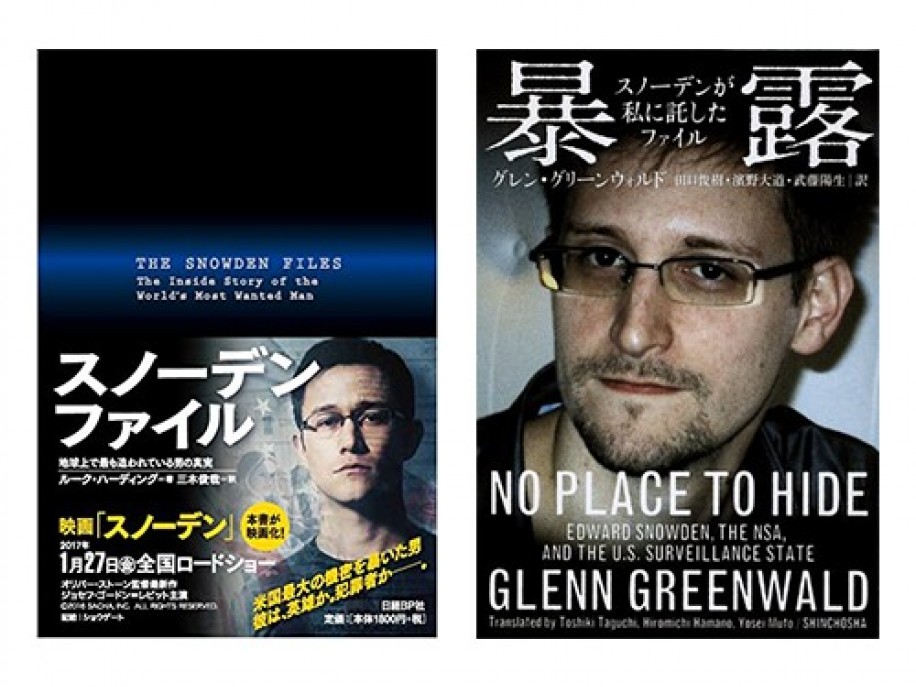書評
『石を放つとき』(二見書房)
年を重ねた探偵が生む厚み
ローレンス・ブロックがマットことマシュウ・スカダーというアル中の私立探偵を主人公にしたシリーズ第一作、『過去からの弔鐘』を刊行したのは、一九七六年のことである。以来、四十五年の歳月が流れた。邦訳紹介されたのが八七年だから、日本語でスカダーと出会った読者も、すでに三十数年の年を重ねている。ニューヨーク警察の刑事だったスカダーは、強盗殺人犯を追跡中、自分の発した流れ弾でひとりの少女の命が奪われるという痛ましい出来事をきっかけに妻子と別れ、職を辞した。酒におぼれる無免許の私立探偵は定型のうちである。スカダーの一人称に特別な響きがあったのは、アルコール依存症の自主治療の会に顔を出して過去を悔い、わずかでも前を向こうと怯えながら弱さをさらけ出し、さらけ出すことで弱さを認める強さを得ようとしていたからだ。八八年に邦訳された『八百万の死にざま』は、弱者への眼差しと、自己崩壊寸前で持ちこたえているスカダー自身の脆さへの信頼の深さにおいて輝いていた。
もっとも、全十七作を数えるシリーズのうち、酒に溺れた私立探偵が登場するのは最初の五作のみである。スカダーがスカダーとして真の一人称を獲得するのは、依存症を克服し、飲んでいた時代を振り返るようになったあとのことなのだ。過去の回想と語りの現在が交錯し、物語に距離と厚みが生まれる。その厚みを安定的に更新していくには、主人公が年を重ねていかなければならない。
スカダーの年齢が作者とおなじ五十五歳に設定されたのは九四年の『死者の長い列』からだが、すでに馴染みの登場人物である元娼婦のエレインと再婚したことでも読者を驚かせた。
本書は、最新の中篇「石を放つとき」にスカダーが登場する十一の短篇を集めた『夜と音楽と』をあわせたもので、『聖なる酒場の挽歌』(八六年)につながる名篇「夜明けの光の中に」はもとより、ただ愚直に人を訪ねて話を聞くことで受け身のまま事件を解決に導く「バッグ・レディの死」や、『慈悲深い死』以後、徐々に存在感を増していった元ギャングのミック・バルーが店をたたみ、身を固めるという単行本未収録の二篇をふくめ、スカダーの魅力と半生を一望できる構成になっている。
表題作は、当然「老い」を大きな主題としている。スカダーは八十歳、エレインも六十歳を超えている。家族のような関係を結んでいたかつての少年TJもいつしか四十を過ぎ、刑事時代の知己も引退して生の機密情報も入ってこない。当たり前のように記されたグーグルという言葉が、頁(ページ)のうえで奇妙に浮いている。
膝の痛みで歩くのが遅くなり、簡潔な話し方もできない「老人」となっても、スカダーはエレインの若い友人のために、ある意味、命がけで動く。隠し事なしの、何でも話せて円満に見える老夫婦の今後がどうなるのか。ひとつひとつ、大切にしていた人生の駒が失われ、ふたりの結びつきを保ち、子のない彼らを「マミー」「ダディ」と呼んでさらに強くしてくれる存在をどこかで欲している心の隙を埋めるかのような、思いがけなくも明るい結末は、『伝道の書』の一節を念頭に置いているとはいえ、どこか切なくもある。
ALL REVIEWSをフォローする