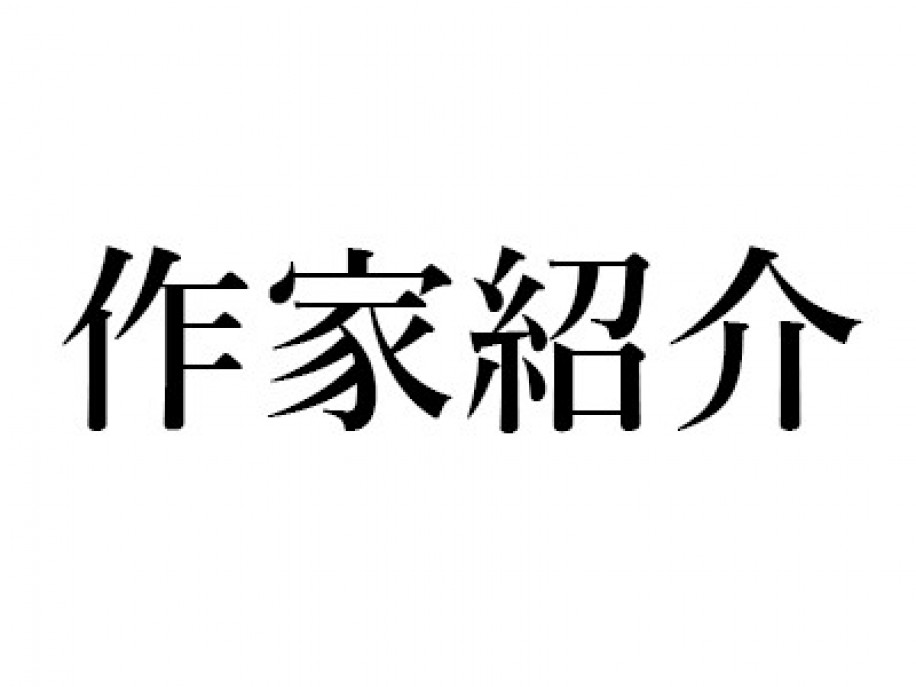書評
『中村とうよう 音楽評論家の時代』(二見書房)
ポップ音楽を文化史に
中村とうよう氏は一九六〇年代から二〇一一年に七十九歳で自殺するまで、二世代以上にわたる外国音楽ファンの道しるべとなった唯一無二の音楽評論家だろう。僕自身も、ラテンアメリカの音楽について、音楽のとらえ方について、彼からすべてを教えてもらったと思っている。しかし、音楽評論家は雑誌記事やレコードの解説、コンサートやレコードの企画など、書籍に残らない活動が多いので、あとになるとその活躍の全貌はわかりにくくなる。本書は彼の弟子にあたる著者が、「とうようさん」の仕事を丹念に追いかけて整理した音楽的評伝である。中村とうようは、ラテン音楽からジャズ、ブルース、フォーク、ロック、黒人音楽、そしてアフリカなどの「ワールド・ミュージック」へ、アジアの音楽へと、次々に関心の焦点を移しながら、ポップ音楽を文化史の重要な一部分としてとらえる見方を確立し、各国の音楽の間の関係性を重視する特異な視点を作りあげた。また、純粋なものよりも混淆(こんこう)したもの、俗受けする猥雑(わいざつ)さのあるものにこそ価値がある、という独自の評価軸に行きつく道筋もよくわかる。
中村とうようという生身の人間の部分にあまり踏みこまなかった点は僕には残念だったが、関係したレコードのリストなどの資料的側面が重視されているのはいかにもコレクター的な細心さだ。彼があそこまで多様な音楽についてどのようにして知識を得ていたのかという長年の謎は、本書でも解明されなかったが、それは武蔵野美術大学に寄贈された蔵書等のコレクションを見よ、ということだ。その詳細な目録は著者によって別に公刊されている。また、本書の内容を補完する副聴CD『とうようズ・チョイス・スペシャル』も同時に出た。中村とうようが最後に愛した少し悲しい楽曲集である。
何の道しるべもなく、多くの人が一曲単位で音楽を消費していくデジタル配信の状況に対する危機感が副題にはこめられているだろう。
ALL REVIEWSをフォローする