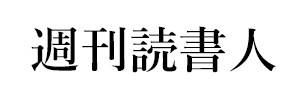書評
『徳川家康』(吉川弘文館)
家康の行動を居所を前提に時系列で描く
「はしがき」によると、本書は約四二〇〇点にもおよぶ徳川家康の発給文書の博捜をふまえて、彼の生涯を淡々と描こうとした評伝である、という。叙述の特徴は、家康の行動をその居所を前提として時系列に描くという、著者年来の方法論を駆使したことにある。評者は、きわめて納得のゆく「ベーシック家康伝」との読後感を得るとともに、今後ふまえるべきいくつかの論点を学んだので、ここにその一部をご紹介することにしたい。著者は、家康の人生を大きく四期に区分する。それをもとに章分けするのであるが、中心となったのが、後半生にあたる第三期(本能寺の変のあと、・・・秀吉に臣従し、豊臣政権下にあった時期、四二~五七歳、第三・第四章)と、第四期(秀吉の死を契機に「天下人」をめざし、・・・その死にいたるまでの時期、~七五歳、第五~第八章)である。
従来の研究は、神君家康がいかにして天下を取ったのか、という政治史研究が主流だった。著者は、逸話さえ混入した所謂「徳川史観」から脱するために、徹頭徹尾、実証主義を貫くのであるが、二つの画期を設定して天下人への道程を描いている。その第一が家康の秀吉への臣従であり、その第二がその逆というべき豊臣秀頼の家康への臣従である。
第一の画期は、天正十二年(一五八四)の小牧・長久手の戦いから同十三年の秀吉の関白任官、そして同十四年の家康上洛による豊臣大名化である。それを前提とする第二の画期は、慶長五年(一六〇〇)の関ヶ原の戦いから同八年の家康の将軍任官、そして同十六年の秀頼の二条城訪問による豊臣から徳川への政権交代だった。
著者は、家康の臣従は他の豊臣大名とは異なり、秀吉の妹朝日姫の輿入れを伴うものであり、「完全に屈服させることはできなかった」、「一方的な和睦ではなかった」ことに特徴があったとする。それゆえに、関ヶ原の戦いの後、ただ一人の大老という優位な立場をもとに、伏見城において諸大名に対する領地替え、公家・門跡に対する知行割りをおこない、着実に権力基盤を固めえたのだった。
さらに、慶長十七・十八両年の寺社や公家に対する法度の強制、そして大坂の陣による豊臣家滅亡を経て、徳川体制が確立したとみる。
なお、近年において関ヶ原の戦いに関する研究は活況を呈しているが、全体の六分の一にあたる約七〇頁もの紙幅を割いて戦前・戦後について詳述し、史実の確定に努めている。また、関ヶ原の戦いから大坂の陣までの政治体制を、徳川・豊臣両氏による「二重公儀体制」とする笠谷和比古氏の見解を一蹴し、家康主導の政治史を叙述している。
「おわりに」で、著者は一次史料だけでは人間家康を描ききれなかった、と方法論の限界について告白する。確かに、家康像の骨格はきわめてクリヤーになったが、血肉をつける方法は後進の課題とするべきであろう。それでも、本書が伝統の人物叢書通巻三〇〇冊目を飾るにふさわしい大著であることに異論の余地はあるまい。
[書き手] 藤田 達生(ふじた たつお・三重大学教育学部教授)
ALL REVIEWSをフォローする