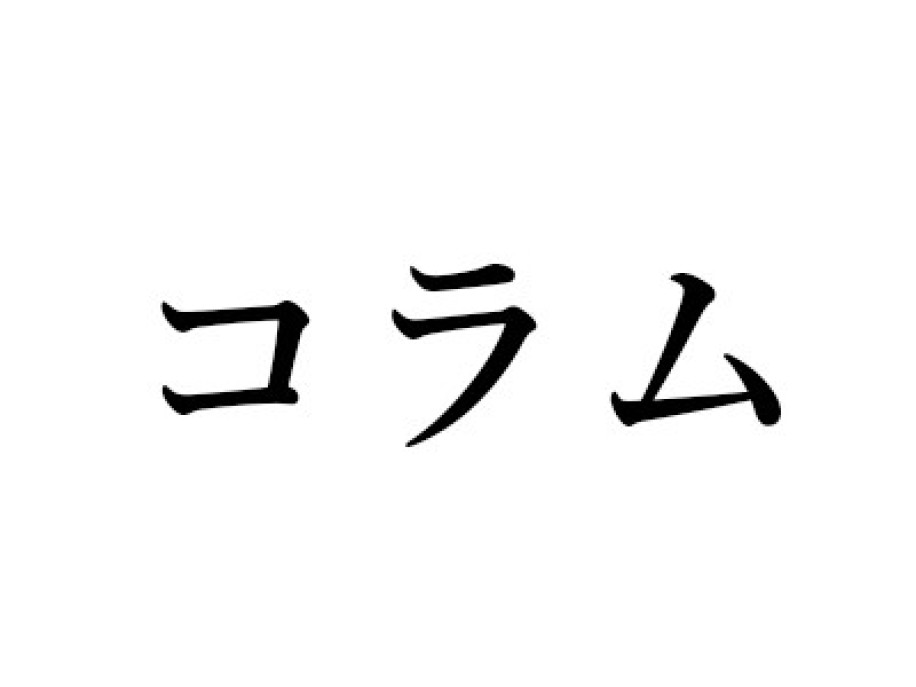前書き
『歯車にならないためのレッスン』(青土社)
オウム真理教を内側から描き出した『A』『A2』から、日本のマスコミと政治の宿痾を浮き彫りにした『i-新聞記者ドキュメント-』にいたるまで、観る者の視点そのものを揺さぶるような作品を発表しつづけてきた映画監督・作家の森達也さん。しかし、森さんを制作・執筆へと駆り立てているのはジャーナリスティックな精神でも、不正を許さないという「大義」でもなかったといいます。では、そこにあったものとは何なのか——。4月26日刊行の『歯車にならないためのレッスン』の「まえがき」を先行公開します。
もちろん、時事評論家ではない。あくまでも「のようなポジション」だ。でもそうしたコメントを求められることは少なくない。
これまでのキャリアでオウム真理教や死刑制度や下山事件などを扱ってきたこともあって、時おり肩書としてジャーナリスト的な形容をされることがある。その場にいるならばあわてて否定できるけれど、印刷物やネットなどでは事後に知るだけだ。もう修正できない。だから後ろめたい。
僕はジャーナリストではない。むしろ真逆な位置にいる。だって書くときも撮るときも、優先するのは常に自分の主観だ。ジャーナリストならば客観性や中立性や公正性に配慮しなければならない。もちろん、完璧な客観性や中立性や公正性を達成することなどありえないが、可能なかぎり留意しなければならないと思っている。さらにジャーナリズムにおいては大義も必要だ。不正を許さないこと。公益に奉仕すること。弱者の声を届けること。
これまで書いてきた書籍や撮ってきた映画やテレビ・ドキュメンタリーなどには、前述したジャーナリズムの大義と、かなりの面で被る作品は少なくない。でもそれは、これまでのテーマの多くが社会的な問題と重なったからであって、大義が先にあったわけではない。
ずっと優先してきたのは、徹底して自分の興味や好奇心だ。撮ったり書いたりしているとき、客観性や中立性や公正性などについて考えることはほとんどない。いや、ほとんどじゃない。まったくない。これでジャーナリストなど名乗れるはずがない。社会派でもない。たまたま興味を持ったテーマが、社会的で政治的だっただけなのだ。
***
だから考える。いつからこういうことになったのか。僕にとっての原点はオウム真理教の映画『A』だ。映画祭や上映会などでは上映後に、「なぜオウムを撮ろうと思ったのか」「なぜオウムの施設に一人で入ることができたのか」などとよく質問されるけれど、そもそもオウムを撮った理由は、この時期に僕がテレビディレクターだったからだ。
地下鉄サリン事件が発生してからほぼ1年、メディアはオウムバブルの時期だった。テレビは早朝から夜中までオウムの特番だらけ。オウム関連以外の企画はほぼ通らない。だからドキュメンタリーの被写体にオウムの現役信者を選択した。オウム真理教に対しては、どちらかといえば強い興味などなかったはずだ。つまり消去法。あくまでも仕事の一環だ。強い意志や使命感など欠片もない。
一人で撮り続けた理由も、この作品は危険だと判断したテレビ局上層部から撮影中止を言い渡されて撮影クルーに発注できなくなったからだ。自分でこの手法を選択したわけではない。ならばなぜ、所属していた制作会社から解雇されたのに撮影を続けたのかと質問されるけれど、事態を甘く見ていたからと答えるしかない。まさかクビにはならないだろうと思っていたのだ。つまり組織の論理を軽視していた。
メディアの誰もがオウム真理教の信者たちのドキュメンタリーを発想しなかった時期に撮った理由をひとつだけ無理やりに挙げれば、僕の鈍さに由来していると言うしかない。当時の日本社会全般が抱いていたオウムに対する嫌悪や憎悪を、僕は他人ごとのように眺めていた。共有していなかった。これに尽きる。
僕は鈍い。だから組織の中で優秀な歯車になれない。テレビの仕事を始める前、いくつかの会社を転々とした時期があった。もしも当時の上司や同僚たちに訊けば、あきれるほどに使えない社員だったと誰もが口を揃えると思う。
これは余談になるけれど、公開後に『A』が一部で評価されて香港やベルリンやバンクーバーなどいくつもの映画祭に招待されながら、この評価はフロックなんだと僕は自分に言い聞かせていた。才能や実力ではない。だから続編などありえない。あっというまに馬脚を現す。映画はこれ1本にしておくべきだ。ずっとそう思っていた。結果として『A2』を撮ってしまったけれど、あのときの不安と躊躇いは今もはっきり覚えている。
とにかくどこからどう考えても、僕の資質はジャーナリスティックな要素とはほど遠い。政権批判とかメディア批評とか、できることならやめたい。それに見合うだけの取材力もないし、知識や教養もない。要するに分不相応なのだ。
ただし分不相応ではあっても、今の社会や政治について物申すことはしていいはずだ。特に『A2』発表以降から現在に至るまで、執筆を生活の糧にしてきた期間は長い。そして書くためには、さすがに最低限の勉強をしなくてはならない。読書だけではなく実際に多くの場に足を運び、多くの人に話を聞いた。それは僕にとって、書いたり撮ったりするうえで大きな糧になっていることは間違いない。
***
ポーランドにあるアウシュビッツ=ビルケナウ強制収容所に行ったとき、最後の所長だったルドルフ・ヘスが居住していた家に案内された。子煩悩で家族思いのヘスは、ドイツから妻と五人の子どもたちを呼びよせて、鉄条網の外に小さな家を建てて家庭菜園を作り、一家仲良く暮らしていた。
もちろん家はもう解体されている。でも敷地は残っていた。ふと目を上げて、僕は衝撃を受けた。その家からユダヤ人の遺体を焼いていた焼却所までは、歩いて数分の距離だったのだ。仲睦まじく暮らす家族たちの目に、煙突から立ち昇る黒い煙はどのように映ったのだろう。処刑台に送られる直前に、ヘスは以下の言葉を残している。
ヘスと同じくナチス親衛隊員でユダヤ人移送の最高責任者だったアドルフ・アイヒマンも、家族思いで愛妻家だった。彼が裁かれる法廷を傍聴したハンナ・アーレントは「凡庸な悪」という言葉を想起して、その著書『エルサレムのアイヒマン』において、アイヒマンの罪は多くの人を殺したことではなくナチスという組織の歯車になったことだ、との論を展開している。
ヘスはユダヤ人虐殺現場の歯車のひとつで、アイヒマンはユダヤ人を虐殺現場へ輸送する歯車のひとつだった。2人だけではない。ナチス宣伝相のゲッベルスや副総統だったゲーリング、金髪の野獣と言われたゲシュタポ長官ラインハルト・ハイドリヒ、親衛隊のトップにいたハインリヒ・ヒムラー、ホロコーストに加担した彼らナチス高官たちも、組織の歯車として多くの人を殺害し続けた。ナチスだけではない。誰もがアメリカに敗けることを予想しながら無謀な戦争を始めた大日本帝国。総計で数千万人が犠牲になったといわれるスターリンの大粛清と中国の文化大革命。ルワンダやクメール・ルージュの大虐殺、同国人8万人を殺したといわれる韓国の4・3事件。まだまだいくらでもある。日本における朝鮮人虐殺、連合赤軍やオウム真理教の事件、あるいは安倍政権以降ずっと続いている官僚機構の文書捏造問題なども含めて、組織共同体が大きな過ちを犯すとき、歯車になった人たちが実直に駆動していることは共通している。
チャップリンはその監督作『モダン・タイムス』で、この時期にフォード自動車が採用していたベルトコンベア式工程への批判を込めて、あの有名な歯車に巻き込まれるシーンを呈示した。組織は個を幸せにしないとのメッセージだ。
でも機械は歯車がなければ動かない。もしもその組織を構成する人たちの多くが、『A』を撮り始めたときの僕のように、場を見ることが苦手で空気に対して鈍い歯車だったとしたら、その組織は早晩に不具合を起こして大混乱しながら機能停止するはずだ。
だから歯車は重要だ。でもこのとき、何か変だなとかちょっと違うかもと思ったとき、それを言葉にしたり動きで示したりすることを忘れない個でありたい。違和感を表明できる歯車であってほしい。それだけで集団の暴走や過ちは、大きく回避できると思うのだ。
***
ここに掲載されているのは、基本的には2017年から2022年までの期間に、いくつかの雑誌や新聞に寄稿した原稿のアンソロジーだ。一貫したテーマはない。でも時代性は確実に息づいている。そしてそれは、少なくとも同時代にこの国に暮らしている人たちならば、共有できるテーマのはずだ。
ただし多くの人と共有できるテーマではあっても、「鈍い」からこそ、時おり多くの人と僕は視点がずれる。つまりコントロールに難がある速球型のピッチャーだ。たまたまストライクゾーンに入れば威力を発揮できるけれど、逸れるときはすさまじい。
そう思いながら読んでほしい。どれがストライクなのかボールなのか、それは(あらためて書くまでもないけれど)読む人一人ひとり(つまりあなた)の判断だ。
[書き手]森 達也(映画監督・作家)
群れ、馴れ、そして個を失ったこの国で生きるために
時おり思う。いつから自分は時事評論家のようなポジションになってしまったのか。もちろん、時事評論家ではない。あくまでも「のようなポジション」だ。でもそうしたコメントを求められることは少なくない。
これまでのキャリアでオウム真理教や死刑制度や下山事件などを扱ってきたこともあって、時おり肩書としてジャーナリスト的な形容をされることがある。その場にいるならばあわてて否定できるけれど、印刷物やネットなどでは事後に知るだけだ。もう修正できない。だから後ろめたい。
僕はジャーナリストではない。むしろ真逆な位置にいる。だって書くときも撮るときも、優先するのは常に自分の主観だ。ジャーナリストならば客観性や中立性や公正性に配慮しなければならない。もちろん、完璧な客観性や中立性や公正性を達成することなどありえないが、可能なかぎり留意しなければならないと思っている。さらにジャーナリズムにおいては大義も必要だ。不正を許さないこと。公益に奉仕すること。弱者の声を届けること。
これまで書いてきた書籍や撮ってきた映画やテレビ・ドキュメンタリーなどには、前述したジャーナリズムの大義と、かなりの面で被る作品は少なくない。でもそれは、これまでのテーマの多くが社会的な問題と重なったからであって、大義が先にあったわけではない。
ずっと優先してきたのは、徹底して自分の興味や好奇心だ。撮ったり書いたりしているとき、客観性や中立性や公正性などについて考えることはほとんどない。いや、ほとんどじゃない。まったくない。これでジャーナリストなど名乗れるはずがない。社会派でもない。たまたま興味を持ったテーマが、社会的で政治的だっただけなのだ。
***
だから考える。いつからこういうことになったのか。僕にとっての原点はオウム真理教の映画『A』だ。映画祭や上映会などでは上映後に、「なぜオウムを撮ろうと思ったのか」「なぜオウムの施設に一人で入ることができたのか」などとよく質問されるけれど、そもそもオウムを撮った理由は、この時期に僕がテレビディレクターだったからだ。
地下鉄サリン事件が発生してからほぼ1年、メディアはオウムバブルの時期だった。テレビは早朝から夜中までオウムの特番だらけ。オウム関連以外の企画はほぼ通らない。だからドキュメンタリーの被写体にオウムの現役信者を選択した。オウム真理教に対しては、どちらかといえば強い興味などなかったはずだ。つまり消去法。あくまでも仕事の一環だ。強い意志や使命感など欠片もない。
一人で撮り続けた理由も、この作品は危険だと判断したテレビ局上層部から撮影中止を言い渡されて撮影クルーに発注できなくなったからだ。自分でこの手法を選択したわけではない。ならばなぜ、所属していた制作会社から解雇されたのに撮影を続けたのかと質問されるけれど、事態を甘く見ていたからと答えるしかない。まさかクビにはならないだろうと思っていたのだ。つまり組織の論理を軽視していた。
メディアの誰もがオウム真理教の信者たちのドキュメンタリーを発想しなかった時期に撮った理由をひとつだけ無理やりに挙げれば、僕の鈍さに由来していると言うしかない。当時の日本社会全般が抱いていたオウムに対する嫌悪や憎悪を、僕は他人ごとのように眺めていた。共有していなかった。これに尽きる。
僕は鈍い。だから組織の中で優秀な歯車になれない。テレビの仕事を始める前、いくつかの会社を転々とした時期があった。もしも当時の上司や同僚たちに訊けば、あきれるほどに使えない社員だったと誰もが口を揃えると思う。
これは余談になるけれど、公開後に『A』が一部で評価されて香港やベルリンやバンクーバーなどいくつもの映画祭に招待されながら、この評価はフロックなんだと僕は自分に言い聞かせていた。才能や実力ではない。だから続編などありえない。あっというまに馬脚を現す。映画はこれ1本にしておくべきだ。ずっとそう思っていた。結果として『A2』を撮ってしまったけれど、あのときの不安と躊躇いは今もはっきり覚えている。
とにかくどこからどう考えても、僕の資質はジャーナリスティックな要素とはほど遠い。政権批判とかメディア批評とか、できることならやめたい。それに見合うだけの取材力もないし、知識や教養もない。要するに分不相応なのだ。
ただし分不相応ではあっても、今の社会や政治について物申すことはしていいはずだ。特に『A2』発表以降から現在に至るまで、執筆を生活の糧にしてきた期間は長い。そして書くためには、さすがに最低限の勉強をしなくてはならない。読書だけではなく実際に多くの場に足を運び、多くの人に話を聞いた。それは僕にとって、書いたり撮ったりするうえで大きな糧になっていることは間違いない。
***
ポーランドにあるアウシュビッツ=ビルケナウ強制収容所に行ったとき、最後の所長だったルドルフ・ヘスが居住していた家に案内された。子煩悩で家族思いのヘスは、ドイツから妻と五人の子どもたちを呼びよせて、鉄条網の外に小さな家を建てて家庭菜園を作り、一家仲良く暮らしていた。
もちろん家はもう解体されている。でも敷地は残っていた。ふと目を上げて、僕は衝撃を受けた。その家からユダヤ人の遺体を焼いていた焼却所までは、歩いて数分の距離だったのだ。仲睦まじく暮らす家族たちの目に、煙突から立ち昇る黒い煙はどのように映ったのだろう。処刑台に送られる直前に、ヘスは以下の言葉を残している。
私はそれとは知らず第三帝国(ナチス)の巨大な虐殺機械のひとつの歯車にされてしまった。その機械もすでに壊されてエンジンは停止した。だが私はそれと運命をともにせねばならない。世界がそれを望んでいるからだ。
ヘスと同じくナチス親衛隊員でユダヤ人移送の最高責任者だったアドルフ・アイヒマンも、家族思いで愛妻家だった。彼が裁かれる法廷を傍聴したハンナ・アーレントは「凡庸な悪」という言葉を想起して、その著書『エルサレムのアイヒマン』において、アイヒマンの罪は多くの人を殺したことではなくナチスという組織の歯車になったことだ、との論を展開している。
ヘスはユダヤ人虐殺現場の歯車のひとつで、アイヒマンはユダヤ人を虐殺現場へ輸送する歯車のひとつだった。2人だけではない。ナチス宣伝相のゲッベルスや副総統だったゲーリング、金髪の野獣と言われたゲシュタポ長官ラインハルト・ハイドリヒ、親衛隊のトップにいたハインリヒ・ヒムラー、ホロコーストに加担した彼らナチス高官たちも、組織の歯車として多くの人を殺害し続けた。ナチスだけではない。誰もがアメリカに敗けることを予想しながら無謀な戦争を始めた大日本帝国。総計で数千万人が犠牲になったといわれるスターリンの大粛清と中国の文化大革命。ルワンダやクメール・ルージュの大虐殺、同国人8万人を殺したといわれる韓国の4・3事件。まだまだいくらでもある。日本における朝鮮人虐殺、連合赤軍やオウム真理教の事件、あるいは安倍政権以降ずっと続いている官僚機構の文書捏造問題なども含めて、組織共同体が大きな過ちを犯すとき、歯車になった人たちが実直に駆動していることは共通している。
チャップリンはその監督作『モダン・タイムス』で、この時期にフォード自動車が採用していたベルトコンベア式工程への批判を込めて、あの有名な歯車に巻き込まれるシーンを呈示した。組織は個を幸せにしないとのメッセージだ。
でも機械は歯車がなければ動かない。もしもその組織を構成する人たちの多くが、『A』を撮り始めたときの僕のように、場を見ることが苦手で空気に対して鈍い歯車だったとしたら、その組織は早晩に不具合を起こして大混乱しながら機能停止するはずだ。
だから歯車は重要だ。でもこのとき、何か変だなとかちょっと違うかもと思ったとき、それを言葉にしたり動きで示したりすることを忘れない個でありたい。違和感を表明できる歯車であってほしい。それだけで集団の暴走や過ちは、大きく回避できると思うのだ。
***
ここに掲載されているのは、基本的には2017年から2022年までの期間に、いくつかの雑誌や新聞に寄稿した原稿のアンソロジーだ。一貫したテーマはない。でも時代性は確実に息づいている。そしてそれは、少なくとも同時代にこの国に暮らしている人たちならば、共有できるテーマのはずだ。
ただし多くの人と共有できるテーマではあっても、「鈍い」からこそ、時おり多くの人と僕は視点がずれる。つまりコントロールに難がある速球型のピッチャーだ。たまたまストライクゾーンに入れば威力を発揮できるけれど、逸れるときはすさまじい。
そう思いながら読んでほしい。どれがストライクなのかボールなのか、それは(あらためて書くまでもないけれど)読む人一人ひとり(つまりあなた)の判断だ。
[書き手]森 達也(映画監督・作家)
ALL REVIEWSをフォローする