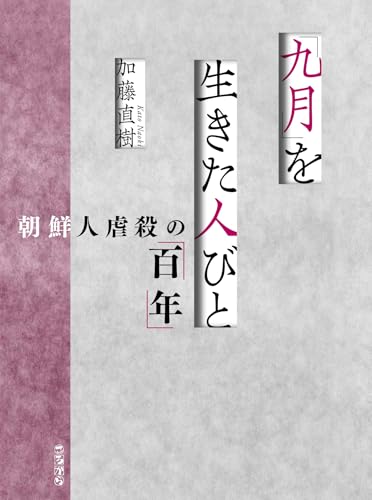書評
『禍』(新潮社)
体の奥まで、世界の果てまでの旅
世界を席捲したパンデミックのせいで、「禍」という字はすっかり馴染みのものとなり、「か」と打つと手元のパソコンでは勝手に変換されてしまうくらいだ。もちろん、本書のタイトルはコロナとは関係ないし、安易にあの疫禍と関連づけられることはきっぱり拒むようなユニークな短編が七編、収録されている。寡作で知られる作家は、十年以上の時間をかけて、この短編集を織り上げたのだという。
それでも、つい、目や耳や口といった器官がいかに異物の侵入に対して無防備かを体験した後ならではの怖さを感じるように思うのは読み手の状態のせいだろう。
七つの短編は登場人物も描かれる世界も違うけれども、共通してモチーフになっているのは、人間の体の一部である。口、耳、目、秘部、鼻、髪、そしてラストは皮膚、だろうか。あるいは人体の細胞全部がまるごと、だろうか。
幻想小説集、または怪奇短編集と呼ばれるのかもしれない本書の、どの物語でも、その身体器官に、予想もつかないものが入る、あるいは予想もつかないものが器官から出てくる。ずるずる引きずり込まれたり、突発的に何かが飛び出してきたり、がさついたものを呑み込んだり、肉に分け入ったり。それらは皮膚を這うような、あるいは体の内部をまさぐられるような執拗な文体によって、ぞわぞわと体感させられることになる。
孤独な人間の奇妙な一日のようにして多くの物語は始まるのだが、読者がぼんやりと想定したような方向へは、けっして流れて行かない。あっけにとられながら、禍々しい物語に引っ張り込まれ、のめり込んでしまうのは、一つにはその強靱な文章ゆえだ。
「耳もぐり」という一編はことのほか奇妙だ。ある男(らしき人物)のひとり語りで幕を開ける。男はアパートの隣の部屋に住む女性を訪ねてきた別の男に話しかけている。失踪した恋人の行方を知りたがっている相手に、「ほかの誰も知らなくとも私だけは知っています」と思わせぶりな前置きをして、しかし男は「耳もぐり」という奇妙な秘儀について語り出す。鍵形にした指を他人の耳に入れてずるりともぐり込み、肉体をのっとる。話は男がその秘儀を会得した四十年も前にさかのぼり、脱線なのか本筋なのか、一向に失踪した恋人の話は出てこない。しかし、あまりに奇天烈でおもしろいので、読者は話のきっかけなど、半分忘れて読み進む。そうするうちに、文章自体が歪み始める。なぜなら、男(らしき人物)は、厳密には「ひとり」ではないからだ。
七つの短編はそれぞれ、文体も異なる。文字だけで読者に体の奥の奥まで、そして奥を突き抜けて世界の果てまで旅をさせてくれるのは、まさに小説を読む醍醐味と言えるだろう。
「耳もぐり」以外の各編について言えば、「食書」は本を食べる話、「喪色記」は目を通して異世界とつながる話、「柔らかなところへ帰る」は豊満な肉体に溺れる話、「農場」はハナバエという不思議なものを育てる話、「髪禍」は髪と新興宗教の話、「裸婦と裸夫」は文明がひっくり返る話と言えるかもしれない。ひとことどころかこの紙面で説明するのは到底不可能、「読んで」というしかないが、『禍』を読むのはじつに「至福」の体験である。
ALL REVIEWSをフォローする