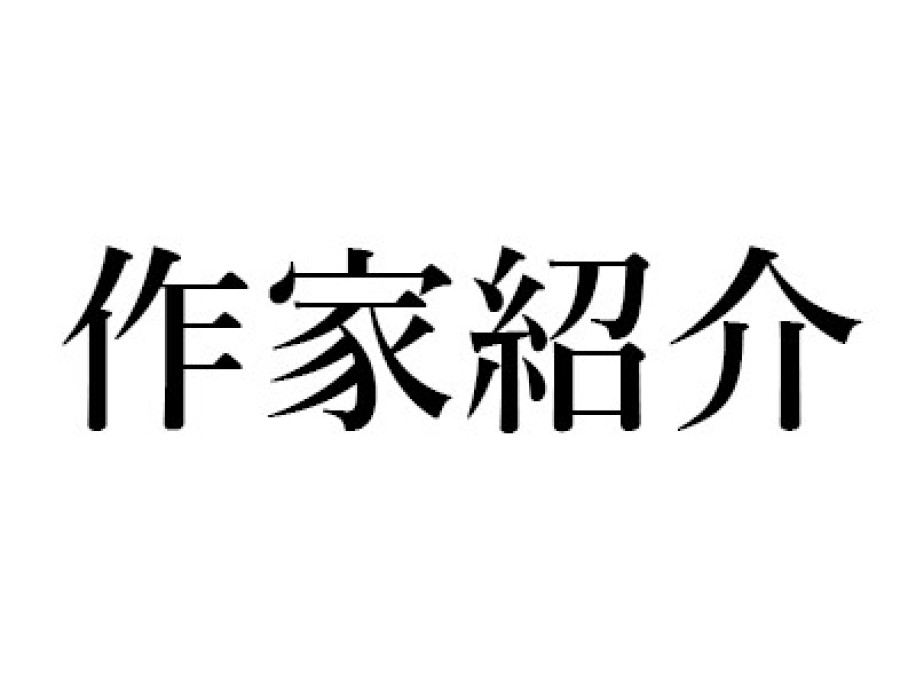書評
『移民船から世界をみる: 航路体験をめぐる日本近代史』(法政大学出版局)
移住者の心伝える、南米への航海日記
移民といえば、外国人労働者の受け入れを連想するかもしれないが、日本もかつて国策として海外移民を奨励し一九〇八年から一九七三年までの六十五年のあいだ、ブラジルだけでも約二十四万人の日本人が移民した。その経緯は送り出し側と受け入れ側の視点から語られることが多く、移民船の歴史と移民たちの航路体験にはほとんど目が向けられてこなかった。南米への移民船は乗客数が多いだけでなく、航海日数も長い。数百人から数千人もの大集団が四十日から六十日余のあいだ狭い空間のなかで共同生活を営んでいた。船のなかで移民たちはどのような日々を送り、秩序の維持や公衆衛生の管理がどう行われたのか。著者はこの未踏の領域に目を付け、辛抱強い資料調査と緻密な史料分析を通してその全容に迫った。
明治初期の移民船については、乗船者の詳細や船内の日常など不明な点が多いが、明治末期になると、移民船の仕様や性能、船客数などの記録が残っているだけでなく、移民船に乗り込み、現場の様子をレポートするジャーナリストも現れた。船内の食住環境、船員と乗客のトラブル、赤道祭や「慰労会」などの行事、船内発行の新聞やポルトガル語講習会などが記されている。
船が日本を離れ、移民先の国に到着するまでのあいだはほんらい司法や行政の空白期にあたる。しかし、移民輸送監督者や助手がつけた「移民輸送日誌」によると、一九二〇年代の後半には、船のなかで日常生活は整然と営まれていたという。行政組織のかわりに家長会、婦人会、青年会、各道府県人会などの自治組織が活動しており、船内の役割分担に応じて、監視係、風紀係、演芸係、運動係、教育係などが配置されている。彼らは定期的に会議を開き、船内生活の秩序維持に努めた。移民船のなかでは幼児教育と小学校教育が行われており、小学校開校式、幼稚園開園式も挙行されたことには驚いた。
本書の白眉は一九二八年十二月二十二日に神戸を出港し、翌二九年二月十一日にブラジルのサントスに到着した、まにら丸の航海についての考察である。著者は二〇一九年、熊本県八代市野崎の民家で発見された「航海日記」を調査し、全文の画像をデジタル化して翻刻した。航海士が記す航海日誌や、移民監督側がまとめた移民輸送日誌と違って、移民がみずから記録し、編纂したものである。
そこから見えたのは、移民乗船者の自己管理意識の高さだ。彼らは見知らぬ大地に向かう緊張感のなかでも、日常の余白に彩りを添えることを忘れない。その根底にあるのは、母国日本との一体感であり、「一等国」の国民に恥じないよう、行動する自制心である。
世界的に見ると、移民は迫害からの逃亡か追放によるものもあれば、経済的な理由によるものもある。定住を前提とする場合、国を捨てるという覚悟を要する。それに対し、南米への移民は食い詰めたあげくの選択とはいえ、当事者たちは国を追われたという認識はない。地球の最果ての地に思いを馳せ、心に希望の蠟燭を灯しながらも、生まれ育った土地の民という自覚を捨てていない。この意外な一面が航海体験の再現を通して浮き彫りにされた。
ALL REVIEWSをフォローする